

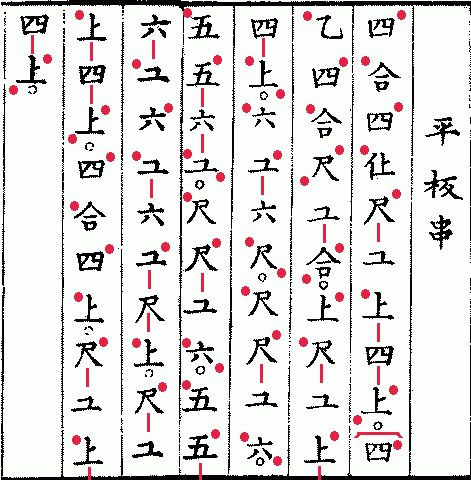
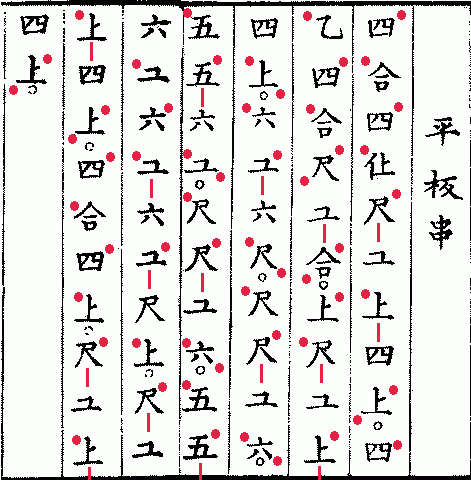
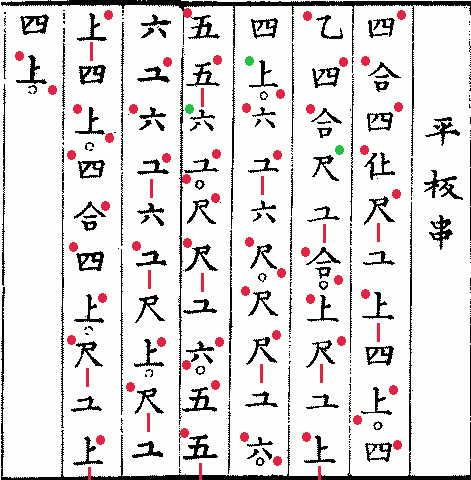
|
四−合−|四−仩−|尺工上四|上−−○| [四−乙−|四−合−|尺−−工|合−−○| 上−尺工|上四上−|−○六−|工六尺−| −○尺−|尺工六−|−○五−|五六工−| −○尺−|尺工六−|−○五−|五六工−| 六−工六|工尺上○|尺工上四|上−−○| 四−合−|四−上○|尺工上四|上−−○|] ■ 再現曲 |
四−合−|四−仩−|尺工上四|上−−○| 四−乙−|四−合−|尺−工合−|−○上−| 尺工上四|上−−○|六−工六|尺−−○| 尺−尺工|六−−○|五−五−|六−工−| −○尺−|尺工六−|−○五−|五六工−| 六−工六|工尺上○|尺工上四|上−−○| 四−合−|四−上○|尺工上四|上−−○| ■ 再現曲 |


|
|
四 合 四 C 尺 工 上 四 上。四 乙 四 合 尺 工 合。上 尺 工 上 四 上。六 工 六 尺。尺 尺 工 六。 五 五 六 工。尺 尺 工 六。五 五 六 工 六 工 六 工 尺 上。尺 工 上 四 上。四 合 四 上。尺 工 上 四 上。 |
四−合−|四−C−|尺工上四|上−−○| 四−乙−|四−合−|尺−−工|合−−○| 上−尺工|上四上−|−○六−|工六尺−| −○尺−|尺工六−|−○五−|五六工−| −○尺−|尺工六−|−○五−|五六工−| 六−工六|工尺上○|尺工上四|上−−○| 四−合−|四−上○|尺工上四|上−−○|] |
|
<a2> <g2> |<a2> c2 |de c<a> |c2.r4 | <a2> <b2>|<a2> <g2> |d2.e |<g2.>r4 | c2 de |c<a> c2& |cr4 g2 |eg d2& | dr4 d2 |de g2& |gr4 a2 |ag e2& | er4 d2 |de g2& |gr4 a2 |ag e2 | g2 eg |ed cr4 |de c<a> |c2.r4 | <a2> <g2> |<a2> cr4 |de c<a> |c2.r4 | |
a2 g2 |a2 >c2< |de ca |c2.r4 | a2 b2|a2 g2 |d2.e |g2.r4 | c2 de |ca c2& |cr4 g2 |eg d2& | dr4 d2 |de g2& |gr4 a2 |ag e2& | er4 d2 |de g2& |gr4 a2 |ag e2 | g2 eg |ed cr4 |de ca |c2.r4 | a2 g2 |a2 cr4 |de ca |c2.r4 | |