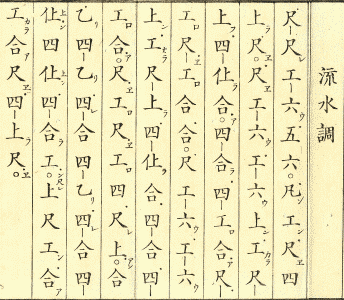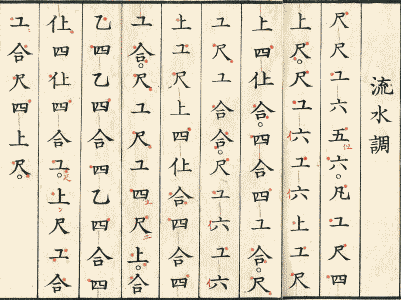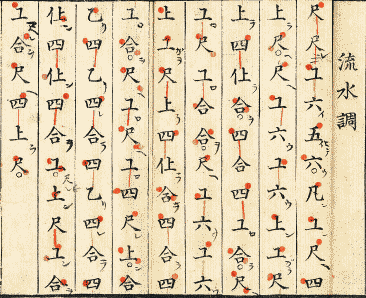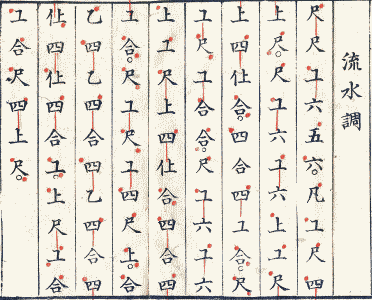古い工尺譜の本では「流水板」について 「西洋音楽の1/4拍子にあたる。」 と解説したものが多い。
しかし,中国の工尺譜における「板・眼」による付点法(「板式」)というものは,要は打楽器のリズムパターンを表したものであって,いわゆる西洋音楽の「何拍子」というのとは多少異なる。すなわち「板(×)」とは打楽器が強く打たれる箇所,「眼(・)」のほうはそれより弱く打たれる箇所,というだけのことであり,よって「板」のみで「眼」が打たれない「流水板」とは,「打楽器の発音箇所がぜんぶ強打」ということである。
「板」を仮に「ドン」とし「眼」を「ジャン」としよう。
「ドン ドン ドン ドン」とのみ打楽器の鳴らされるのが「流水板」である。
「一板一眼」は「ドンジャン ドンジャン」(2/4と解説されることが多い)。
「一板三眼」は「ドンジャンジャンジャン ドンジャンジャンジャン」。
といったことである。これらはあくまで,実際の演奏に即した打楽器の発音位置を示したものであり,フレーズが複雑になってくると,実際の打楽器の音を伴わない「腰板」「腰眼」(虚板・虚眼)といった符号を付して拍子や音長の区切りが指示される。仮に「腰板」を「パ」「腰眼」を「チ」と,打楽器のミュート音で表現するならば「ドン パ ドン パ」も「流水板」なら,「ドン ドン パ ドン パ パ」も「流水板」,「一板一眼」とあっても実際には「ドン ジャン チ ドン パ ジャン ドン パ ジャン チ ドン 」といったこともある。すなわち曲全体としては,実際には2/4だったり4/4だったりするわけである。
「板式」には上記のほかに「板」の入らない自由演奏を「散板」というものと「加贈板的一板三眼」というぜんぶで五つの形式がある。もっとも一般に用いられるのがこの後者で,実際に打楽器が発音される記号(実板・実眼)と虚板・虚眼が,合わせて8種類もある。これもつまりリズムの種類からいうと4/8だが,大別すれば2/4----2拍子の曲と実質的には同じ,これらを組み合わせれば5/8や7/8というジャズのようなリズムも指示表記が可能なわけである。
日本の清楽の付点法や筆者の再現でいうと,中国の「板式」の「板」がオモテ拍点,「眼」がウラ拍点にあたる。ただ中国の工尺譜の付点法には,日本の清楽の付線にあたるものがなく,符音の長短はおもに,「板・眼」と符字間の空隙やその文字の大小の関係によって読み解かれるのが一般的である。
すでにほかの曲でも触れたように。日本の清楽の曲題における「流水」という語は,こうした付点や演奏形式上の「流水」とは関係なく,一般には歌の入らない器楽曲(厦門流水・中山流水など),または清楽家自作の曲に「○○流水」というよう,その作家の号を冠する語として用いられている(徳健流水・渓菴流水など)。
おもえらく,清楽における頭拍子のみの付点法は朱点の「●」を「×」に替えれば,ほぼそのままで中国の板式の「流水」となる。中国にも「流水」と題する器楽曲・俗曲の類はあり,もちろん曲の形式ではなく「流れる水」の方を指す語として「○○流水」と題する曲も存在するが,日本の清楽曲題に「○○流水」というものが多いのは,清人が言語の異なる日本人に曲を伝授するに際し,複雑で難解な板式を以ってするより,多くの曲を「流水」,すなわち一本調子の均等・定長なリズムで(日本の「雨垂れ拍子」のように)教えたところ,名称がきれいなため,これを曲名や曲調の名と勘違いした,そうしたところからきたものではないかと筆者は考える。
中国では打楽器の「拍板」がリズムの基礎であるが,日本の清楽では邦楽の「雨だれ拍子」をとりいれ,おもとして手拍子や膝打ちが教授における「拍子のとりかた」であった。清楽曲を近世譜や五線譜に直したもので,同一の曲であってもこれを2/4とするものと4/4とするものがあることも,上記の中国の付点法における「板式」と,西洋音楽でいうところの「何拍子」という概念との間の乖離の問題と同じようなものとすれば,比較的納得がゆくのではなかろうか。
(参考資料:楊蔭渕『工尺譜浅説』(1962),沈寄『中国音楽指南』(民国10)等 )
* 連山派・『声光詞譜』「新流水」の記事は こちら。
* 四竃訥治『清楽独習之友』をはじめ,いくつかの譜本には「流水調」と題される同題の異曲が収録されている。原譜は2/4だが,曲調の比較のため各符の音長を2倍にし,4/4に組みなおしてみよう。
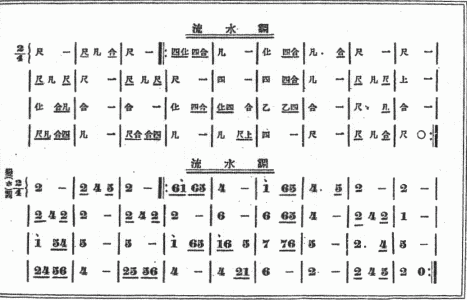
尺−−−|尺凡−合|尺−−−|[四仩四合|
凡−−−|仩−四合|凡−−合|尺−−−|
尺−−−|尺凡−尺|尺−−−|尺凡−尺|
尺−−−|四−−−|四−四合|凡−−−|
尺凡−尺|上−−−|仩−合凡|合−−−|
合−−−|仩−四合|仩四合−|乙−乙四|
合−−−|尺−−凡|合−−−|尺凡合四|
凡−−−|尺合合四|凡−−−|凡−尺上|
四−−−|尺−−−|尺凡−合|尺−−○|]
再現曲 MML譜
ほぼ同じ曲が花井信『清楽指南』では「流水曲」と題されているが,沖野の『清楽曲譜』などに見える「流水曲」は,またこれらとさらに違う曲で,『声光詞譜』においては「流水」と題されている。
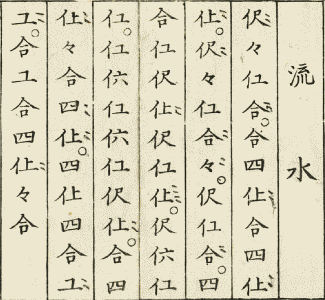
伬−伬仜|合○合四|仩−合四|仩−仩○|
伬−伬仜|合−合○|伬仜合○|四合仜伬|
仩−伬仜|仩−−○|伬𠆾仜仜|仜𠆾仜𠆾|
仜伬仩○|合四仩−|仩合四−|仩○四仩|
四合工−|工○合工|合四仩−|仩合−−|
再現曲 MML譜
曲調は「漫板流水」に近い。柚木友月の『明清楽譜』には「流水(YNK017)」「流水曲(YNK076)」という2曲が収録されているが,この2曲はどちらも上の曲と,後半の曲調に若干の違いがあるだけで,符字順列は完全に一致している。
| 柚木『明清楽譜』「流水」 | 「流水曲」 |
|
伬−伬仜|合−合四|仩−合四|仩−仩○| 伬−伬仜|合−合−|伬仜合−|四合仜伬| 仩−伬仜|仩−−○|伬𠆾仜仜|仜𠆾仜𠆾| 仜伬仩−|合四仩−|仩合四−|仩−四仩| 四合工−|工○合工|合四仩−|仩合−−| |
伬−伬仜|合−合四|仩−合四|仩−仩○| 伬−伬仜|合−合−|伬仜合−|四合仜伬| 仩−伬仜|仩−−○|伬𠆾仜仜|仜𠆾仜𠆾| 仜伬仩−|合四仩−|仩合四仩|−四仩四| 合工−工|−合工合|四仩−仩|合−−−| |
前者は『声光詞譜』の版とほぼ一致し,後者も4列3小節目の「四」を1拍に縮め,終曲部分を整えたという程度のもののようである。
* 長崎派・柴崎孝昌『明清楽譜』より「流水調」。
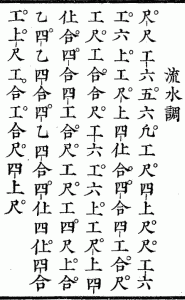
尺尺工六|五−六−|凡−工−|尺−四上|
尺−−−|尺−工六|工−六−|上−工−|
尺上四仩|合−−−|四合四工|合−−−|
尺−−工|尺−−工|合−合−|尺−工六|
工−六−|上−工−|尺上四仩|合−−−|
四合四工|合−−−|尺−−工|尺−−工|
四−尺−|上−−−|合−乙−|四乙四合|
四乙四合|四仩四−|仩−四合|工−−−|
上尺工−|−−合−|工−合−|尺−四上|
尺−−−|
再現曲 MML譜
符字順列は渓派の譜と完全に一致する。近世譜2列3・4小節の「工−六−|上−工−|」が『清風雅譜』では「工六上−|工−」となり,以下が半小節ぶん前送りになっている。頭点だけなので4列1・2と6列3・4小節の「尺工」は「尺−工−|」かもしれないが,ここは渓派の譜に倣う。ほか音長の異なる点がいくつかあるが,これも連山派の譜同様,曲尾は小節内にぴったりおさまる。同じく長崎派の『瑞蘭派清楽譜』には「流水」と題される曲が2曲あり,一方は『声光詞譜』の「流水」と同じもの,もう一方はいまのところ類例のない未知の曲である。