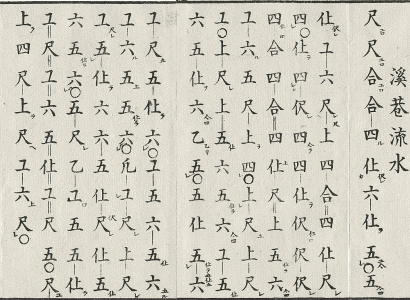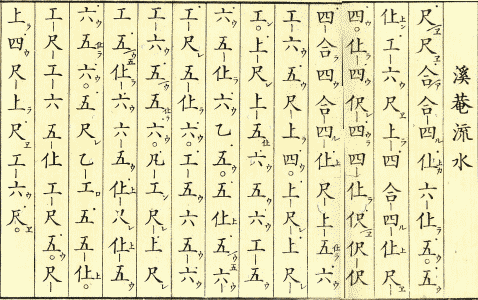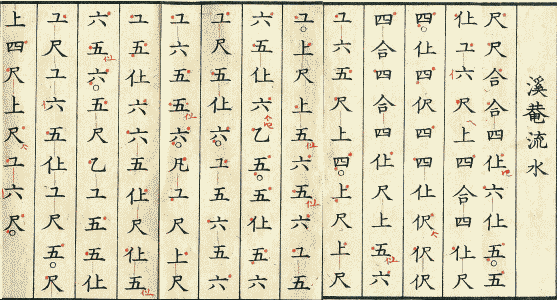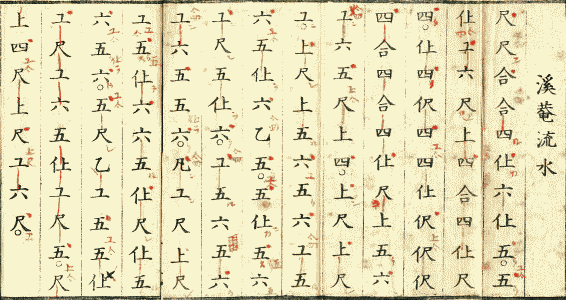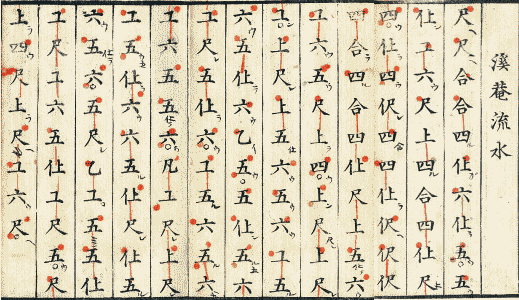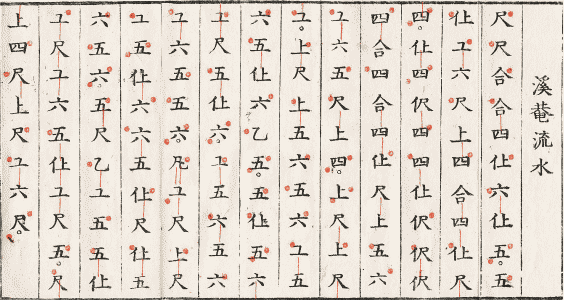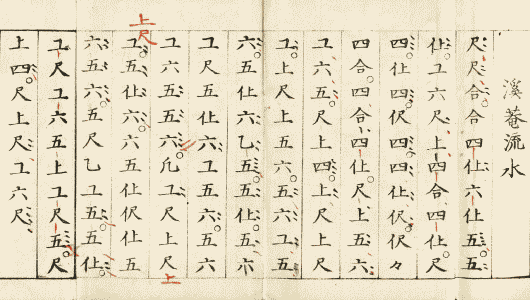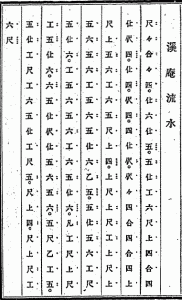*連山派『声光詞譜』より「渓庵流水」。
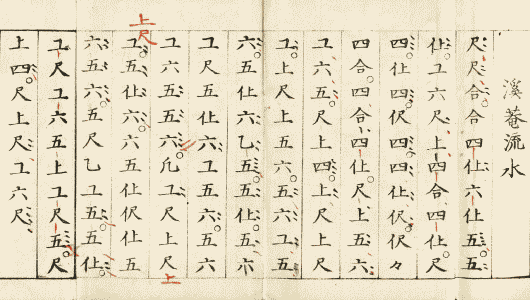
付点の指示が全体に難解,また9〜10行目に入れられている朱字の「上上尺」も本譜に追加するものなのか,装飾符ととらえるべきなのか不明であるなど,読み解き上の問題が多いため正確な近世譜への変換と再現曲が行い得なかった。ここでは譜画像のみの紹介とする。符字順列と拍点の比較から,柚木友月『明清楽譜』所載の譜が,この『声光詞譜』の系統の付点を整理したものと思われるので,あるていど確証のある同派のこの曲の再現としては,まずこれを挙げよう。
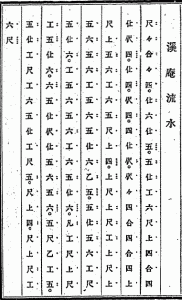
尺− 尺−|合− 合四|仩− 六仩|五−−○|
五− 仩−|工六 尺上|四合四 仩伬|四−−○|
仩四−○ |伬四○四 |仩伬○伬 |伬四合 四合四|
上尺上 五−|六− 工六|五− 尺上|四−−○|
上−−尺|上− 尺−|工− 上尺|上五 六−|
五− 六−|工五 六−|五仩 六−|乙− 五−|
−○ 五−|仩− 五−|六工 尺五|仩六○工 |
五六 五六|−工 六五|−仩 六−|−○ 凡−|
工尺 上尺|工− 五−|−仩 六○|六−−五 |
仩伬 仩五|六− 五−|六−−○|五尺 乙工|
五○ 五−|仩− 工尺工六|五仩工尺 五○|尺上 四○|
尺上 尺−|工六 尺−|−− |
再現曲 MML譜
ピンク色は,渓派の譜と比較した場合に相違のある箇所である。
付点の指示は最初に挙げた『声光詞譜』の手写点より明確であるため,再現はほぼ間違いないと思われるが,渓派のものと比べると曲調に不自然さのあることは否めない。まず2列4小節目の「四」が4拍となっており(渓派では3拍),ここから標準譜と比べ1拍のズレが生じるが,これは3列4小節目で「合四」を8分×2とすることで解消されている。続く「上尺上」(*仩尺上)の音長は渓派では4分+8分+8分,5列2小節目の「上尺」は渓派では4分半+8分,あるいは4分+4分なので,ここから2拍・半小節増のズレが生じている(上記『声光詞譜』の譜でここは4分+4分)。7列2・3小節目の「五六」は渓派では2分半+4分,ここで1拍減じて1拍増となり。同列4小節目の「六」が4拍から2拍となって,ここでズレは−1拍となる。再現曲を聞き比べた際,プラスマイナス2拍のズレだと,拍子のオモテ/ウラが反転するだけなのでさほどの不自然さは感じないが,1拍や3拍となると拍子と合わなくなるため,このあたりからおかしく感じられるわけである。8列3小節目「仩(=仩)」,渓派では「五」の2分で,標準譜とのズレは−2拍。ここまでと異なり,符音自体が異なっている。続く「凡−工尺」の部分は渓派では「凡工−尺」,実演奏の感想からすると,ここは渓派の「渓庵流水」においては演奏の要点の一つだと思われるが,音長が違っており,平坦な印象に聞こえる。9列目「六五」は渓派では4分×2,なぜここを伸ばすのかは理解できないが,これにより−2拍のズレが解消され,以下1列半小節は渓派の譜と同じだが,10列1〜2小節の「五仩」(渓派4分×2)が2分×2となっていることで,ふたたび2拍増,拍子の反転した状態のまま終曲に到り,全体では渓派のものより半小節ぶん多くなる。
次いで同派・沖野勝芳『清楽曲譜』の「渓氏流水」では,各符の音長を縮小した譜が見える。これを譜の比較のため2倍に引き伸ばすと以下のようになる。

尺− 尺−|合− 合四|仩− 六仩|五−−−|
五− 仩−|工六 尺上|四合四 仩伬|四−−仩|
四−−伬|四− 四仩|伬−伬伬|四合四 上尺上|
五− 六−|工六 五−|尺上 四−|−− 上−|
−尺 上尺|工− 上尺|上五 六−|五− 六−|
工五 六−|五仩 六−|乙− 五−|−− 五−|
仩− 五−|−六 工尺|五仩 六−|−− 工五|
六五 六−|工六 五−|五− 六−|−− 凡−|
工尺 上尺|工− 五−|−仩 六−|六五 仩尺|
仩五 六−|五− 六−|−○ 五尺|乙工 五−|
五仩 工尺工六|五仩工尺 五−|尺上 四−|尺上 尺−|
工六 尺−|−○ |
再現曲 MML譜
前半は渓派のものとあまり変りがない。沖野は音楽活動の幅の広い人物だったようなので,清楽家としての伝系は連山・梅園派だが,渓派など他流の演奏もあるていど分かっていて,譜を修整したのかもしれない。 原譜6小節目 「伬 伬 伬 四 合 四 上 尺 上|」,原譜の指示のままだと1小節4拍半の長さとなる。「四合四」と「上尺上」は他から考えても8分+16分+16分(音長2倍で4分+8分+8分)になるはずであるが,渓派の譜ではこの「四合四」の前にさらに「合四」の4分+4分が入っている。この部分は後刊の『洋峨楽譜』でもこの部分は同じなので,彼の伝系ではそうなっていたものだろう。このためここから渓派の譜と2分・半小節ズレ,拍子が反転している。8〜9列目「凡工−尺」が「凡−尺工」となっているのは柚木の例と同じである。ただしこの2箇所と,符が1オクターブ上の高音になっている箇所が1〜2あるほかは,渓派の譜とほとんど一致している。
先行する四竃訥治『清楽独習之友』の譜も沖野の譜同様に4/4ではあるが,渓派の譜と比べ各符の音長が1/2となっている。こちらも比較のため音長を2倍とし,4/4の譜に組んでみよう。

再現曲 MML譜
|
尺− 尺−|合− 合四|仩− 六仩|五−−−|
五− 仩−|工六 尺−|○上 四−|合四 仩−|
○尺 四−|○仩 四−|○伬 四−|四仩 伬伬|
四合 四合四|仩尺上 五−仩|六− 工六|五− 尺上|
四−−−|上− 尺−|上尺 工−|−− 上尺|
上五仩 六−|五− 六−|工六 五−|五仩 六−|
−乙 五−|−○ 四−|仩− 五五六 |工尺 五仩|
六− 工五|六− 五六|工六 五−|五仩六−|
−−凡工|−尺 上尺|工− 五五仩|六− 六五|
仩− 尺仩|五− 六−|五仩 六−|−− 五尺|
乙工 五−|五仩 乙工|五− 五仩|工尺工六 五仩工尺|
尺仩 四−|尺上 尺−|工六 尺−|−− |
|
2列2〜3小節,「尺−○上」は渓派の譜では半分の4分半+8分。続く「四−合四」も4分+8分+8分。「仩−○尺」は4分半+8分。この3箇所で6拍・1小節半増で拍子が裏返る。3列4小節目「伬伬」は「伬−伬伬」,2分の「伬」が欠けており2拍減で拍子が戻る。5列2小節目「上−尺−」は「上−−尺」,同3〜4小節に渡る「工」の長音は,渓派の譜では2分の長さである。6列3小節目「工六五」は渓派では「工五六」。原譜3列3小節目はそのままだと1小節5拍となる。「六乙」(近世譜6〜7列目)をそのまま2倍の音長とすると2分半+4分(渓派では2分+2分),ここで四竃の近世譜の小節切りとは以下が半小節ズレとなって合わなくなる。7列3小節目の「五五六」は渓派では「五六」の2分半+4分,音長が半分となりここから渓派の譜と拍子が合うが,つかの間直後8列頭の「六」が渓派の半分の音長,2小節目「六五」は渓派では4分半+8分,もしくは4分+4分,続く「六」は2分である。9列3小節目「五五仩」は渓派では「五仩」で2分半+4分の長音,逆に10列目頭は「仩尺仩五」で4拍のところ6拍に伸びている。そして12列目「尺仩(渓派では 尺上)」の前の「五○」を欠いて,全体では1小節半長くなっている。
連山派の付点法だと各符の音長は明確に表示できるが,曲中に緩急がある場合には符音がそのまま伸び縮みしてしまうため,四拍子・二拍子といった定型的な拍子にあてはめて近世譜を組むと,このように不自然な形になってしまうことが多い。音同士の関係やフレーズ単位での再現は単音の拍数をそれぞれに記す連山派の方式よりは,ウラ/オモテ拍点と付線による渓派の付点法のほうが,やや正確かもしれない。渓派の譜が付線の相違は多少あれど,曲調をほぼ正確に伝えているのにくらべると,連山派や四竃をはじめとした後世の近世譜に,このようにどれにも不自然な部分や合致しない箇所があるのは,この付点法の差異,またさらに最初のほうで述べたように,この曲に演奏上容易ならざる箇所,またもともと覚えにくい不自然な感のあるフレーズがいくつもあるため,その教授・伝承が完全なものではなかったこともあろう。それはそれで清楽曲の伝承における乱れや,そのパターンが垣間見えて興味深い。
筆者手持ちの長崎派の資料中に「渓庵流水」を収録しているものはない。何杏村(河副作十郎 長崎の人 清朝からの帰化人)の『清楽曲牌雅譜』には収録されているが,由来から案じても,一般に長崎派では演奏されなかった曲と考えてよかろう。