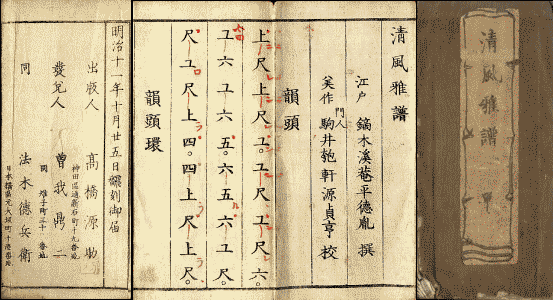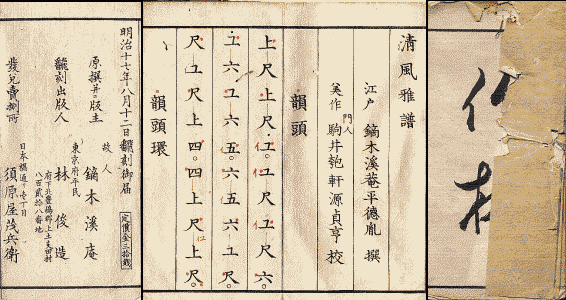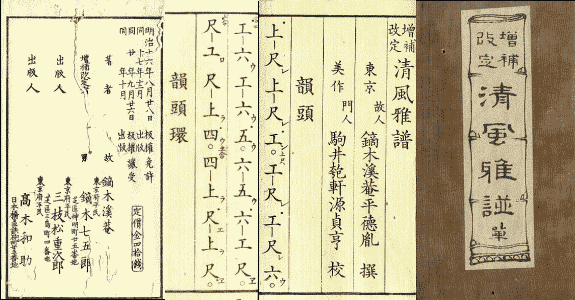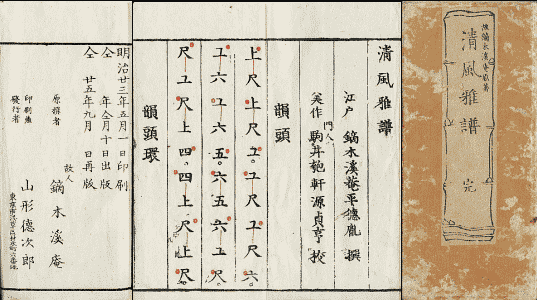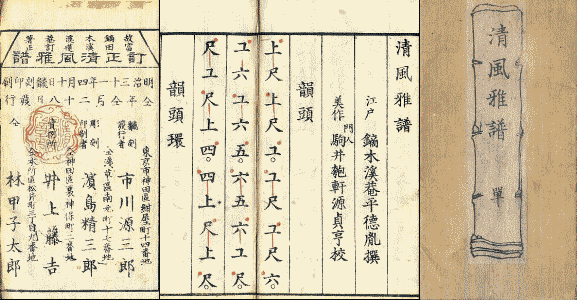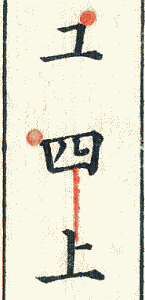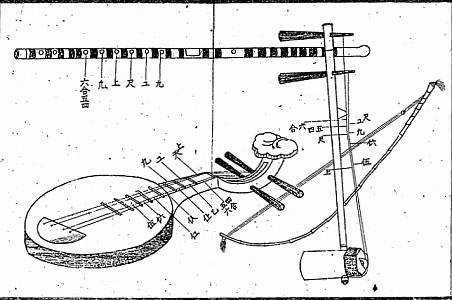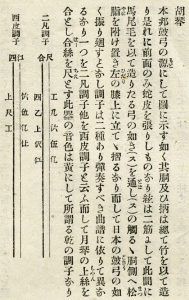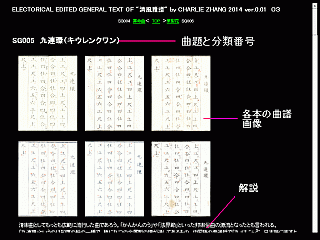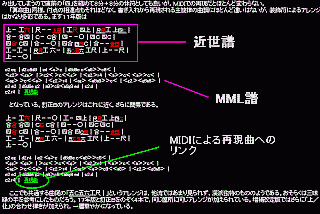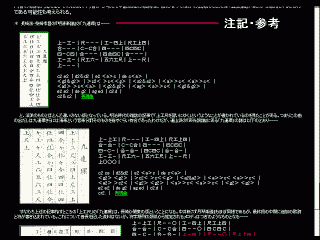以下の本文中において,以上の基礎資料はとくに表記する場合をのぞき,上記見出し太字の略号をもってその書名に代るものとする。
《原譜の読み解きについて》
『清風雅譜』収録の曲譜は中国由来の「工尺譜」によって記されている。
しかし日本の清楽における「工尺譜」はその基本的な部分において,大陸のそれとは著しい違いがある。
「工尺譜」とは,単純に言えばドレミ…にあたる音階を「上・工・尺…」という漢字の順列に置き換えてメロディを表記する,言うところの「文字譜」の一種であるが,中国大陸で一般的な工尺符字の音階順列は----
合 四 一 上 尺 工 凡 六 五 乙
である。「合」を「ソ」,「上」を「ド」とした時のソラシドレミファソラシとなり,「合」の1オクターブ高が「六」,「四」が「五」,「一」が「乙」に対応し,「乙」以上の高音は「仩・伬・仜・𠆩…」と符字に「イ」をつけた文字で表記される。
日本の工尺譜本の曲譜では,このうち「一」の符字,すなわち大陸で「乙」に1オクターブ低とされる符字がなぜかほとんど用いられず,「乙」の字で統一されている。すなわち基本的にその音階は----
合 四 (乙)上 尺 工 凡 六 五 (乙)
となる。後述するが,譜本によく載っている明笛の音階表では「乙」は「合四」の後に,月琴の音階表では「六五」のあとにあり,実際の演奏におけるこの符の音の高低は,使用楽器と前後の符の関係によって,演奏者が決定していたものと考えられる。
つぎに,工尺譜というものは元来,その曲の音階をのみ表記したもので,各音の長さはそこには表現されていない。そこで中国の工尺譜においては,符字横に「板」「眼」という記号を付してリズム楽器の入る箇所を示し,これと符字間の空隙の大小の関係を以って各符の音長関係を表し,曲調を読み解くというのが一般的である。「板」「眼」のきまりは知っていてもなかなか説明しがたいほど複雑なものだが,これによりかなり細かなニュアンスまで表すことができる。
これに対し,日本の清楽では,工尺符字左右の上下にリズムの目安となる朱点(拍点−筆者の造語−と呼ぶ)を打ち,符字間に朱線(付線−同前−)を引く,独特な「付点法」が用いられる(上記「増補改定版」では一部,付点や装飾符が印刷されている)。
点と線の意味合いは流派によって若干異なるが,渓派においては拍点は「雨だれ拍子」,すなわち伝統的な音楽の教授時に,先生が左右の膝を交互に打って拍子をとる,その拍子取りと同意とされている。すなわち右がわの点は右の膝,左がわの点は左膝を打ったもの,と考えればよい。
左右の膝を打って拍子をとる場合,利き腕が右の場合,通常は右手がわからはじまる。ここから筆者は,右がわに打たれる拍点を「オモテ」,左に打たれるものを「ウラ」と呼称している。
また,資料によっては拍点が,この「オモテ」のほうだけしか付されていないものがある。ウラ拍子のタイミングがとりにくい場合など,まずオモテ拍子だけを打ってカウントをとり,練習することがあるのだが,こうした場合の拍子を「頭拍子」という。そこからとって,そうした資料に付される片方だけの拍点を「頭点」と呼ぶことにする。
「頭点」だけの資料は,基本的に単独で読み解くことは出来ない。上記資料のうち11年版と増補改定の2冊は「頭点本」であり,これらからの譜や曲は,ほかの資料のウラ点を参考に読み解いたものである。
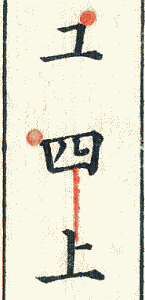
付線は,基本的にはその符字間を「なめらかに弾く」「連続して弾く」もの,と解説されることが多い。短い音,というよりは「音と音との間が短い箇所」に付せられるものである。複数の朱入り譜本を対照した場合,もっとも異なることの多いのが,この付線の位置である。とくに2分半+4分といった不均等な関係や,同じ長さの音が連続する場合などでは,その筆記者もしくは教授者の感覚や好み,音長の解釈の仕方によって,付けたり付けなかったり,あるいは付される箇所が異なったりすることがしばしばある。
日本の清楽の付点法には明確な統一性やしっかりとした基準はないのだが,それでも中国の工尺譜における「板」「眼」によるものと比べると,その基本的な読み解き法は格段に単純・簡素で,分かりやすい。
すなわち拍点1つの音の長さの範囲を4/4拍子1小節の半分と考え,左右2点で1小節とするならば,左の画像の「工」は1拍点半小節の長さなので「2分音符」,「四上」が2つで半小節だから「4分+4分」,あわせて1小節,ということになる。
この拍点と付線は,譜本の購入者が曲を教授された折に,装飾符などとともに自分で書き入れるものだが,このほか曲譜読み解きの手がかりとなるものとして,「句点」がある。「句点」は符字の下,もしくは下の左右どちらかに印字されていることが多い「○」もしくは「。」の類で,これは主にフレーズの区切りや,明笛における息継ぎ箇所を表す。
通常,こうした句点で区切られる直前の音は長音であることが多いため,再現MIDIにおいて,筆者はこれを1拍の休符とし,直前の音に組み込むこととしている。すなわち直前の音が4/4における全符であった場合,これを2分半+休符という形に替え,2分音符であった場合は4分+休符とする。しかし直前の音が2分以下の長さであった場合は,再現上ほとんど分からないため,基本的には無視することとした。
一つのフレーズをどこで切るのか,ということはかなり微妙な嗜好にかかわるものと見えて,これもまた同じ曲でも,版によって異なっていることがあるが,それゆえ逆に,他本の譜との比較をする際に,その同違を判断するための目安ともなっている。



「拍点」はどちらも基本的には符字の斜め上,もしくは真横に打たれるが,一つの符字が2拍点(=全符),もしくはそれ以上の長さとなる場合には,符字の上下に付される場合が多い。
またその符字の音が,拍子の境をまたぐような場合には,点が単独で符字の斜め下に打たれる。このような拍点を「下付き点」と呼ぶことにする。
画像1)の「尺」は単純に長音を表したもの。この「尺」は4/4拍子における全符の長さである。
画像2)の「仩」も2拍点だが,その後の「四」に拍点がない。すなわち「仩」の音の範囲のうちに「四」が含まれているということになる。「四」と次の長音の「仩」との間には付線があるから,この間は短い。そこから「仩」を2分半,「四」を4分と読み解いて1小節とする。
画像3)1拍点下付き点の例である。この場合は3字で1小節だが,「仩」の拍点が下付きとなっている。いちばん上の「四」と「仩」の間が短く,「仩」とそのあとの「四」の間は長く,しかも「仩」の音が拍子の境を渡るということ。すなわち上下の「四」はどちらも4分,真ん中の「仩」が2分ということになる。
「下付き点」は複雑なことが多いので,かならず前後の関係を長めに俯瞰しながら読み解くことが必要である。
以下にもういくつか,工尺譜の再現の例を示してみよう。
横書きなので「
o」をオモテ拍点(原譜では右がわ),「
o」をウラ拍点(原譜では左がわ)としよう。
例:o上工 o尺 o四 o尺工 合。
「付線」はこう表す。
例:o上−工 o尺 o四 o尺−工 o合o。
これを読み解くにおいて,筆者は「近世譜」(筆者の造語)というものを用いる。「近世譜」は明治になって数字譜をもとに考案された改良工尺譜の類を指す。さまざまな形式があるが,ここでは『音楽雑誌』などで四竃訥治らが提唱し,沖野竹亭『清楽曲譜』などで使われた形式を基礎としたものを用いる。
| |が1小節,符字1つが4/4の四分音符,「−」で伸ばす音1拍ぶん,○が休符である。詳しくは後述,《近世譜について》を参照せよ。
すなわち上記の例は,以下のように近世譜に変換される。
例:o上−工 o尺 o四 o尺−工 o合o。 = |上工尺−|四−尺工|合−−○|
少し変えてみよう。「四」にオモテ/ウラ拍点がついているが次の「尺」にはない,この場合は「四・尺」が2分半4分となる。17年版は「尺合」間に付線がないが,増補改定・25年版・訂正ABなどは,こちらに付線を入れることで「合」が短い音であることを強調していることが多い。すなわち,この2例は,付線の違いはあるが,再現される曲調は同じとなる。
例1:o上−工 o尺 o四o 尺 o合o。 = |上工尺−|四−−尺|合−−○|
例2:o上−工 o尺 o四o 尺−o合o。 = |上工尺−|四−−尺|合−−○|
「尺」が全符で,次の拍子にまたがる場合には次のようになるが。
例:o上−工 o尺o o四−尺 o合o。 = |上工尺−|−−四尺|合−−○|
同じ「尺」が2分の長さで,拍子をまたぐ場合には,以下のように下付き点が増えて,読み解きが少し難しくなる。
例:o上−工o 尺o 四o 尺−o合o。 = |上工−尺|−四−尺|合−−○|
「工・尺・四」の拍点が「下付き」。「工」は長音だが「上」と「工」の間は連続するので付線,「四」が長音で「尺・合」間は連続するので付線,と考えるが,所有者が下付き拍点のみで読み解けると考えている場合,付線はまったく付されないこともある。
本文中にもしばしば言及されるが,こうした旧来の付点法では2拍点間を4/4とした場合の四分音符までを表現するのがせいぜいで,それ以下の細やかな表現を指示するのが難しい。たとえば----
例:o尺−工 o尺−工−上。
----と,1拍点内の3字が付線で結ばれている場合がある。これは4分8分8分,もしくは8分8分4分となる指示だが,これだけではどちらなのか判別できない。
まさしくこうしたケースが,複数の版本の必要となる場合である。すなわち,同じ箇所をある譜本は (A)「
o尺
−工
o尺 工
−上。」 とし,別の本では (B)「
o尺 工
o尺
−工 上。」 と結んでいる。
Aは 「尺・工」間 を付線によって表現できない(ほど微妙な)関係としたのであり,Bは1拍子間においてもっとも短い間隔の部分を指示している。すなわちこうして資料を複数並べることによってようやく,この半小節の中では「尺・工」間が最も短い,すなわち「8分8分4分」だ,ということが確定されるのである。同様に4分半+8分の場合は----
例:o上−工 o尺 尺−o四 o尺 工−o合o。 = |上工尺−尺|四−尺−工|合−−○|
という形式が一般的だったようではあるが,8分になる符の後に付線を付さない場合も多い。
概して符音の長さが均等な関係にない場合,またそこに拍子をまたぐ符音が影響を及ぼしているような場合などは,各本の拍点・付線が一致しないことが多い。 これは旧来の付点法が,あくまでも音符同士の相対的な関係をもとにした,未熟な「目安」程度のものであったためである。
《楽器ごとの読み解きについて》
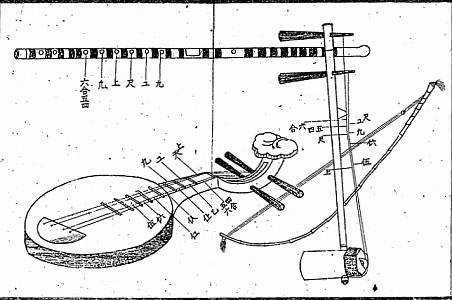
溪派における通常の工尺譜の読み解きには,楽器により,基本的に次のようなルールがある。
1)明笛:
低音楽器なので最低音(全閉鎖)を「合」とし,「合」と「六」は1オクターブの関係になる。ただし低音の「合・四・乙」に隣り合って,もしくははさまれて高音(ニンベンのついた符字)のある場合は,ニンベンのない(1オクターブ下の)音として発音される。 符字による音階の順列は----
合 四 乙 上 尺 工 凡 六 五 仩 伬 仜…
2)月琴:
清楽におけるメイン楽器である月琴は中音楽器,最低音が「上」なので「合/四/乙」の音は「五/六/乙」として弾かれ,「上」と「仩」は1オクターブの関係になり,最高音である「彳」のついた「上」まで,符字はそのまま読み解かれる。 符字による音階の順列は----
上 尺 工 凡 (六/合) (五/四) 乙 仩 伬 仜…
また数は少ないが,低音弦を一音上げた「尺合調」という調弦で弾かれることもある。
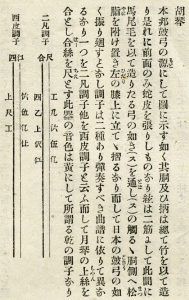 3)胡琴:
3)胡琴:
胡琴は高音楽器で,二つの調弦がある。「二凡調(ねはんてう)」では最低音は「合」とされる。ただしこれは実際には月琴の「六」の音にあたり,明笛の「合」よりは1オクターブ高い音である。「合/四/乙」と「五/六/乙」はいずれも同じ低音域の音として演奏され,その1オクターブ上の音を表わす時にはニンベンを付する。工尺符字の原則からいえば「四」のオクターブ上が「五」,「五」のオクターブ上は「伍」であり,「伵」ということはない。これはこの符字が記号的に使われるものであることを示しており,同じような例は唐琵琶の譜でもある。基本的にニンベンのついた高音はすべて出せる範囲の音に変換される。 符字による音階の順列は----
(合/六) (四/五) 乙 上 尺 工 凡 (イ合/イ六) (伵/伍) (イ乙) 仩 伬 仜…
となる。もうひとつ二線を1音づつ上げた「西皮調(せいぴてう)」もしくは「四工調(スイコンチョウ)」という法があって,最低音は「四」,「四/五」と高音開放弦の「工」にニンベンが付される。この場合の「仜」はいわば指替えの指示で,低音弦の「工」ではなく開放弦を用いるよう注意をうながすためのもので,音の高低には関係がない。
(四/五) 乙 上 尺 (工/仜) 凡 (六/合) (伵/伍) (イ乙) 仩 伬 仜…
基本的には,胡琴譜で「四/五/工」にしかニンベンのない場合が「西皮調」,「合/六/四/五/工」にあるのが「二凡調」である。
この場合の「○○調」というのはチューニングの名前であると同時に,そのチューニングで演奏されるメロディの類も意味する。どちらも芝居で用いられる曲調で,「西皮調」は北方まわりに発展した曲調。「西陂調」「西坡調」と書かれることもある。「二凡調」は南まわりの曲調,中国では「二黄調」もしくは「二簧調」と書かれる。「二黄」は京劇などで特徴的に使われる代表的な曲調であったため,転じて劇音楽そのものをも指すようになった。普通話だと「erfan」と「erhuan」だが,類音として通用させたものである。どちらも現在の京劇が成立する以前にそれぞれ各地の音楽を吸収しながら発展したものである。
もちろん月琴のみでのアンサンブルも盛んに行われていたようだし,さらに打楽器や阮咸・弦子(中国三線/蛇皮線)もしくは唐琵琶などさまざな楽器が加わることもあったようだが,この明笛・月琴・胡琴という三つの楽器の組み合わせというものが,清楽の合奏としてはもっとも基本的で,よくある構成だったようだ。
いま仮に明笛を基音楽器とし,「上=4C」として,それぞれの楽器の音域を,それぞれの楽器における工尺符字の並びとともに,表にしてみよう。まず,胡琴が「二凡調」である場合はこうなる----
| 明笛 | 合 | 四 | 乙 | 上 | 尺 | 工 | 凡 | 六 | 五 | (乙) | 仩 | 伬 | 仜 |
| 実際の音 | 3G | 3A | 3B | 4C | 4D | 4E | 4F | 4G | 4A | 4B | 5C | 5D | 5E | 5F | 5G | 5A | 5B | 6C |
| 月琴 | − | − | − | 上 | 尺 | 工 | 凡 | 六/合 | 五/四 | 乙 | 仩 | 伬 | 仜 | − | 𠆾 | 伍 | − |  |
| 胡琴 | − | − | − | − | − | − | − | 合/六 | 四/五 | 乙 | 上 | 尺 | 工 | 凡 | 𠆾 | 伍 | 亿 | 仩 |
胡琴が「西皮調」の場合は次のようになる。
| 明笛 | 合 | 四 | 乙 | 上 | 尺 | 工 | 凡 | 六 | 五 | (乙) | 仩 | 伬 | 仜 |
| 実際の音 | 3G | 3A | 3B | 4C | 4D | 4E | 4F | 4G | 4A | 4B | 5C | 5D | 5E | 5F | 5G | 5A | 5B | 6C |
| 月琴 | − | − | − | 上 | 尺 | 工 | 凡 | 六/合 | 五/四 | 乙 | 仩 | 伬 | 仜 | − | 𠆾 | 伍 | − |  |
| 胡琴 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四/五 | 乙 | 上 | 尺 | 工/仜 | 凡 | 六/合 | 伍/伵 | 亿 | 仩 |
「上=4C」としたのは,音の関係を分かりやすくするためである。製作者により楽器個々により音の高低は若干異なるが,古い明笛に合わせた演奏実験からすると,実際には「上=E
b〜E」くらい。これより長音2度ほど高かったようである。また明笛の高音の限界を「仜」,胡琴を「仩」としたが,実際にはもう少し上まで発音可能である。ただし古い楽器なので,現在の笛子や二胡にくらべると高音域での安定は悪く,現実的にはこのあたりくらい,譜にもあまりそれ以上の高音の指示はない。
最後に,上記6種を底本とする再現曲に関しては,書き込みによる曲調の差異比較のため,一律同じような楽器の組み合わせ(月琴/明笛/リズム)で再現している。また本来はそれぞれの曲に鼓譜があったものと推測されるが,そのほとんどは不明である。再現曲では原譜の拍点との関係を分かりやすくするため,基本的には同じリズムパターンを採用している。
竹板:|●○○○|●○○○|
砕子:|○○●●|○○●●|
鉦:|○○○○|●○○○| (| |=4/4,1小節,○無音/●発音)
オモテ拍子が竹板(竹の板のカスタネット・拍子木),ウラ拍子が砕子(金属製の板を連ねたもの),これだけだとさびしいので鉦的な音をあざえてある。
《近世譜について》
旧来の工尺譜のままでは,これを学んだことのない一般の読者諸氏にはまったくもって読み解きがたく,また付点の差異によって生じる,同じ曲の各譜本間の曲調の差異なども分かりにくい。本稿では,これをある程度,視覚的・直感的に理解ができるよう,原譜の付点から読み解かれる音長をもとに,「近世譜」に組み直した譜を付した。
「近世譜」というのは,西洋から伝わった数字譜の方式をもとに,明治時代後期に流行った改良工尺譜の類を筆者が総称したもので,さまざまな方式が考案された。本稿採用のものは四竈訥冶『清楽独習之栞』や沖野勝芳『清楽曲譜』などを参考としている。
1)特に記載がない場合には,原譜のオモテ(右)・ウラ(左)の2拍点間を4/4の一小節とする。
2)無標記の工尺譜の符字一文字を1/4音とし,長音はこれに「−」を1拍として付して表わす。
|上■■■| :4分音符
|上−■■| :2分
|上−−■| :2分半
|上−−−| :全符
3)短い音は下線を付し,文字サイズを若干縮めて表わす。
|上尺工■■| :4分+8分+8分
|上−尺■■| :4分半+8分
|上尺工凡■■| :4分+8分+16分+16分
4)休符は「○」を以って表わす。
|上−−○| |上○尺工|
ただし工尺譜>近世譜の変換において,原書で「
o上
o。」「
o尺。」と,長音の後に句点「。」が登場する場合,筆者はこれをそれぞれ「3拍+1拍の休符」(「上−−○|),「1拍+1拍の休符」と変換する。
すでに述べたように工尺譜における句点は,演奏の切れ目,明笛の息継ぎ箇所程度の意味しかなく,かならずしも休符に変換されるべき表示ではないが,MIDIによる再現,また実演奏の上では自然と休符に近い表現となるからである。ただしこの方式は,音符と合わせて2拍,すなわち休符に1拍をあてられる以上の長音にのみ適応され,4/4で音長が4分以下となるようなものにはあてはまらない。再現曲でも実演奏でも,聞いて分からないレベルとなるためである。
5)
[■■■■] 間を繰り返し節とする。
[上尺工凡|:上尺工−|] 上尺工工|
とあるのは「 : 」以降を,一度目は 「上尺工−|」,二度目を 「上尺工工|」 として弾けという指示である。
6)原工尺譜において,「六」以上の高音は「仩」のように,基本の符字に「イ」を付して表現される*が,入力上の便宜,また後述するMML譜への変換上の必要から,本稿近世譜においては上=4Cとして,高音符字を「仩(5C)=C,伬(5D)=D,仜(5E)=E...と全角英文字で表現する。
*3
7)近世譜において,各本の書き込みによる装飾符は基本的に赤文字で標記する,たとえば 「尺工合−|」 の「合」に「工尺」という装飾符がついている場合には 「尺工合
工尺|」, 同じく「尺」に「四」が付された場合には 「
尺四工合−|」 などと表示される。
装飾符は邦楽で言うところの「アンコ」にあたり,各演奏者があるていど自由に入れたものなので,「定番」「定型」というものはあっても,それ自体に正確なきまりはなく,正確な音長はほぼ不明である。たとえば 「尺−−−」 という全符に「尺合」という装飾がつくとき,演奏者がこれを 「尺−
尺合」 としていたか 「尺−−
尺合」 としていたのかは,正直分からないことのほうが多いが,基本的には原符の音長を越えず,拍子の領域を越えない範囲ならば,多少長くても短くても再現される曲調上にさほどの違いはない。他本の資料や,また実際に演奏してみた結果などを参考に,適宜判断することとする。
《MML譜について》
MMLというのは,パソコン初期の頃に開発された音楽の既述法で,簡単に言えば「ド」という文字を打ち込めばパソコンから「ド」の音が出るようにするための技術である。筆者は再現した近世譜を,この既述法に変換して本稿中のMIDI曲を作成している。MMLは基本的には数字譜や文字譜と同様のものなので,工尺符字をMMLで使う文字や記号へ変換すれば済む。複雑なDTMソフトを用いなくても音楽への変換が可能なためである。
MMLの形式は複数あるが,だいたい共通しているのは,音階を abcdefg のアルファベット7文字で表わし,2 4 8 16 といった数字と組み合わせることで1音を表わすというところである。つまり2eと書けばミの2分音符,8cと書けばドの8分音符というわけである。休符は「r」で表現され,オクターブ上げたいときは音符前に「>」を付し,下げたいときには「<」を付せばよい。
クラッシック音楽やギター等の経験のある方は「abcde…」が「ラシドレミ…」と同じ意味を持つことはご存知だろうから,見慣れれば五線譜とあまりかわりなく読み解くことが出来,しかも基本的には言語を選ばない,どこの国の者にでも理解できるようになっている。
MMLの楽譜を音楽に変換するソフトはいくつもある。興味のある方は実際に試してご覧になられたい。ただし本稿のMML譜は,ブラウザ上に表示するため,一部の記号を英数全角字に変えてあるので,そのままでは読み込まれないと思われる。
本当ならば,より一般的で理解しやすい数字譜か五線譜に変換したものを参照につけるべきなのだが,どちらもパソコンの上で作成・参照するのには労力も多大で,かつ時間がかかる。このあたりでご容赦願いたい。
工尺符字の音高の読み解きは各楽器によって微妙に異なるが,MML譜では「合」を最低音とし 「合 四 乙 上 尺 工 凡 六 五 仩 伬 仜…」 を音階の順列とし,合=3G,上=4C(ピアノの真ん中のド)として変換している。すなわちMML譜において「合」は <g>,「仩」(近世譜では「C」)は >c< で表示される。
本稿のMIDI再現曲は,そうして組まれた基本的なMML譜をもとに,それぞれの楽器の読み解きに従って適宜変換した物を組み合わせて作成されている。 たとえば,原譜で「合」であった音は,明笛のパートでは <g> だが月琴では g になる,明笛では「合」と「六」はオクターブの関係になるが,月琴ではどちらも g ,胡琴ではどちらも <g> となるといった具合である。(既述
《楽器ごとの読み解きについて》 参照)
《本稿の構成について》
1)曲題と各本画像
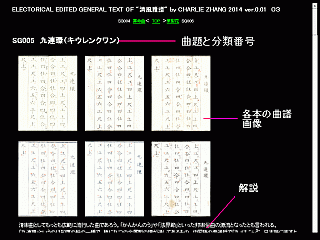
2)本文と近世譜・MML譜(基本的に白文字)
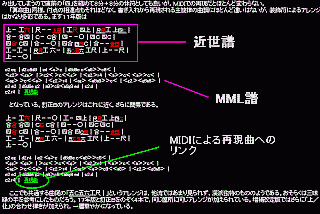
3)注記・参考の類(青文字)
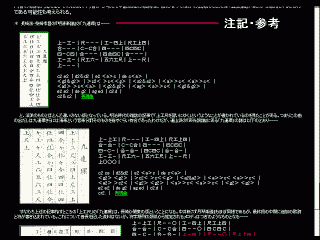
なお参考とした画像のうち,緑の枠線で囲まれているものは,手持ちの資料ではなく,国会図書館デジタルアーカイブの資料からの引用である。また楽譜全体を見やすくするため,だいたいの画像はトリミングや切り貼りなどの処理をしてあり,原譜のままではないことをお断りしておく。
*1 近世譜あるいは数字譜の資料では同じ曲譜が2/4でも4/4でも再現されていることがある。そもそもこの拍点は,稽古の時などに両膝を交互にたたく形式で拍子をとった場合の,右をオモテ拍点(符字の右がわに付される),左がウラ拍点(同じく左がわに)としたところからきているようだが,これを等しく1つの拍子とした場合には2/4,本稿のようにオモテ・ウラの2拍点を4/4の一小節と考えた場合には4/4となるわけであり,とくにテンポの緩急を意味するものではない。
*1 溪派などの付点形式では基本的に,西洋音楽の全符から8分音符の細かさまでしか表現し指示することが出来ない。よって,より複雑なメロディを表現する時には,拍子を2倍から4倍の長さに引き伸ばした形式で付点がなされていることがある。このため付点のなされた曲をすべて同じ拍子やテンポで再現すると,その緩急が不自然なものとなることがある。
*2 清楽に用いられた明笛などから,実際の清楽音階は合=Bb,上=E
bほどで,西洋音階と比した場合,上=ドとした時のミにあたる第3音が10〜20%ほど低く,三味線のみやこ音階に近い音階で演奏されていたようである。
*2 上=ドとしたときの「シ」に当る「乙」は,中国の工尺譜では「合 四」に続く低音域が「一」,「六 五」に続く高音域が「乙」で表わされるが,日本の工尺譜ではこの書分けがほとんど用いられず,特に指示のない場合は,使用する楽器の能力,曲調の流れと前後の関係などより演奏者が適当に高低を判断していたようである。
*2 「合四」と「六五」は「同音」と書かれることも多い。現実にはオクターブの関係にあり「同じ音」ではないのだが,これは清楽の主要楽器であった月琴の最低音が「上」で,それより低い「合 四 乙」を1オクターブ上の「六 五 乙」で弾くことに由来する。日本の伝統音楽は,基本的には絶対音に基づかない「移動ド」を基礎とするものであったため,オクターブというような高低の概念が薄い。最低音が「合」の明笛は「合四」「六五」を分けて吹き,逆に「合四」に続く,あるいははさまれた「六」以上の高音(たとえば「仩」)は1オクターブ低い音で演奏されたはずである。
*3 いちおう「合」より低い音は最後の一画を下方向に撥ねて表現するという方法もあるが一般的な曲譜においては見たことがない。
*3 さらに高音を表わすときには「彳」が用いられる。
《更新履歴》
2014年8月 ver.0.01 完成,同年10月より知人を中心に公開。
2015年6月 読み解き解説部分書き直し,構成入れ替えなど。ver.0.02
2017年7月 英数大文字表記だった近世譜の高音符字をニンベンつきの実字に変換。部分的に見直し,書き換え。ver.0.03