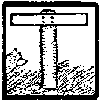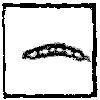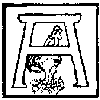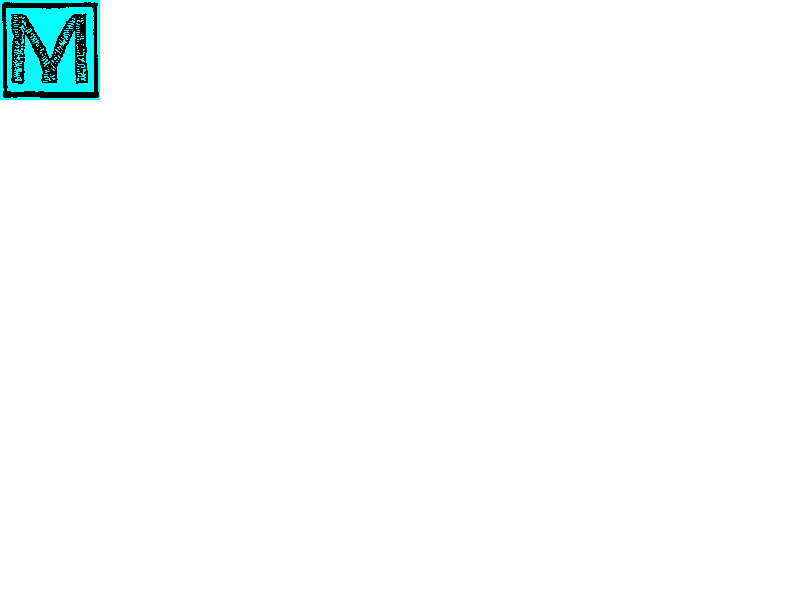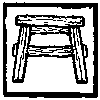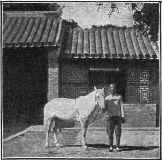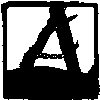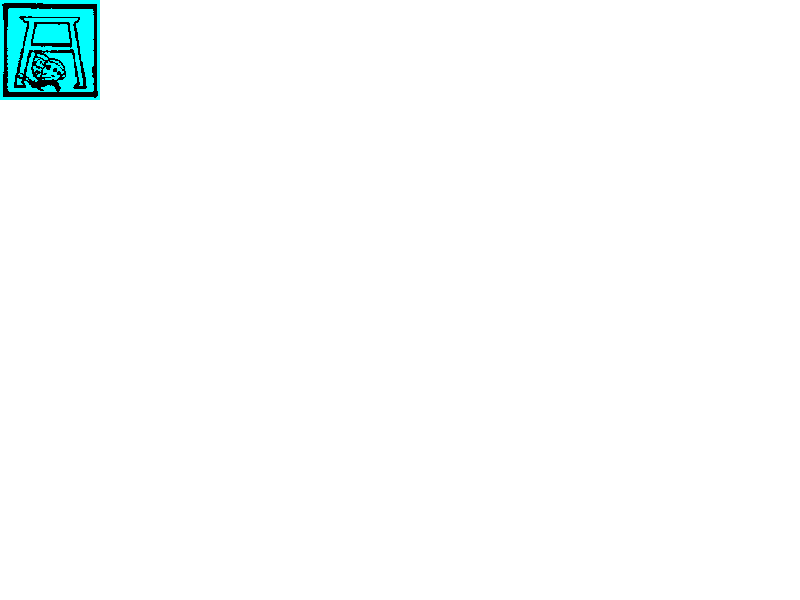〈VISITORS〉
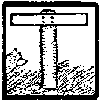 T T
|
he wolf has come,
The tiger has come,
The old priest follows,
Beating a drum.
|
オオカミきたよ トラもきた
和尚(おしょ)さんも太鼓 しょってきた
子守唄。唄の起源説については長くなるので別表参照。(
WOLF.TXT)
「和尚さん」に代わって(もしくはいっしょに),
本書014-021「楊樹葉兒嘩拉拉…」にも出てきた中国お化け,「マーフーツ」の類が出てくるものも多い。たとえば『中国廿省兒歌集』(遼寧 廿省2-32)の例では「狼來啦,虎來啦,
馬猴揹着鼓來啦。(…大ザル太鼓をしょってきた)」。また李家瑞の『北平俗曲略』(「嘣嘣戯」p.23)に引かれている古い人形芝居のひとくだりにも,登場人物が子どもをあやしながら「狼來咧,狗來咧,等娘與你
打馬虎。(…母ちゃんといっしょにお化けをぶとう)」と歌う場面が出てくる。
日本では「地震カミナリ火事オヤジ」と言うが,中国では「和尚さん」が「トラ」や「オオカミ」や「お化け」なみにコワいものと見ゆる。
北京の例についてはどんな曲調であったのか分からないが,満州族の「悠揺車」とか「揺車曲」と呼ばれる子守唄に,この「狼來咧」と同様のフレーズの入っているものがよく見られる。「揺車」というのは,天上から縄を張って吊るした,彼ら独特の揺りかごのことである。それをブランコのようにゆらしながら唱える子守唄が「揺車曲」だが,こちらの例では,あたまに「巴補哇…(ba--bu--wai--)」「悠悠扎…(you--you--zha--)」といった「ねんねんころり」流の,調子取りの文句のついているものが多い。
巴補哇,俄世啊,
悠悠小孩巴補哇,
狼來啦,虎來啦,
老和尚背着鼓來啦,
悠悠哇,悠悠哇,
馬猴子跳墻過來啦
小孩睡,蓋花被,
小孩哭來想他姑。
悠悠哇,悠悠哇,
小孩醒來吃月餅。
ぱあぷうわ をしあ
ゆうゆう ぼうや ぱあぷうわ
オオカミきたよ トラきたよ
和尚さん太鼓 しょってきたよ
ゆうゆうわ ゆうゆうわ
オバケもかきねを越してくる
ぼうやおやすみ おふとんかむり
泣いてはぼうや 母さん想い
ゆうゆうわ ゆうゆうわ
お目がさめたら お菓子を食べよ
|

| |
(遼寧 『中国兒童民歌選集』 p.97)
|
余談① 『中国の民謡と童謡』(柿崎 進 p.353)には,この唄に関するちょっと面白い記事が見える。他で確かめていないので,ちょっと怪しい点もあるのだが,興味深い伝承なのでとりあげておこう。
(この唄は)…"虎來了" と言つて子供の泣いた時に黙らせる手段に使ふが,伝説によれば "虎" は "忽" に通じ,即ち元の忽比烈の苛酷さに恐怖した漢民族が後代までこれを恐怖の代名詞に使つたものとされてゐる。現に欧州の東部に於ては "虎比烈" 來と云つて矢張り子供をだます方法に使って居るそうである。
余談② これと同類の「脅かし型」子守り唄に――
倭倭來,鼕鼕來,
阿拉囝囝睏熟來。
わあわがくるよ どんどんとくるよ
そうらぼうやの おねむもくるよ
| |
(『歌謡週刊』1-15)
という浙江省の唄がある。寄稿者の注によれば,この「倭倭」とは,明の時代,南無八幡大菩薩の帆柱たてて,中国沿岸から揚子江一帯を荒らしまわった,かの海賊集団「倭寇」のことだそうである。
――――――――――――――――――――――――

|
cf./もう一首,『中国風俗民歌大観』(朱傳迪 1992)にも「狼來啦,虎來啦…」のフレーズを含む,満州族の子守唄が採譜されている。「悠悠扎,巴卜扎,狼來啦,虎來啦。悠悠扎,巴卜扎,瑪虎跳過牆來啦。小阿哥,悠悠扎,你爹出兵發馬啦…」(黒龍江省)
|
ちュエイ パんツル
錐幫子兒
ナー ティツル
納底子兒
チョんら アルショん シィアオミーツァル
掙了二升小米子兒
チョんチョんらオらオ
蒸蒸烙烙
ちーターニャんタ イートゥン かオらオ
吃他娘的一頓犒勞
|
|
〈SHOE-MAKER〉
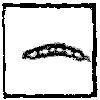 H H
|
E stitches the heel,
And he stitches the sole,
|
Two measures of millet
he gets for the whole;
They steam it,or fry it,
When hungry they feel,
And he eats with his mother
a very good meal.
くつぬのぬって くつぞこはって
粟ば二升も もーらって
蒸しむし 焼きやき
かあちゃん ごちそう おンあがり
低賃金労働の代名詞であった布靴造りの工人は,寡婦や老婆など社会的,生活的弱者の女性が多かったそうだ。ヘッドランドは "He" で訳しているが,これもたぶん女の子の唄だと思われる。というのも『歌謡週刊』1-47に――
小媳婦,坐椅子兒,
錐幫子,抐底子兒,
掙了二升小米子兒,
推推軋軋,
夠咱小倆口吃頓犒勞。(北京)
|
ちいさな嬢ちゃん すわるはこしかけ
くつぬのあわせ そこをさせ
粟の二升を かせぎだせ
ひきひき すーりすり
ちびさんふたり ちょっとくわせ
|
と,すでに出た
083-093同様に,ちゃんと「女の子」の出てくる版があるからだ。句の増減はあるが,ともに同じ系列に属する歌謡である。
――――――――――――――――――――――――
とんらイかン とんらイかン
同來看 同來看
へイチィ シアらコ パイ チィ タン
黒鷄下了個白鷄蛋
とんらイちィアオ とんらイちィアオ
同來瞧 同來瞧
はオツ ちャんら イーシェン マオ
耗子長了一身毛
〈TWO WONDERS〉
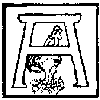 A A
|
ll come and see!
All come and see!
|
A black he laid a white egg for me!
Oh,look there!
Oh,look there!
A great,big rat all covered with hair.
|

|
見にこい 見にこい
黒いニワトリ タマゴが白い
見たかい 見られた
ネズミのからだ 毛だらけだ
『北京民間兒歌選』(王文宝 p.78)にこの唄を引いて,「這是叫別人看事物時唱的歌謡」とある。また同書 p.95 には
出來瞧,出來看,
出來晩了看不見。
|
でてみな きてみな
よるならみーれんぞ
|
というのがあって,こちらのほうには「這是小孩兒在院子裏叫別的孩子看什麽東西時唱的」と書いてある。どちらの注も,訳すと「ほかの子が何かを見ているときに唱える唄」といった程度の内容だが,要するに「
あッ!あれを見ろ!」「なんじゃいな?」「
バカは見るう~」とか,「
○○ちゃん?」「なぁに?」「
ナニはナットウ,おコメにゃコウジ」といった手合いのムダ口,ヘラズ口のはやし唄に近いものだと思う。
つまり「同來看!(見ろよ!)」と叫んで人が振り向いたら「黒いニワトリが…」と続けるわけだ。
…いちおう,念をおしておきますが,親のニワトリがどんな色でも,玉子は白か茶色だし。ネズミはもとから毛だらけですからね。
――――――――――――――――――――――――
|
チょんユエりィ
正月裏
チょんユエチぉん
正月正
てィエンチィアんへイら ティエンシャんトぉん
天將黒了點上燈
アルユエパン
二月半
レンルゥウォーら チィウちーファン
人若餓了就吃飯
サンユエちャん
三月長
レンヤオカイファン チィウれイちィアん
人要盖房就壘墻
|
〈DO AS YOU OUGHT〉
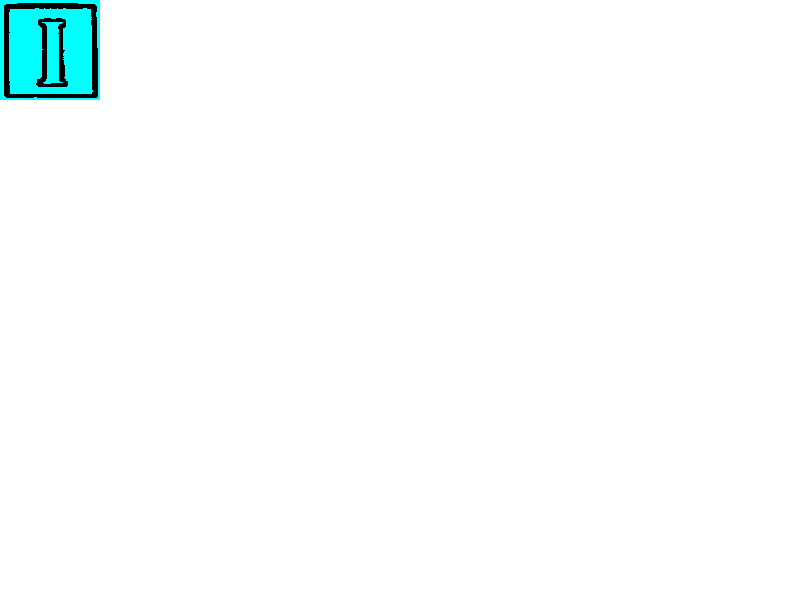 I I
|
N the first month,
when it is night,
|
If you are wise,
your lamp you'll light;
And when the second
month you meet,
If you are hungry
you should eat;
And in the third month
most of all
To build a house
you must lay a wall. |
お正月 正月ぴたり
暗くなったら 提灯ぴかり
二月ははんぱ
おなかすいたら 食べようご飯
三月にゃがい
家を建てるにゃ 壁積まにゃあ
|
各月の歳時や行事を綴った同様の形式の唄は数多くあるが,この唄に関しては,その内容において,ほかに類似の採集例がなく,ちゃんとした暦唄なのか,それをモトにしてつくられたはやし唄なのか分からない。その文句もどうやら,内容よりも「正-燈」「半-飯」「長-墻」という押韻のほうに重きがおかれているようで,「正月」以外「二月半」「三月長」ともに何の日を指すものか判然としないところがある。随意調査中。
――――――――――――――――――――――――
ワイシぉんシらオらオ
外甥是老老
チィアータコウ
家的狗
ちーファンら
吃飯了
たーチィウツォウ
他就走
〈MY NEPHEW〉
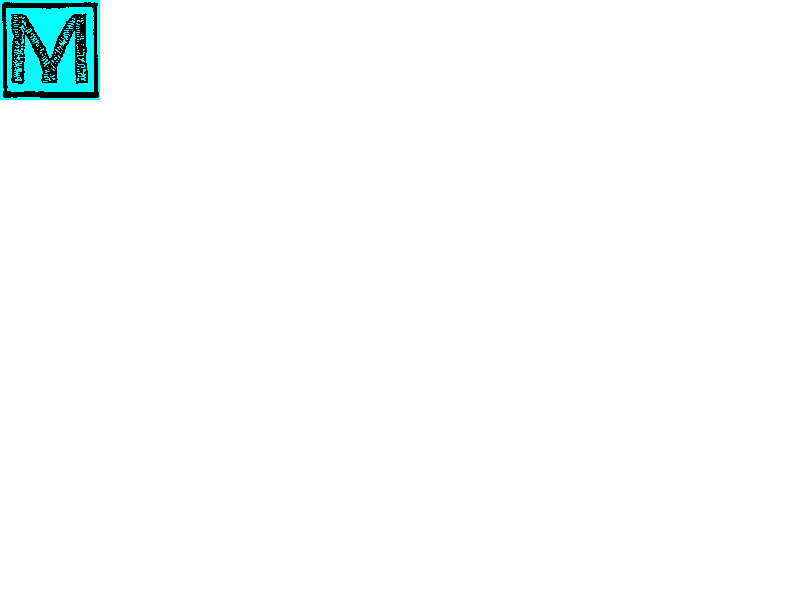 M M
|
Y nephew is a naughty boy,
He comes here every day
|
He eats until he's very full,
And then he runs away. |
|
あいつ甥っ子
婆ちゃん家のワンコ
メシを食べたら
いづこか散歩
「外甥(wai
4sheng
1)」は自分から見て姉妹の息子。他家へ嫁いで行った女兄弟の子どもだから,本家筋から見るとより他人観が強いらしく,時として「厄介者」的なからかい語,罵語として用いられる。
「わらべ唄」というよりは「諺」として採録しているものが多いが,『井陘縣志料』(河北 民国23年)では,
外甥子是狗。
外甥子是狗。
吃了老娘家的飯就要走。
|
おいっこ ワンコ
おいっこ イヌっこ
婆ちゃんちでタダ飯 食べたらさらば
|
という例を載せて,これを「家庭問題に関する歌」の一つに数えているから,何らかの節回しをもって唱えられていた,ウタとコトワザの中間のようなものだったのかもしれない。
古い例では『廣天籟集』(1869)の第十七首(GT-017:搖搖搖,搖到外婆橋…)の「評語」に「諺にいわく」として「外孫狗,吃得向外走。(娘孫っ子 食ったら出てく)」というのが見える。
また『新河縣志』(河北 民国19年)「外甥是狗,吃了就走。」,『義縣志』(遼寧 民国20年)に「外甥是老家的狗,吃了就走。」,『萬全縣志』(河北 民国23年)にも「外甥狗,吃了飯兒往家走。」といった類例が見られる。
――――――――――――――――――――――――
|
|
ほアチィアオシュ ウぉんウぉんウぉん
花椒樹 嗡嗡嗡
ちャん コ ちャル
唱個唱兒
ナイナイ ティん
奶奶聽
〈RED PEPPER FLOWER〉
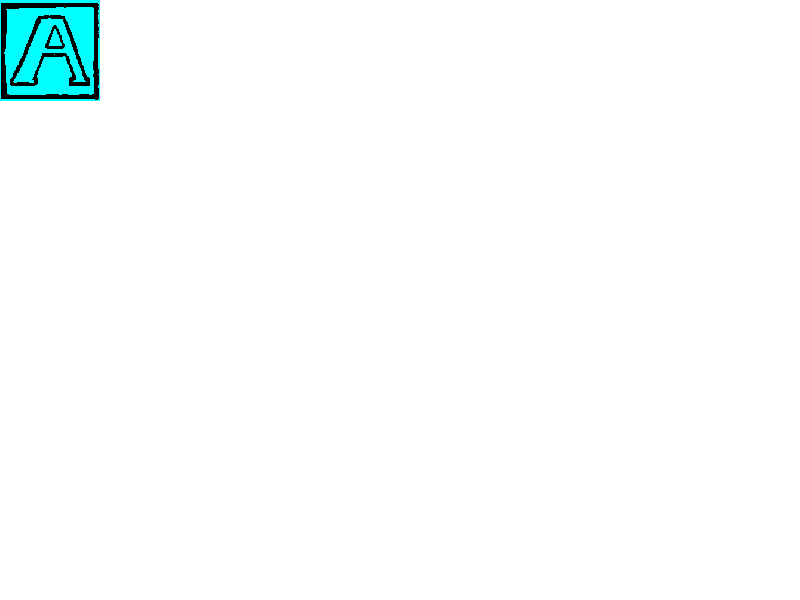 A A
|
red pepper flower,
Ling, ling, ling,
|
Mama will listen
And baby
will sing |
さんしょの木ヨ ほぉらほら
ぼうやは 唄って
婆ちゃんが 聞いたげる
あやし唄。『歌謡週刊』1-23にも
花椒樹,水零零,
你唱個唱兒
給我聽。(北京)
|
さんしょの木よ ひぃやひや
あなたのお歌
聞かせてよ
|
という類唄が採録されている。「花椒樹(hua
1jiao
1shu
4)」はサンショウの樹(
Xanthoxyum piperitum DC.)。「花椒樹,棘針多…(~トゲ多い)」とか「花椒樹,紅孤朶(~枝赤い)」というように,民謡の起句の題材としてよく使われる。
肉食の習慣が薄かったためだろうが,日本では「香辛料」と呼ばれる香味の分野がとても狭く,「伝統的」などといえるものはほとんどない。そのなかでサンショウは,ほとんど唯一,香辛料として古くから使われていたものである。英訳にある‘red pepper’はトウガラシのことだが,トウガラシのからさが「辣」(la
4…刺すようなからさ)と表現されるのに対して,サンショウのからさは「辛」(xin
1…シビレるようなからさ)と表現される。日本語でからいのを「辛い」と字を当てるのも,サンショウがその「からさ」の代表だったからだろうか?
さすがにこの起句には,それほど隠喩が隠されてるとは思わないが,辛いものを食べると,口の中が熱くなって,はあはあと息をしながら口を開けて冷まそうとする。そんなふうに大きくお口をあけて,唄を歌って――というような連想はあったかもしれない。
――――――――――――――――――――――――
|
シャんシャンタ るオツ
上山的騾子
シィアシャンタ マー
下山的馬
ピんティータ マオるゥ
平地的毛驢
プー ヨん ター
不用打
〈DON'T BE CRUEL〉
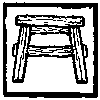 A A
|
mule going
up hill,
A donkey on
the street,
|
Or a horse coming down hill
You
never
ought
to beat. |
|

|
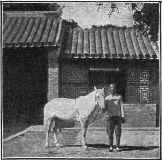
| |
|
のぼりのラバに
くだりのおウマ
平地のロバにゃ
ムチ用なし
|
ご存じとは思うが「ラバ」はロバとウマの混血雑種である。英語では母ウマ,父ロバを‘hinny’と呼び,母ロバ父ウマの雑種を‘mule’と呼ぶ。
「英訳は動物愛護の唄みたに訳しているが,それぞれの行路にもっとも適した家畜をうたった諺唄であろう。」というのが前版(1999)の解説。その後『東北農諺滙釋』(長白叢書10 林中凡 1992)という資料に
下坡的騾子。
上坡的馬。
平地的驢馬子不用打。(同書 p.228)
という類例を発見。解説によれば
「ラバは下り道で速く,ウマは上りに強い,そしてロバは平地では速いので,そういった場所では,どれもたびたびムチを入れる必要がない。」 とのこと。ラバとウマの用途が本例とは逆だが,これは産地によって脚質が異なるためだろうか?
どちらも共通なのはロバだが,「平地はロバではなくウマだろう」という方もおられましょう。――が,たしかに平地でのウマは速いのですが,この動物はけっこう繊細で,世話にもずいぶん手がかかる。それに比べるとロバはメンテナンスフリーで,力も強く,文句を言わない。
中国ではこの脚質の違いを利用して,牛と馬,馬とラバといった組み合わせで荷車を挽かせたりする,異種多頭挽きがふつうに行われている。そのためか,これらをいっしょにした諺がけっこうある。
たとえば「打了騾子馬也驚(ラバを打つとウマまで驚く)」これは「彼岸の火事がこちらまで」といった意味。「驢朝東,馬朝西(ロバは東に,ウマは西)」というのは,いっしょに繋いだウマとロバが,それぞれあっちゃの方向へ向かうので馬車が動かん,という反目立往生の態を表し,「肥了騾子痩了馬(ラバは肥えたがウマ痩せた)」あちらを立てればこちらが立たず,ということだそうな(参考:中野江漢『支那の馬』大正13年)。
本例に似て,家畜の用途の違いを唱えたものには以下のようなものもある
牛耕地,
騾駕轅,
馬碾場,
驢子套在磨盤上。
(『東北農諺滙釋』 p.222)
|
牛は畑に
ラバは荷に
馬はカラ剥き
ロバをくくるは粉挽き臼よ
|
「碾」は脱穀用のひき臼。「碾場」で「脱穀する」という意味。「磨盤」は製粉用のひき臼のこと。
――――――――――――――――――――――――
シィアオシィアオほアぺン るゥインイン
小小花盆緑陰陰
リーとウツァイタ ワンニィエンちィん
裏頭栽的萬年青
ニャんニャんファんりー シぉんクイツ
娘娘房裏生貴子
ティエティエツァイワイ ファーワんチィン
[爹爹]在外發萬金
イェイエ たイたイらオシュウシィん
[爺爺]太太老壽星
|
|
|
小さな花鉢 こいみどり
うわるオモトは なおあおい
おくさま産むよ
良い子をひとり
だんなのお仕事
黄金(こがね)とみのり
爺さま婆さま 長寿で元気
|
〈FLOWER POT〉
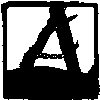 A A
|
wee little flower-pot,
very deep green,
With just the
sweetest flowers that
|
ever were seen;
Mother with her babies playing very funny,
Father doing business, making lots of money,
Grandpa very old, but never going to die,
Grandma just as bright as a star in the sky. |
|
原書では後半二句の「爺爺(おじいさん)」と「爹爹(お父さん)」の文字が入れ違っているので,類例から推察して修正しておいた。
「萬年青(wan
4niang
2qing
1)」は「おもと」(
Rohdea japonica Roth)。ユリ科の観葉植物。通年,濃い緑色で枯れないところから,長寿,もしくは「家運長久」のおめでたい植物とされる。
「老壽星(lao
3shou
4xing
1)」は,日本の七福神の「福録寿」のもとになった「南極老人星」のこと,人間の幸福と長寿を司る神様。
安徽省の例だが,『歌謡週刊』2-8 にも,こんな類唄が見える。
吉祥草,萬年青,
爺爺婆婆老壽星,
媽媽在家生弟弟,
爸爸在外發萬金。
|
きちじょうそうに おもと
爺さま婆さま 長生きそうとう
母さんおうちで 産んだは弟(おとと)
父さん大金 かせぐよおそと
|
「吉祥草」(
Reineckia carnca Kunth.)もまたユリ科の植物で,緑の葉と,紅紫色の実が年を越しても残るところから「子孫長久」をあらわすめでたい植物とされている。
これらのように植物は出てこないが,ヴィターレの収集にあるこの唄も,同じたぐいのものだろう,
壽星老兒福禄星,
増福増壽壽長生,
生文生武生貴子,
子孝孫賢輩輩兒榮。
(V169-218)
|
寿星老に福禄星
増福増壽 長生きせい
やくにん さむらい えらい人
孝行息子に かしこい孫に
生まれる子はみな 大繁栄
|
これには「生日(誕生日)に子どもたちによって唱えられるまじない唄」だと解説がついている。じっさいは誕生日だけでなく紅事(おめでたい行事)や,お正月などに,家人や門付けの芸人などによって唱えられた,ことほぎの唄の一種である。
――――――――――――――――――――――――
cf./『民間文学』(1981.6 p.37「鎮江伝統兒歌」)には,これらの唄を起句として用いたこんな民謡が載っている。「吉祥草,萬年青,爹爹奶奶老壽星,我是爸爸龍宝貝,我是媽媽命心肝,我是哥哥親妹妹,嫂嫂説我太討嫌,我能在家過幾年?」
|
チィン クーる パん イン クーる パん
金軲轆棒 銀軲轆棒
イェ イェル ター パル
爺爺兒打板兒
ナイ ナル ちャん
奶奶兒唱
イーちャんちャんタオ ターてィエンりィアん
一唱唱到大天亮
ヤん ほウらコ はイツ メイ ちゥル ファん
養活[了]個孩子沒處兒放
イーファんファんツァイ コウたイシャん
一放放在鍋臺上
ツゥール ツゥル タ ほォ ミィたん
嗞兒嗞兒的喝米湯
|
|
|
チンクルパン
インクルパン
拍子木打つはお爺ちゃん
あわせて唄うはお婆ちゃん
唄いはじめりゃ
朝までとまらん
赤ちゃんそだてる場所あらん
そんでカマドの上しかなからん
そこでチュルチュル
おもゆさん
|
〈A NEW BABY〉
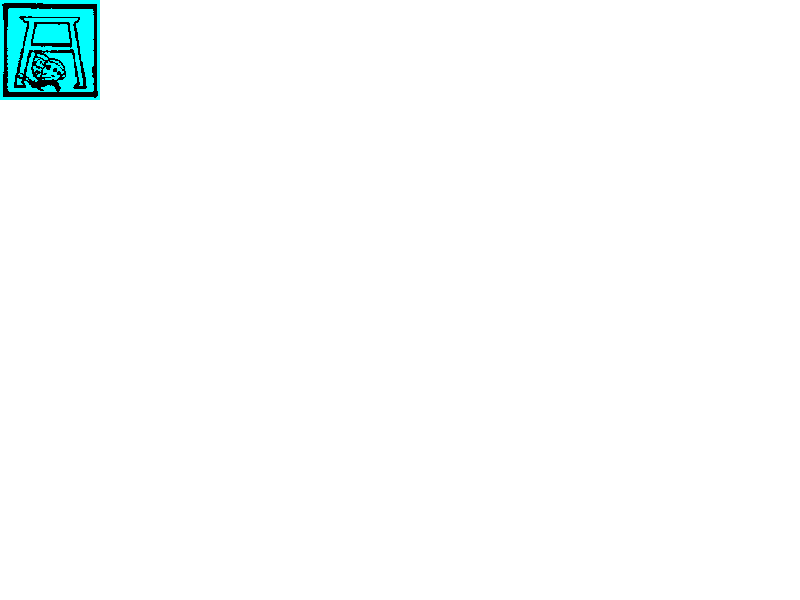 A A
|
glit-wood mace,
And silvered things,
|
My grandfather plays,
And grandmother sings;
My grandmother sings till broad daylight,
And baby comes to our home at night;
They place the child by the pot on the
ground,
And it eats rice soup with a sucking
sound. |
中国語歌詞の六行目の「了」の字が抜けているのは,先行するヴィターレの本から転載したさいの誤写か,原書のレイアウト上の削除だと思われるため,これを補っておく。
李家瑞『北平俗曲集』(p.179 「兒歌」)に清代の唱本からとして,
金咕嚕棒,燒熱炕,
奶奶彈絃子爺爺唱,
一唱唱了個大天亮,
養了個孩子沒地方放,
一放放在鍋臺上,
咂咂咂喝米湯。
|
チンクルパン たきぎにしょ
ばあちゃん三味ひき じいちゃん歌い
歌いだしたら 夜明けまで
うまれたぼうやは なんとしよ
ヘッツイ(竈)のうえでも ほかしましょ
ちゅうちゅうちゅう おもゆさん
|
という古例が引かれている。ヴィターレは末句の「嗞兒嗞兒(ci
1r ci
1r)」という表現について「汁をすする音の擬声語。これにあたる字が辞書に見当たらないので,口へんの字の中からいちばん音の近そうな字を選んであてた。」(V020-034)と注しているが,こちらの末句「咂(za
1)」には,ちゃんと「吸う,すする」の意味がある。
また,これと同じく,一句目を「燒熱炕」とする版もよく見られるもので,比較的近年にも
金軲轆棒,燒熱炕,
爺爺打板奶奶 唱
一唱唱到大天亮,
養了孫子沒地方放,
一放放在鍋臺上,
嘖兒咂,喝米湯,
別喝唻,別喝唻,
留着給你阿瑪漿衣裳唄。
|
チンクルパン たきつけよ
じいちゃん拍子木 ばあちゃん歌手よ
歌いだしたら 夜明けまで
孫ができても ない居場所
へっついにィでも ほかしましょ
ずぅるちゅと おもゆやりゃ
のむない のむない
とおちゃんのおべべの糊にしよ
|
(『民間文学』1982.7 張嘉鼎「満族童謡」)
|
という報告例がある。
ヴィターレは起句の「軲轆棒」を「むかしの武器,棍棒のたぐいを模した玩具」と解説しているが,この「満族童謡」の注には
「金軲轆棒」は根のついた木の株でつくった棒槌で,大昔の狩猟用の投擲具に由来し,「得薹(dei1tai3…日本の「根ッ木」に近い遊び)」という子どもの遊びに使われるのだが,危険なので大人はこれを見つけると,とりあげて燃やしてしまう。ゆえに「燒熱炕(オンドルで燃やす)」と歌われるのだ。
という説が見える。
――――――――――――――――――――――――
cf./その他のヴァリエーション
『北平歌謡集』(平111-059)「金箍棒,燒熱炕,爺爺打板奶奶唱…養活孩子沒地方放…吱咂喝米湯。」
『北京的歌謡』(薛汕 1957)「金箍棒,銀箍棒,爺爺打鼓奶奶唱…養活孩子沒地方放…滋兒滋兒喝米湯。小子小子少喝点兒,留点給你爸爸漿布衫兒。」
『北京民間兒歌選』p.135「金箍棒,銀箍棒,爺爺打鼓奶奶唱…養活孩子沒地方放…吱兒吱兒喝米湯。」
『歌謡週刊』(河南 1-17)「芝麻杆,燒熱炕,爺爺打炕奶奶唱…奶奶唱的…爺爺唱的…」

|
イーちャんちィウフぉん
一場秋風
イーちャんりャん
一場涼
イーちャんパイるウ
一場白露
イーちャんシュアん
一場霜
イェンシュアんタンター
嚴霜單打
トゥケンつァオ
獨根草
マーチャースゥツァイ
螞蚱死在
つァオケンシャん
草根上
|
〈THE DEAD CICADA〉
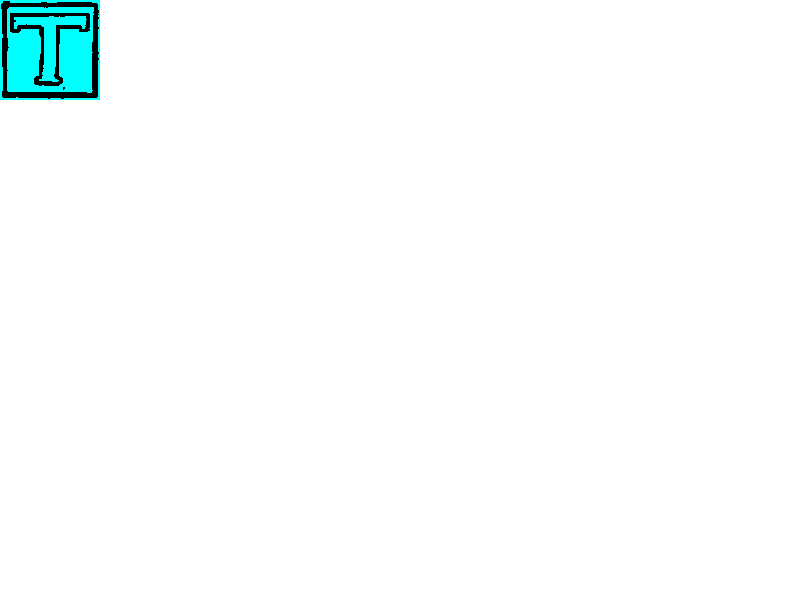 T T
|
HE rain has come
And has overflowed,
|
The drew and the frost
Are on the road.
The last of the grass
Has drooped its head
The cicada is on it,
Frozen dead.
秋風吹いて さむくなり
露も降りては 霜へとかわり
霜の鞭打つ 枯れ残し
イナゴの死ぬる 草枕
|
「螞蚱(ma
4zha
4)」はバッタ類,とくにイナゴを指す。日本では雪が降っても,その下に枯れ草くらいは残っているものだが,中国北方の冬は厳しく,吹きすさぶ風に地表の枯草すら飛ばされ,見渡す限り黄色い土ばかりの荒野と帰し,わずかに残るは草の「根の部分だけ(獨根草)」という状態になるのだそうだ。
『歌謡週刊』1-43「彈北京的歌謡(続)」で常恵は,これを民謡として採録したのはヘッドランドの「大間違い」で,これは唱本「王二姐」「摔鏡架」中にある一俗曲の一節なのだとしている。
蓮花落來蓮花落,
小臘梅桂花單枝
…(唱一回)…
八月秋風陣陣涼,
一場白露一層霜,
嚴霜單打獨根草,
掛大扁甩子落在喬麥梗兒上…
|
蓮花落だよ蓮花落
ロウバイ モクセイ一枝に
――
八月秋風しだいに寒く
露も凍るし霜も降る
霜は鞭打つ草の根を
バッタ横たう枯れソバに
|
(李家瑞 『北平俗曲略』「王二姐」 p.147)
|
「掛大扁(gua
4dabian
3)」は,日本で言うところのコメツキバッタ(舂米郎:chong
1mi
3lang
2)の類。「掛得扁兒(gua
4debia
3r)」とも書く。この「蓮花落」という俗曲は,かつて北方で盛んに唱えられたもので,山東省に起源する歌曲だそうである。
しかしながら。柿崎進の『中国の民謡と童謡』(昭和17年 p.214)に――
一陣秋風一陣涼
一場白露一場霜
嚴霜單打獨根草
窮人凍死在路傍
|
秋風立つて身に泌む頃
しつとり露は下り霜は白くなる
霜は草木の根を枯らし
路傍の乞食達を凍え死なす
|
と,そのパロディが採集されていることからも推測されるように,この唄が「民謡」として口承で歌われていたことはまず間違いないので,少なくともヘッドランドの例は,芝居の一節を「間違って」「民謡として」採集したようなものではないと,わたしは考える。
また『通縣志要』(北京 民国30年)を見ると「一場秋雨一場寒,十場秋雨要穿棉。(秋雨一降り寒さもひとしお 秋雨十度め綿入れ着よう)」,『昌樂縣續志』(山東省 民国23年)にも「一場春雨一場暖,一場秋雨一場寒。(春雨一降りしだいにぬるみ 秋雨一降りしだいにさむい)」という,これに似た口調の「諺」が見える。
『古謡諺』によれば『田家五行志』にも「一場春風對一場秋雨。」という句があるそうだ。
これらの諺と本書の唄を関連付けた記事は今のところないが,わたしにはむしろ,この唄はこうした諺から発展したもので,例の俗曲中のくだりなども,逆にそうした民間の歌謡が,芸能のほうに「取り込まれた」ものである可能性のほうが高いとも思われるのだが。
――――――――――――――――――――――――
cf./『歌謡週刊』1-34 周作人「兒歌之研究」に「一陣秋風一陣涼,一場白露一場霜,嚴霜單打獨根草,螞蚱死在草根上。」という例が引かれ,のち『北平歌謡集』(平006-005)などにも転載されている。しかし,この周作人の記事に答える形で常恵が上記の論文を書いているのだが,その文脈からすると,これはもともと本書の唄を転載したものであった可能性がある。そうすると冒頭の部分の「一場」が「一陣」になっているのは周作人の記憶違いであろうから,ヴァリエーションではないかもしれない。
『中国廿省兒歌集』(山東 廿省2-34)「一場秋風一場涼,一場白露一場霜,嚴霜單打獨草,蚱蜢死在枯草場。」