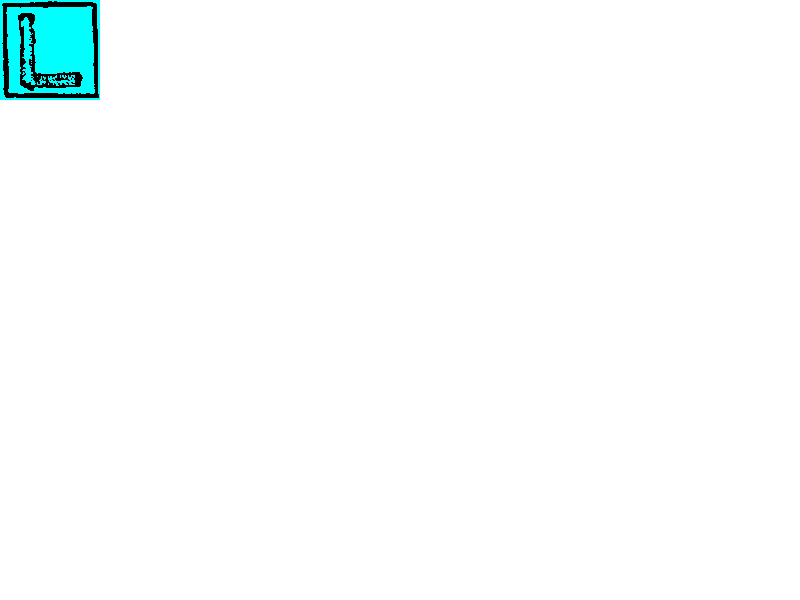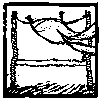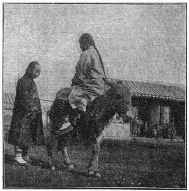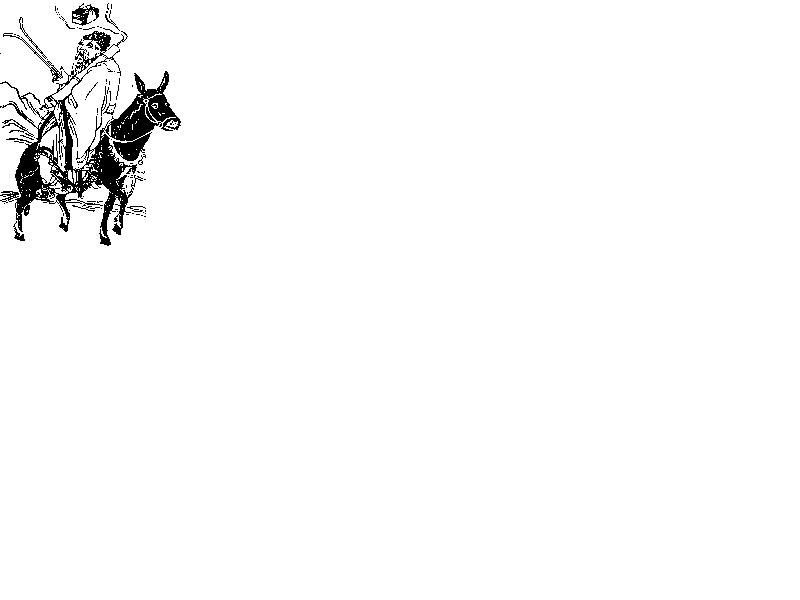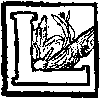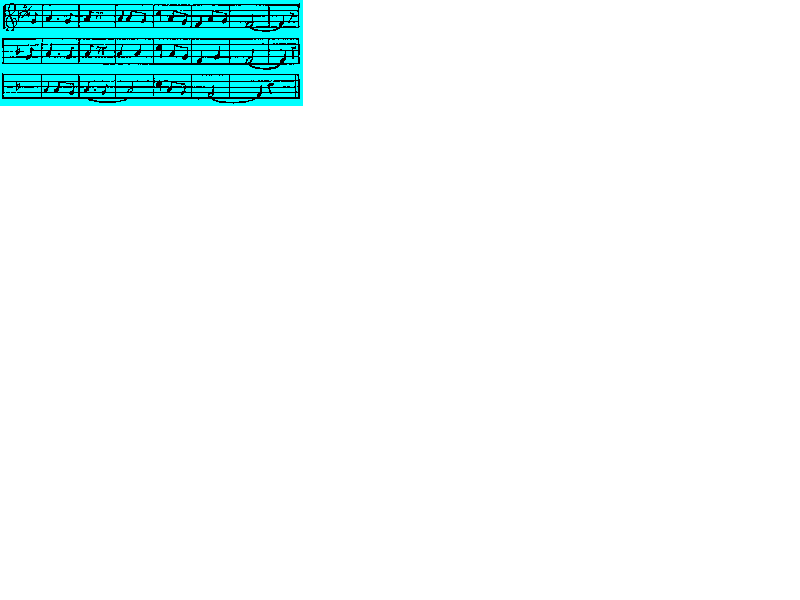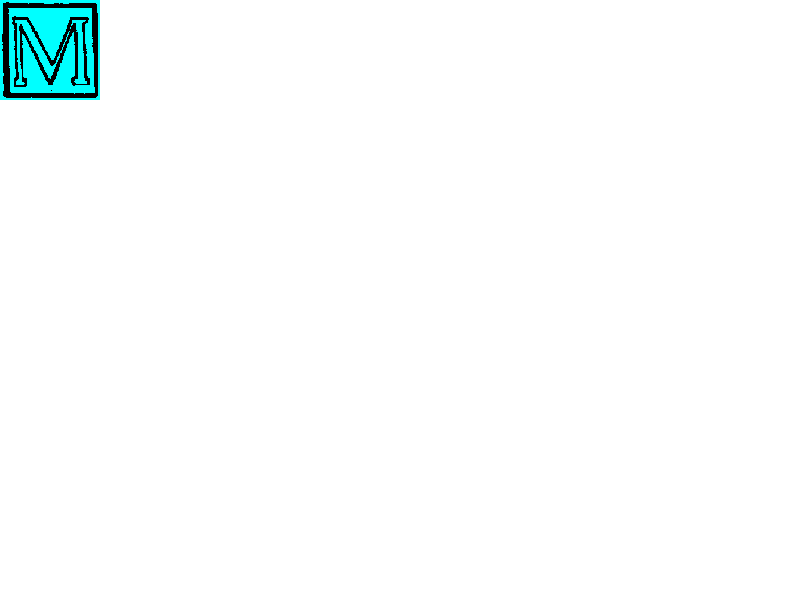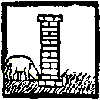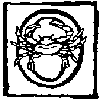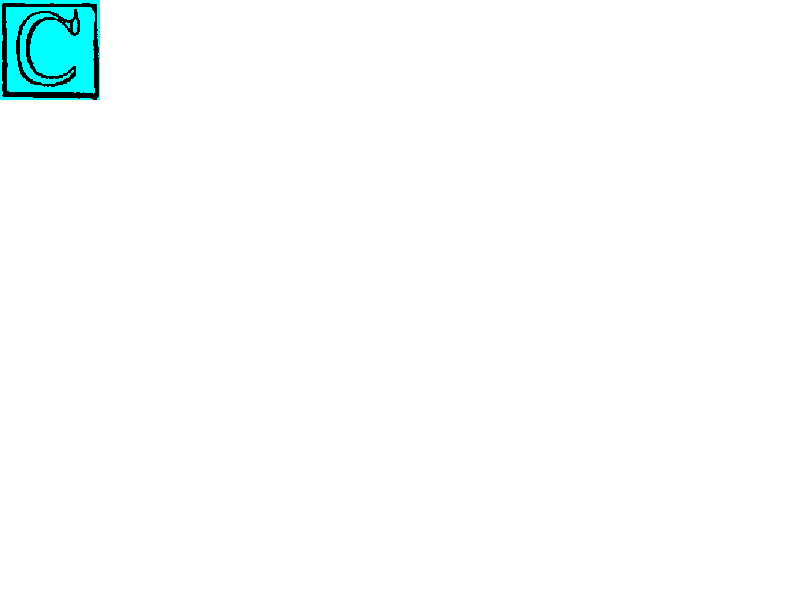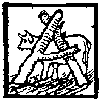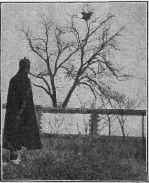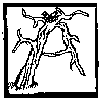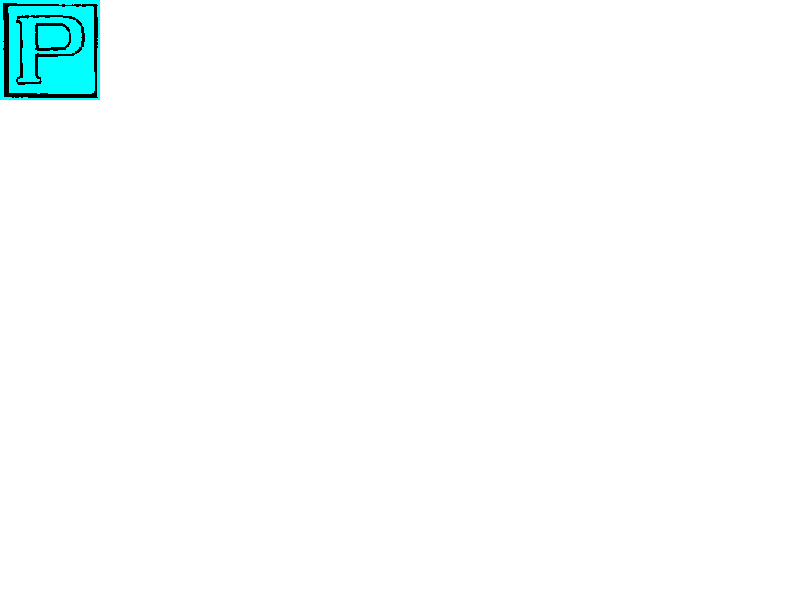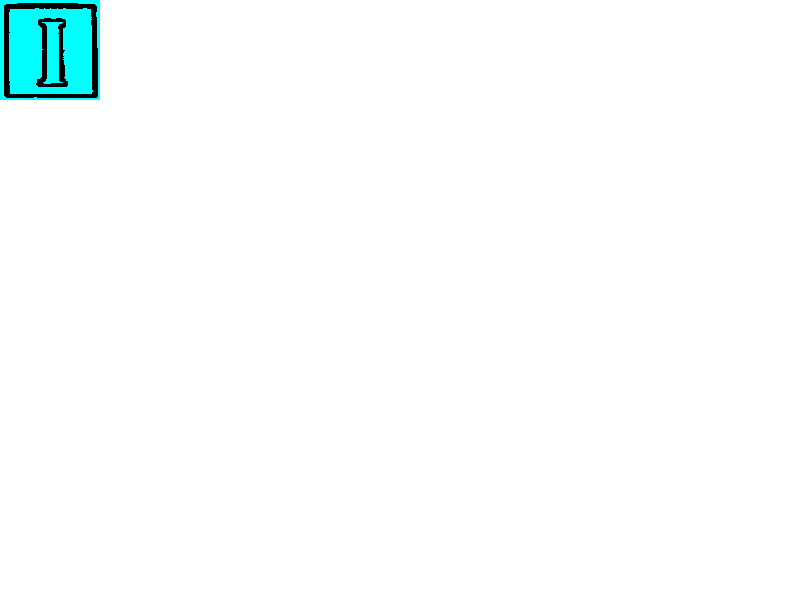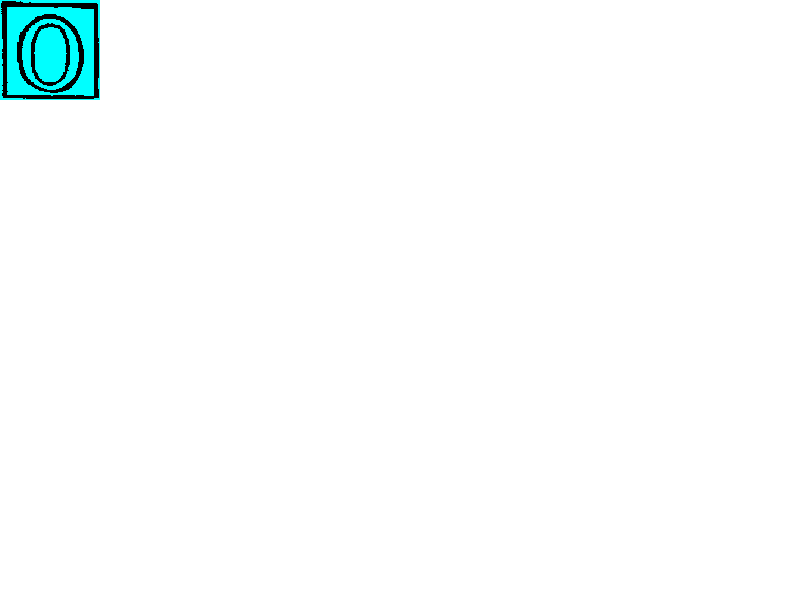|
とゥツ とゥ シャん ナオクー
禿子禿 上腦箍
くーちュー ヨウらイ チィエントウフー
箍出油來煎豆腐
トウフーほゥアん チィエンイェンワん
豆腐黄 見閻王
イェンワん タイチョ てィエマオツ
閻王戴着鐡帽子
シィアータ とゥツ ファー ノゥエツ
嚇的禿子發瘧子
〈GO TO BED〉
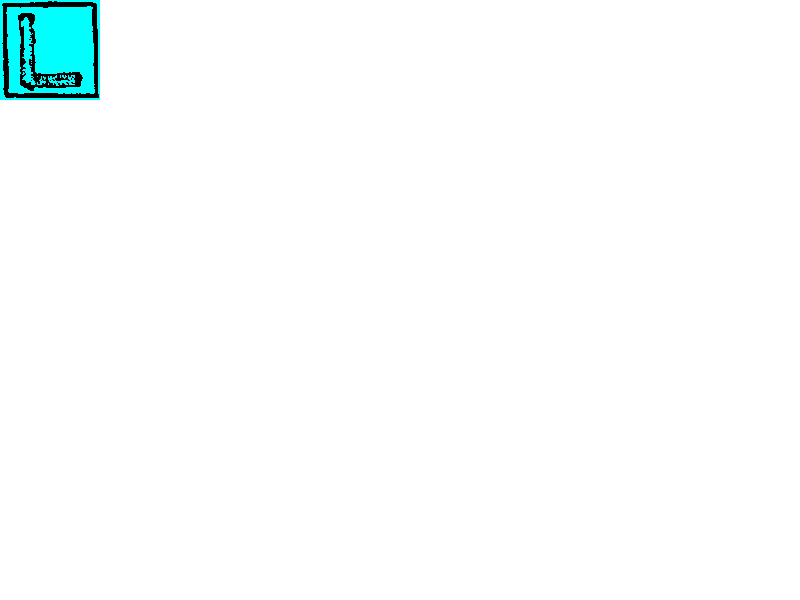 L L
|
ITTLE baby, go to bed,
We'll put a hoop
around your head,
|
And with the oil we get thereby,
Our little bean-cake we will fry.
And when we've fried our bean-cake brown,
We'll see the king go into town,
An iron cap upon his head;
Now-you-must-surely-go-to-bed. |

|
つるりん頭に たがはめて
あぶらしぼって おトウフ揚げて
キツネになったら お閻魔さまへ
閻魔大王 鉄帽子
つるりんびっくり 床(とこ)につき
英訳のタイトルから察すると,ヘッドランドはこれを子守唄(眠らせ唄)として訳したいらしい。そういう用いられ方をしたかもしれないが『各省童謡集』(各001-001)に見える類例の注に「這是嘲禿子的意思」とある通り,本来はからかい唄である。同書の語釈に従うなら「上腦箍」というのは「頭にたがをはめ」たみたいに頭頂部の禿げあがった様の形容という。または,そういう髪型をした子をからかう唄だろう。宣教師ヘッドランド先生は著書の中で,当時のわらべ唄に,こうした嘲り・侮蔑の唄が実に多いことを嘆いているが,量的に,その手のものをすべて排除するわけにはいかなかったものと見ゆる。英訳はおそらく,そういうわけで原意を余り入れずに起こしたものならん。
「頭にたがをはめて」しめつけるというと,孫悟空のが有名だが,実際,昔の拷問には,真赤に焼いた鉄の輪っかで頭を締め付けるというのがあったそうだ。地獄の「閻王(閻魔大王)」へ連想がつながってゆくのはそうした記憶からかもしれない。ちなみに植物から油をしぼるときに用いるしめつけ板のことも「箍」という。その油で豆腐を「揚げる」と「油揚げ」になるわけだが,日本ではそれはお稲荷さんへのお供え物と決まっている――東京,小石川の「こんにゃく閻魔様」はこんにゃくが大好きなことで有名だが,油揚げが好きな閻魔様というのにはいまだお目にかかったことがない。
「発瘧子」の「瘧」は「おこり」と訓じる。急激な悪寒,発熱をともなうマラリア的な病気で,日本でも平安時代から『源氏物語』などのなかで,「神仏のタタリ」や物憑きの病として代表的なものとされている。
ヴィターレの収集はこれの,前半2行のみしかない版(V037-058)を採録している。また同じ出だしで――
禿子禿 上脳箍
箍出油來炸豆腐
你一碗 我一碗
饞的禿子白瞪眼。
(北京 『歌謡週刊』1-47)
|
はげさん おつむにタガはめ
油しぼって豆腐揚げ
あなた一杯 わし一杯
いやしんぼうして はげさん白目
|
というものなど,いくつかのタイプがある。「白瞪眼(ba
2ideng
4yan
3)」は,この場合「目を白黒させて」といった様子。「もーダメ…」といったような表現。
類例のなかにはこうした四句程度の歌詞を振り出しに
本書120-130同様の「禿頭数え唄」(大禿子得病,二禿子慌…)へとつながってゆく型も見られる。
――――――――――――――――――――――――
|
チョコレン シょんらイ シィんル チィ
這個人生來性兒急
ちィんちェン ツァオちィ ちウ カンチィ
清晨早起去趕集
つオ ちュアんら るゥ プーくゥ
錯穿了緑布褲
タオ ちィ チョ イーとウ るゥ
倒騎着一頭驢
〈THE NERVOUS MAN〉
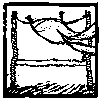 A A
|
NERVOUS disposition
He had when he was born,
|
To hurry to a fair one day,
He rose at early morn;
Put on his wife's green trousers
And started to sale,
A riding on a donkey--
His face turned toward its tail. |
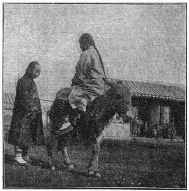
|
うまれついてのあわてんぼ
朝もはよからお買物
ズボンは緑の女物
ロバのさかさにのったとよ
からかい唄。「緑布褲(緑色のズボン)」というのは女物。男物は藍か黒色であった。また旧来,妓楼で働く男衆の服が緑だったことから「緑色の服を着た男(穿緑衣服的)」というのは「寝取られ男(コキュ)」を意味する罵言でもあった。フックス『風俗の歴史』を見ると「女房のズボンをはく男」と題する中世の木版画が載っていて,説明によれば「女房のシリにひかれた夫」の意味だという。これは西洋でも似たような比喩となるわけだ。
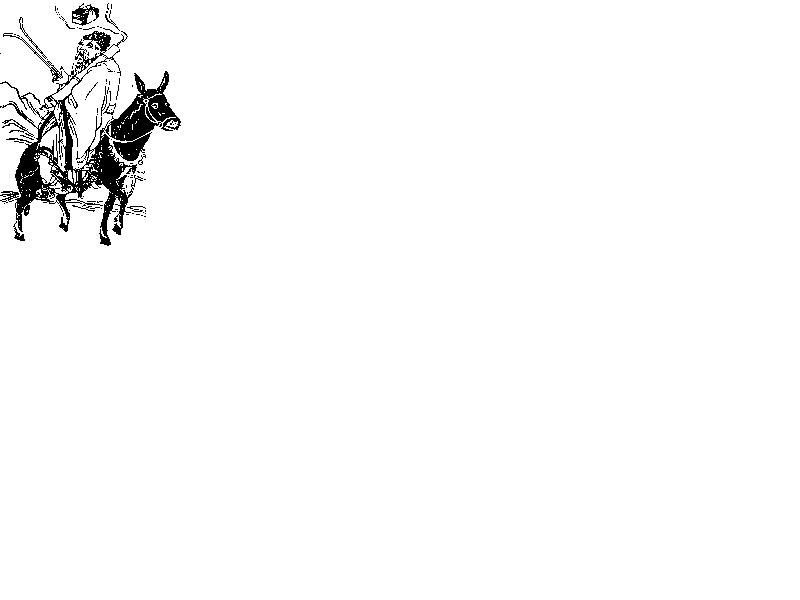
八仙人の一人に「張果老」という仙人がいる。
彼の乗り物はロバとされていて,絵画ではよく,これの写真のように,ロバに逆さ乗りした姿で描かれるから,この「あわてもの」にも,そんなふうに「世俗を超越した者」というイメージが,諧謔的な意味で重ねられているのかもしれない。ちなみに一般には,ロバもしくは馬に前後逆さに乗るもしくは乗せられる,という姿勢は,おおむね罪人が引き回されてゆくときの姿である。
――――――――――――――――――――――――

|
シュイ ニュル シュイ ニュル
水牛兒 水牛兒
シェンちゥ ちィチィアオ ホウ ちゥ とゥル
先出犄角 後出頭兒
ニー ティエ ニー マア
你爹 你媽
ケイ ニー タイ らイタ シャオ やん ロゥ
給你帶來的燒羊肉
ニー プー ちー プ ケイ ニー りゥ
你不吃 不給你留
ツァイ ナァル ノォ
在那兒呢
ツァイ フェン とゥル ホウ とゥ ノォ
在墳頭兒後頭呢
|
|
〈THE SNAIL〉
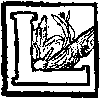 L L
|
ITTLE snail,
little snail,
With your hard, stony bed,
|
First stick out your horns,
Then stick out your head.
Your father and mother
Have brought you some food,
Fried liver and mutton,
Now isn't that good?
|
And now, little snail,
Just as sure as I say
You must eat it at once,
Or I'll take it away.
Oh where is the little snail gone, I
pray tell?
He has drawn himself up, head and
horns, in his shell.
|
|
|
まいまいつむり かたつむり
まずは角だせ おつむをつぎに
父さん 母さん おまさんに
焼き肉みやげに 買うてきた
食べないならば 残さぬつもり
どーこにおいでかネ?
お墓のもりの とびらのかげ
|
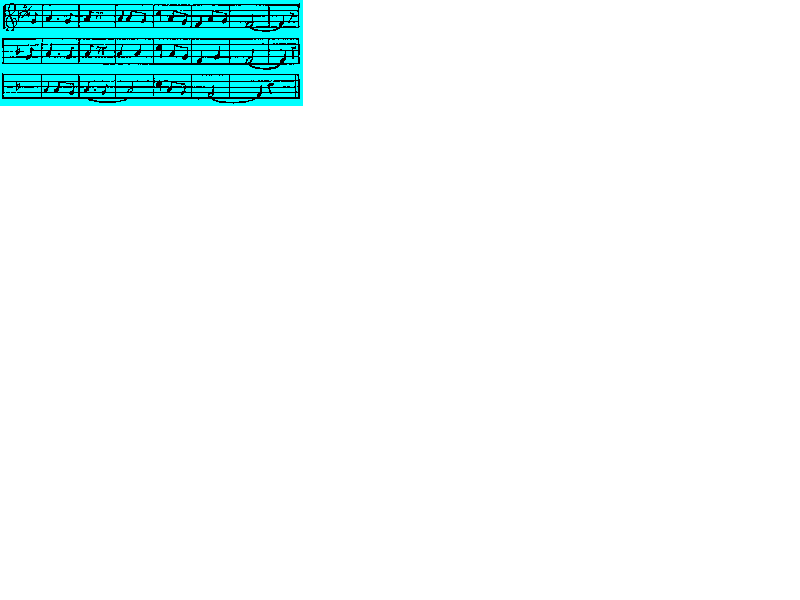
「水牛兒(shui
3niu
2r)」はカタツムリのこと。「かたつむりの角出せ唄」はほとんど世界的規模で分布しております。このとおり,中国も例外ではないわけで。本家マザーグースのはこう――
Snail, snail,
come out of your hole,
Or else I will beat you
as black as a coal.
|
まいまい まいまい
あなからでろよ
こなきゃま黒に
なるまで ぶつぞ
|
ヘッドランドは
"The Chinese Boy and Girl"のなかで‘The little folks laugh over … and are sung to sleep by the "song of the Little Snail."’と,このカタツムリの唄が「子守唄」としても用いられていたことを示唆しているが,今のところそういった例は他に見当たらない。また先行するヴィターレの例(V030-048)が――
水牛兒,水牛兒
先出犄角後出頭
你爹你媽
給你買下燒肝兒燒羊肉。
となっているのをはじめ,採集された例の多くが「燒肝(shao
1gan
1r)」(燒肝兒,キモの煮込み料理)と「燒羊肉」,という具合に料理を二つならべているおり,ヘッドランドの英訳にも
‘Fried liver and mutton’とちゃんとあるので,もしかすると本書の原文は「
燒肝兒」の字が,空きスペースとかレイアウトの関係で脱落しているだけなのかもしれない。
上に四角い石を置く日本のとは違って,漢民族の墓はもともと平地に棺を安置し,土をかけて丸い土饅頭を造ることが多かった。ちょっと金持ちになるとその土饅頭を石材などで覆って一つの構造物にするし,今はコンクリートで固めるのが普通だが,その土饅頭に盛り上がった部分を「墳頭兒(fen
2tour)」という。だからこの「お墓」というのは「カタツムリの殻」のことを指しているわけである。「在墳頭兒後頭」というのはそのまま訳せば「お墓のうしろ」ということになるが,

おそらくこの場合は「在墳頭兒的蓋後頭」すなわち「お墓の土饅頭の蓋(とびら)の後ろ」を舌足らずに言ってるのだと思う。
ヘッドランド の採譜したメロディー(右)とほとんど同様のメロディーラインを持つ版が,近年の歌謡集にも採録されているから,ずいぶん息の長い唄である。これだけ時代が離れて,ここまでメロディーが一致するというような例は,わらべ唄においてはけっこう珍しい。
――――――――――――――――――――――――
cf./同じ形式の唄については,
本書006-012のホタルの唄「火蟲兒火蟲兒…」も参照のこと。ヴァリエーションは多い。『北京民間兒歌選』(王文宝 1982 p.71)のものは4行目まで同様で「…你不吃, 你不喝,譲小狗兒小猫兒給叼了去哩。」『中国民話の会会報』(vol.3-4 1975.5)「現代中国の子供の遊び その一」にも「水牛兒,水牛兒,現出了犄角好處多。你媽,你爹,給你買了燒羊肉。你不吃,喂狗吃,狗不吃,喂猫吃,猫不吃,還是喂你吃!」という版が見える。
曲付きの採集で一番古いのはもちろん,ヘッドランドによる本書の例であるが,そのほか『歌謡週刊』2-7(羅庸「歌謡的襯字與泛聲」 1936.5.16)にも――

|
水牛儿,水牛儿,|先出犄角,後出頭|喂―。|
你爹你媽,|給你買的燒肝儿|燒羊肉|喂―。|
你不喫|[/rai]―。|喂猫吃|咧―。|
(北京 *|は小節の区切り。)
|

というのが見える。また『中国兒童民歌選集』(p.41)のものは4小節目まで歌詞が同じで,そのあとに
「…給你買的燒羊脖子燒羊肉,你要不吃,叫猫叼了去,香香香香蒿兒哉,辣辣辣辣罐兒哎,苦蔓兒哎咳,萵苣萵苣菜兒哎!」
と続いている。この後半部分で野菜の名前が続いているところは,ままごとの八百屋遊びの唄に同じようなものがあり(
V028-046「香香蒿子,剌剌罐兒…」参照),歌詞的にはいくつかの唄が合成されたものであろう。
いづれも多少キーは異なるものの,ほぼ同じメロディと言える。
**歌詞についての補足
SNAIL.txt 参照。
|
てィアオシュイタ コォ ティンチョ ウォーシゥオ
挑水的哥 聽着我説
ナンホォ イァル ニー ちャん ツァイ
南河沿兒你常在
ちィんてィエン インちィン てィアオシュイトゥオ
晴天殷勤挑水多
インてィエン らントゥオ シェンモ プーツゥオ
陰天懶惰甚麽不作
|

|
〈THE WATERMAN〉
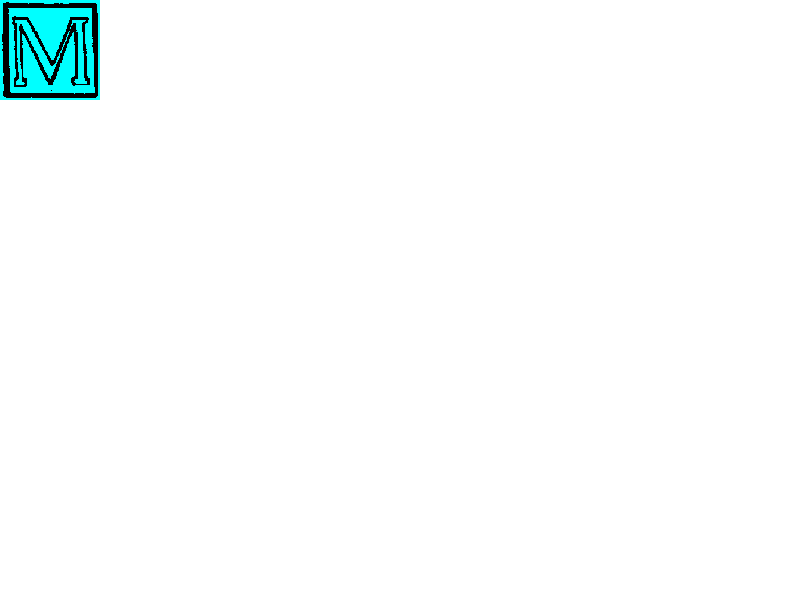 M M
|
Y brother waterman,
Listen,
I request,
|
On the south river bank
You sit and rest.
When the day is bright,
You carry all you can;
And when the day is dark,
You're a lazy old man.
水汲みあんちゃん 聞いとくれ
いつもはそこらの河岸(かし)のうえ
晴れりゃせっせと水汲みで
曇りゃひねもす なーンもせぬネ
北京では土地柄,井戸を掘っても「苦水(ku
3shui
3)」と呼ばれる塩分・カリ分を多量に含んだ水が出て,飲用に適するような井戸が少なかったので,昔は水は掛売りで来る水屋から買い,水瓶などに溜めておくのが普通だった。この水売り人夫は山東省の農夫などが一種のギルドを組んで,出稼ぎでやっている場合が多く,北京っ子たちにとって田舎ナマリの彼らは恰好のからかい相手であったようだ。訳者は山東省の人も,そこの食べ物や飲み物も大好きだが
(過去にドイツの租借地であった関係かビールが美味い),それでも「日本人(ri
4ben
3ren
2)」が「ズゥベンレン」と発音されるのにはびっくりした。
先行するヴィターレの収集(V004-007)には二句目まで同様だが――
挑水的哥,聴着我説,
南河沿兒有你的窩,
晴天晒蓋子,
陰天把脖兒縮。
|
水汲みあんちゃん 聞いとくれ
そこの河原がおまえの巣
晴れたときにゃ甲羅干す
曇りだったら首縮む
|
――と,これを河岸のカメに喩えた版が採録されている。ちなみに人をカメ(とくにスッポン)に喩えるのは,中国ではかなり手厳しい侮蔑にあたる。
――――――――――――――――――――――――
cf./歌い出しのヴァリエーションには『北平歌謡』(平171-093)の「到水的哥,聴着我説…」ではじまるものもある。『北平歌謡続集』(続121-060)の「小二哥,聴着我説,南河沿有你的窩…」もこれの類であるが,職業は特定していない。また後半の「…晴天晒蓋子,陰天把脖兒縮。」といったフレーズは,そっくりなものが北京の街巡りの唄(参照V114-155「平則門拉大弓…」)の,最後(…過去就是王八窩,晴天晒蓋子,陰天躦湯鍋。)にも見られる。「王八窩」は北京市内の貧民街。
|
ミェーミェーヤん
咩咩羊
てィアオほアちィアん
跳花牆
チュワパーツァオ
抓把草
ウェイたーニャん
餵他娘
|
〈THE LAMB〉
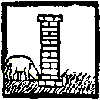 I I
|
T jumped the
chequered wall,
The bleating little lamb,
|
And snatched a bunch of grass
To feed its hungry dam. |
めぇめぇ ひつじ
柵とびこえて
草ひとむしり
母さんにあげた
「咩(mie
1)」は羊の鳴き声。ちなみに猫は「咪(mi
1)」。現在は「咩咩…」で始まる版よりは「羊,羊(yang
2yang
2)…」で始まる方が多いようで,こちらの型のほうがやや古いもののようだ。本書の例はヴィターレ(V040-062 1896)からの転載だが,李家瑞は「乾隆以來北平兒歌嬗變擧例」のなかで,清代の唱本「百本張趕板小孩語」中に見えるわらべ唄として「有個滅滅羊,跳花牆,抓把草,喂他娘。」という例をあげている。「
滅滅羊」なんて字面は凄いが,「滅」の中国語での読みは"mie"だから,何のことはない「咩咩羊」と同じ表現である。
母親が言葉を話し始めた子どもに,最初に教える唄の一つとされ。『大同民間歌謡集成』(山西人民出版 1989 p.267)には――
小羊小羊跳花墻,
抓把草草喂它娘,
他娘不吃草,
氣得小羊滿街跑。
|
(2行目まで同様)
母さん食わぬ
おこってこひつじ 街じゅうはねる
|
というヴァリエーションが見られる。また王文宝『北京民間兒歌選』(p.37)には,もうちょっと長い――
羊,羊,跳花牆,
抓把草, 喂你娘
你娘沒在家,
喂你們老哥兒仨;
你們老哥兒仨沒襪子,
打你們老哥兒仨嘴巴子。
|
(2行目まで同様)
母さんおらぬ
だんなにあげよ
靴下はかぬ
ほっぺた なぐる
|
――という版が,さらに同書 p.38には,これと出だしは同じだが,その後に典型的な「ホラ吹き唄」の文句が続いている版も引かれている
(引自「魯迅先生手抄歌謡及手絵無常像」『民間文学』1956,10)。
羊,羊,羊,跳花墻,
花墻破,驢推磨,
猪挑柴,狗弄火,
小猫兒上炕捏餑餑。
|
ひつじ ひつじ ひつじ かきね越え
かきね壊れて ロバ臼ひいて
ブタが柴刈り イヌ火をたいて
子ネコおこたで饅頭こね
|
――――――――――――――――――――――――
cf./『北平歌謡集』(平085-042)の例は『歌謡週刊』1-47「羊,羊,跳花牆,抓把草, 喂你娘,你娘沒在家,你 喂 們老哥三。」の無断転載。 『歌謡週刊』3-11には四川省の例として「咪咪羊,跳過墻, 喂你媽, 喂你娘,割把草,老娘不吃,関到門,打死老娘。」といった例が見える。 また,『古今風謠』『古謠諺』などに見える『北齊書』楊愔傳の「羊,羊,吃野草,不吃野草遠我道,不遠打爾腦。」あたりも,起源としては関係がありそうだが,なにぶん古すぎてハッキリとはしない。
らオチャん らオチャん
老張 老張
とウティんポーくヮん
頭頂破筐
チィエンツりャんパー
翦子兩把
くヮイツスゥシュヮん
筷子四雙
|
〈OLD CHANG, THE CRAB〉
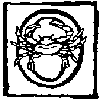 O O
|
ld Mr.Chang,
I've oft heard it said,
|
You wear a basket upon your head;
You've two pair of scissors to cut your meat,
And two pair of chopsticks with which you eat. |
チャンさん チャンさん
ぼろカゴかむり
ハサミが二つ
ハシ四そろい
ナゾナゾ…答え:
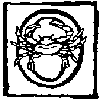 カニ
カニ。『童謡大観』(陳和祥 1922?)にも――
當門兩把大鐵鉗,
碰着東西就箝箝;
身穿鐵甲衣,
聞到薑醋勿連牽。
|
門番にゃ ふたつの大ハサミ
東西にらんでぱちぱっちん
その身まとうは鉄ヨロイ
酢醤油におへば へ~にゃへにゃ
|
八把眉鉗刀,
兩把剃頭刀;
身上背了鐵甲袍,
望着水裏汲汲跑。
|
眉切り八本
髪切り二本
総身まとった鉄ヨロイ
水に入りたや キチキチぽい
| |
と,同じ答えのものが収録されている。
――――――――――――――――――――――――

|
シィアオ ハオツル シャン トンタイ
小耗子兒 上燈台
トウユウ チー シア プライ
偸油吃 下不來
ジャオ ナイナイ ナイナイ プライ
叫奶奶 奶奶不來
ちーリウ くールウ くん シア ライ
激溜轂轆滾下來
|

|
〈THE MOUSE〉
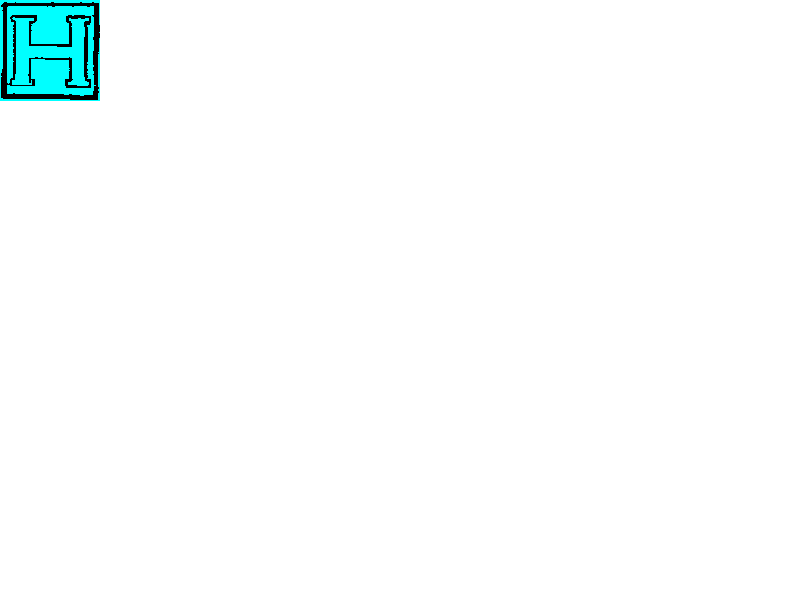 H H
|
E climbed up
the candlestick,
The little mousey brown,
|
To steal and eat tallow,
And he couldn't get down.
He called for his grandma,
But his grandma was in town,
So he doubled up into a wheel,
And rolled himself down.
|
こねずみあんどん よじのぼり
あぶらなめたら おりらんない
ばあや呼んだが ばあやは来ない
ぐるぐるくりん とびおりたィ!
|
「耗子(hao
4zi)」は北京の方言でネズミのこと。普通語では「老鼠(lao
3shu
3)」と言う。ネズミをなぜ「耗子」と言うかについては,まず清代の大学者・郝懿行がその随筆のなかで「什器を齧って耗(へ)らすからだ」と言っている。中国の古い字書『正字通』にも「俗稱鼠為"耗蟲"」とあり。さらには,金澤庄三郎先生は『猫と鼠』(昭22 創元社)のなかで,「耗子」は「マウス」と読めるので,ラテン語(mus)や英語(mouse)と同じく,梵語
musha から派生した語かもしれない――とおっしゃっております。
ともあれ,ヘッドランド がこれを「中国北方では‘
Jack and Jill’に匹敵するくらい良く識られている」という通り,中国伝承童謡のなかで,もっとも知られたものの一つで,類型は甚だ多い。文献初出は『霓裳續譜』(1795 第4巻)の「摘頭換鞋」と題される曲の一節に「…小耗子兒,上燈臺,偸油吃,他可下不來…」とあるものだろう。
先行するヴィターレの版(V097-135)は,これの前半四句のみの短い型となっている。それと同じ前四句,「
上る―盗む―下りられない」を基本型として,本書の例のように ①「ばあや(奶奶)」を呼ぶ型のほか,②『北平歌謡集』(平060-030)に見える「ネコ」の登場してくる型――
小耗子兒,上燈台,
偸油喝,下不來,
咪! 咪! 咪!猫來了,
看你下來不下來。
|
(四句同上)
ミー!ミー!ミー!猫が來て
おりるかおりぬか 見てみてる
|
③「カエル」が出てきて「お葬式」で終わる型――
小老鼠,上燈台,
偸油吃,下不來,
小老鼠哭,大老鼠叫,
一群蛤蟆來吊孝,
瓜,瓜,瓜,瓜。
|
子ねずみ燭台へ上つて
油を盗んで嘗めてたが とうとう下へ下りられぬ
子ねずみチウチウ泣き出した 親ねずみも泣き叫ぶ
蛤蟆(がま)が多くさんやつて來て
おくやみ言つて手をついて
お仕儀しながらグワグワグワ
|
(訳共・柿崎 進 『中国の民謡と童謡』(1943) p.327)
|
など,いくつかのヴァリエーションがある。「代表的な」といってイロイロ紹介されるわりには,曲の採譜例がほとんど見当たらない。かろうじて『中国民間兒童歌曲集』(p.83)に河南省の例で

|
小老鼠,上灯台,
偸油喝,下不來,
偸來油喝,下不來,
(一個得儿 一個得儿
得儿得儿哩,嘣嘣哩,
吃不一楞,得兒拉啊。)
|
こねずみ あんどんよじのぼり
油嘗めたら おりらんない
なめたら油 おりらんない
おひとつ おふたつ
とぅるとぅる ぽんぽん
食べきれないから とぅるら あ
|
というのを見つけたが,これは「打話把」,「せっせっせ」の類の遊びの唄になっているので,本書のようなわらべ唄とは違うメロディかもしれない。
――――――――――――――――――――――――
cf./とにかく目についた類例を型で分類していちおうまとめてみた。興味のある方は別表を参照。
MOUSE.html
|
チィアーツォウら チィアーこぉら
家走喇 家喀喇
マイタ ふーるー シュヮイ ぽーら
買的葫蘆摔破喇
ツァイ マイナ プー マイリィ
再買呢 不賣哩
チィアーツォウら
家走喇
|

|
〈COMING FROM THE FAIR〉
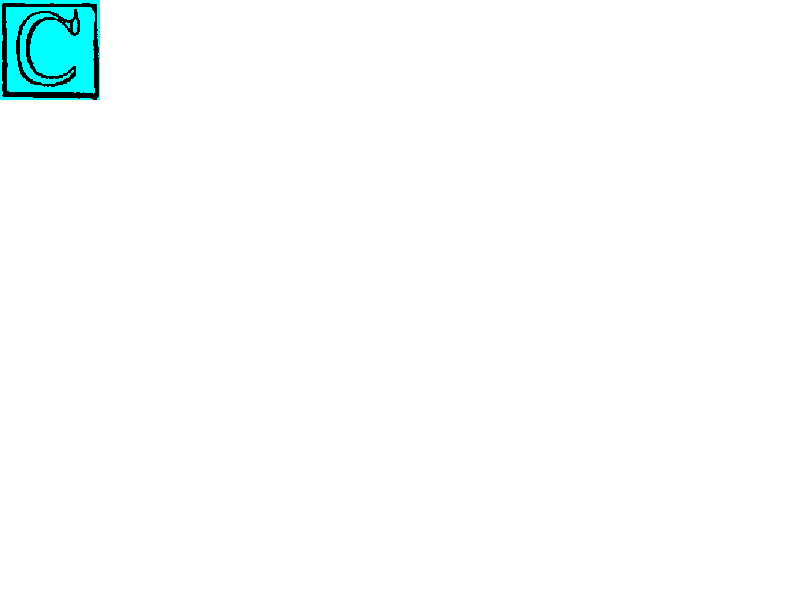 C C
|
OMING from the fair!
Coming from the fair!
|
We bought a little bottle
For our baby over there;
Alas! for we broke it,
And we tried to buy another,
But the shops were all closed,
So we hurried home to mother. |
でーておいでよ ソラおいで
買ったヒョウタン割れたとて
また買お思たが 売てないヨ
でーておいで お家から
類例が少ないもので,たんなるジングルなのか,それとも何らか遊び唄なのか分からないが,『歌謡週刊』2-12「河北兒歌」に「葫蘆(ひょうたん)」が「西瓜(すいか)」になった版が紹介されている。
家走咧,家客咧,
買個西瓜栽破咧,
饞吃咧,子兒嗑咧。(河北)
|
ちあぞうれ ちあこぉれ
買ったスイカをころんで割って
もったいないから つるこぉりぇ
|
こちらについている注によれば,一行目の「家喀(jia
1ke
2)」とは「家を出る(家去)」の意味だそうである。
――――――――――――――――――――――――
らオニュウ ウーイェン メイリィヨウ
老牛無言毎日憂
ニュウぽんイェワン るぉんフぉんソウ
牛棚夜晩冷風颼
ニュウぴー ワンクー ヨんパんター
牛皮鞔鼓用棒打
クーとウつゥオツァン ちィウポーとウ
骨頭磋簮去駁頭
りんスイクー
零碎骨
ヨウ パー トウツ ツオ
又把骰子做
ニュウロウ コォスイ ルゥ たんクオ
牛肉割碎入湯鍋
〈WHAT THE OLD COW SAID〉
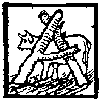 A A
|
SAD old cow to herself once said,
While the north wind
whistled through her shed:
|
"To head a drum they will take may skin,
And they'll file my bones for a big hair-pin,
The scraps of bone they will make into dice,
And sell them off at a very low price;
My sinews they'll make into whips,I wot,
And my flesh they'll put in a big soup pot."
牛さんだんまり日々ゆううつ
牛小屋夜風が吹きまする
皮は太鼓に 棒でぶつ
骨はかんざし ごましおおつむ
のこりの骨は サイコロつくる
肉は切られて お鍋のスープ
「鞔(wan
3)」は「皮を張る」という意味。
ロビン氏はこの唄を「牛のブルース」と命名して,いたく気に入っていた。
日本でも遊里なんかで「どこの馬の骨か牛の骨」と言って材料不詳
(すくなくとも金銀・ベッコウとかゾウゲではない)安いかんざしや櫛を指していたが,これは共通。またこの唄にも「零砕骨又把骰子做」(こまかく刻んでまたサイコロに)とあるが,サイコロの原形は,牛や馬の関節にある四角い骨を加工したものだったとも申します。あながち縁がないわけでもない。類例としては顧頡剛 『呉歌甲集』(1926:呉甲096-131)に――
西方路上一隻牛:
三股頭麻繩穿鼻頭。
白刀進子紅刀出。
拿我肉來大秤秤子小秤賣!
拿我皮來幔鼓敲!
拿我骨來做簪插!
拿我油來澆蠘燭!
|
西方道行き 牛一頭
麻の細引き お鼻のあなに
白刃(しらは)通れば茜に染まり
わが肉売らるよ天秤かかり
わが皮はがされ太鼓のかわに
わが骨けずられ髪飾り
あぶらしぼられ灯火とかわり
|
というのがある。
「牛の肉」というと,われわれ日本人は「スキヤキ」「ビフテキ」などと美味にして高級なものと感じておりますが,中国における牛肉の地位は,じつは最近までそれほど高いものではなかった。じっさい,こんなこともある。戦時中,山西省に学術調査隊が送り込まれた時のこと。来たばかりの調査隊員が牛肉に垂涎するのに対して,現地に長く駐留していた部隊の連中の方は「豚肉の方がずっと美味い」といって譲らなかったそうである――
「どっちがうまいか。それは問題にならない。豚の方がうまいです」
副官の中尉がはっきりと止めをさした。
「ほかのものは一切くはないで,肉ばかり食ふ生活をしてごらんなさい。牛肉をくつたあとで豚肉をくふ――その歯切のよさ,その淡白な風味,牛肉なんか臭くて問題ぢやないですな」
さういはれて見ると返す言葉もなかつた。しかし久しぶりの大きなビーフカツは素敵な味であつた。
(『山西学術紀行』宮本敏行 新紀元社 昭17 p.73)
もっとも牛肉がまったく賞味されていなかったわけではないが,それも近代になり,西欧列強の進出にともなって,租借地を中心に食肉用の牛の飼育がひろまってからのことである。『北支名物夜話』(水野 薫 昭16 満鉄社員会)「青島肉」の項には,牛の飼育が盛んであった同地方(青島はドイツの租借地であった)のこんな民謡が引かれている――
道南的,道北的,
王倆家的大閨尼,
也會走,也會扭,
又會挿花,挿枕頭,
又會拔草, 餵食牛。
(訳共・同書 p.5)
|
道を挾んで南と北の
兩家娘さんもう年ごろよ
歩く姿もちょいと百合の花
刺繍も出来るしお針も上手
それに畑の仕事が出來りや
牛も飼へるしほんにいゝ娘よ。
|
民謡・童謡においてはもちろん,牛といえば「労働力」の代表であって,本書のよりもう少し有名な唄にこんなのがある――
老牛老牛快起身,
南山有地未會耕。
(河北省 『歌謡週刊』2-25)
|
うしさんうしさんはよ起きな,
お山の畑はおこしておらぬ。
|
――――――――――――――――――――――――
|
らオヤー るオツァイ イーこォ シュー
老鴉落在一棵樹
チャんかイこウ チィウチャオふー
張開口就招呼
らオワん らオワん
老王 老王
シャンほウ ヨウコ ター ミェンヤん
山後有個大綿羊
ニー パー ター つァイら
你把他宰了
ニーちー ロゥ ウォーちー チャん
你吃肉 我吃腸
|
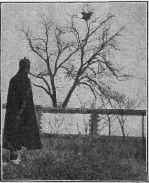
|
〈WHAT THE OLD CLOW SAID〉
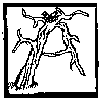 A A
|
N old black crow
sat on a tree,
And there he sat
and said to me:
|
"Ho, Mr.Wang, there's a sheep on the hill,
Which I wish very much you would catch and kill;
You may eat meat three times a day,
And I'll eat the parts that you throw away"
カラス樹の上とまってる
カラスのカアでごあいさつ
王(ワン)のおじさん王おじさん
お山のうらの羊さん
あ奴つかまえバラしちゃお
お肉はあげる ハラワタおくれ
ヘッドランドはこの唄について,由来など特に記していないのだが,おそらく「公冶長故事」に類する昔話中で唱えられていた唄の一つだと思われる。公冶長は『論語』に出てくる人物で,孔子の弟子。「無実の罪で投獄された」とされているところから,その「無実の罪」をネタにしたさまざまな民話が語られている。日本で言うところの「聴耳頭巾」型の民話で,公冶長は「鳥や獣のコトバを解する」人物とされ,彼はその能力を使って,はぐれた家畜(もしくは他人の猟の獲物)を得るのだが,そのために窃盗の罪に問われ,投獄されるが,結局は無実の罪とわかり釈放される――とだいたいこういうストーリー。明代の随筆『留青日札』にとりあげられた「公冶長故事」では,小鳥がこのような唄を歌う――
公冶長,公冶長,
南山有個虎駄羊,
爾食肉,我食腸,
當亟取之勿彷徨。
|
公冶長 公冶長
お山でヒツジを トラがひく
わたしにはらわた おまえにお肉
とりもなおさずいってみな
|
また『歌謡週刊』1-77「従古詩竄改出来的歌謡」(鍾敬文)にも――
公冶長,公冶長,
南山有個虎咬羊,
你食肉,我食腸。(海豊)
|
公冶長 公冶長
お山でトラが ヒツジ噛む
わたしにはらわた あんたにお肉
|
という例が,同様の昔話の中で唱えられる唄として引かれている。
主人公の名前がまるで異なってはいるが,この唄と「公冶長故事」の関係について,最初に指摘した朱自清は,この2種の唄が同系のものである例証として,「老王」の「王(wang
2)」と「公冶長」の「長(chang
2)」の韻が同じであることをあげている(朱自清 『中国歌謡』 p.47)。
「公冶長故事」について。『閑窓自語』(柳原紀光 日本随筆大系2-4)という江戸時代の随筆に「通鳥語女語」(鳥の言葉が分かる女のはなし)という記事に続いて,『公冶長并百鳥語』という本が,日本にも伝わっていたらしいことが書かれている。この随筆の筆者も「今は人の図にものこりしや。きかまほしき。」と言っているが。どんな本なのやら。残っているなら,わたしも見てみたいところだ。
――――――――――――――――――――――――
らーらー へイトウ
拉拉黒豆
らーらー ほァんトウ
拉拉黄豆
ティエントぉん メイリィトウ
點燈沒日頭
〈BEANS〉
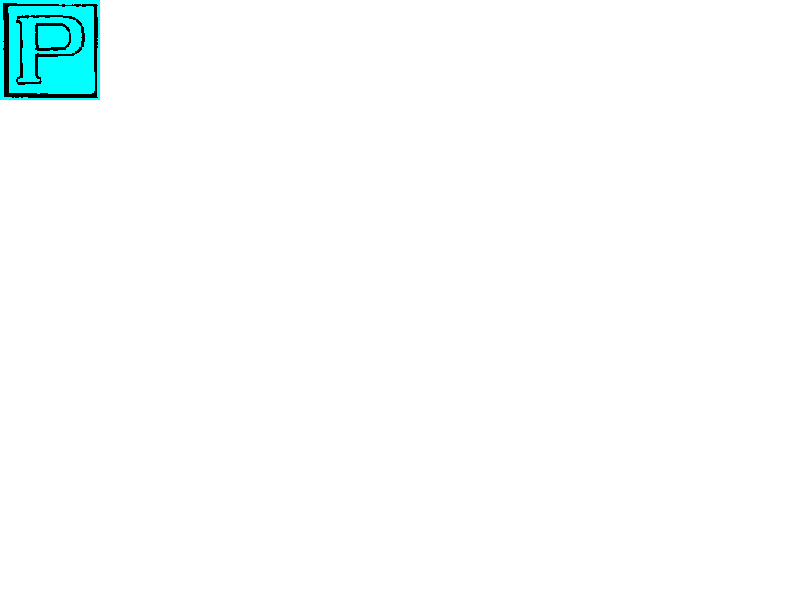 P P
|
ULL up your
black beans,
|
Pull up your brown,
Then light your lamp
When the sun goes down.
らん らん くろまめ
らん らん きいろまめ
あかりつけましょ日も暮れて
「黒豆(hei
1dou
4)」は黒大豆。「烏豆(wu
1dou
4)」ともいう。「黄豆(huang
2dou
4)」は普通の黄色い大豆のこと。
北京のわらべ唄として,けっこうよく引かれる唄なのだが,解説がついていることがないので,たんなるジングルなのか,それとも何かの遊び唄であったのかは不明。
日本における栽培植物としての豆類は,そのほとんどが中国経由でもたらされたものである。そのせいか「豆」に関するアレゴリーは日中ともにだいたい同じ。豆のわらべ唄には他にこんなのがある。たとえば『北平歌謡続集』(続179-084)――
吃豆豆,
長肉肉,
不吃豆豆,
精痩痩。
|
お豆食べれば
ころころ太る
お豆食べねば
ひょろひょろ痩せる
|
傑作である。この唄はまた,子どもたちが太鼓(太平鼓)を叩きながら舞い歌う唱え詞にもとりこまれていたようで,流行のほどが知られる。永尾龍造がそうした例の一つとして――
吃豆豆,長肉肉,
不吃豆豆精痩痩,
吃了豆豆拉臭臭,
拉了臭臭我舅舅。
|
豆を食べたら肥とった。
豆を食なべんだら痩せて来た。
豆を食べたらウンコした。
そしたらお伯父ちやんに見付かった。
|
(訳共・『支那民俗誌』第2巻 第四章「正月中の娯樂」)
|
というヴァリエーションを採集している。これも,なかなか。
――――――――――――――――――――――――
cf./朱自清『中国歌謡』(p.168) にこれを「重塁的格式」(おそらく英語で言う‘cumulateve form’の訳だろう)を用いたる唄の一例として引用しているが,これもまた解説なし。
ワイタイマオ シェチャーホア
歪戴帽斜插花
チンラコ シーフー ホイ シュワ ちャー
尋了個媳婦會耍叉
シャンピーチョ アオ ターラーシェ
苫披着襖趿拉鞋
チンラコ シーフー アイ チー チア
尋了個媳婦愛吃茄
〈THE SLOVENLY BOY〉
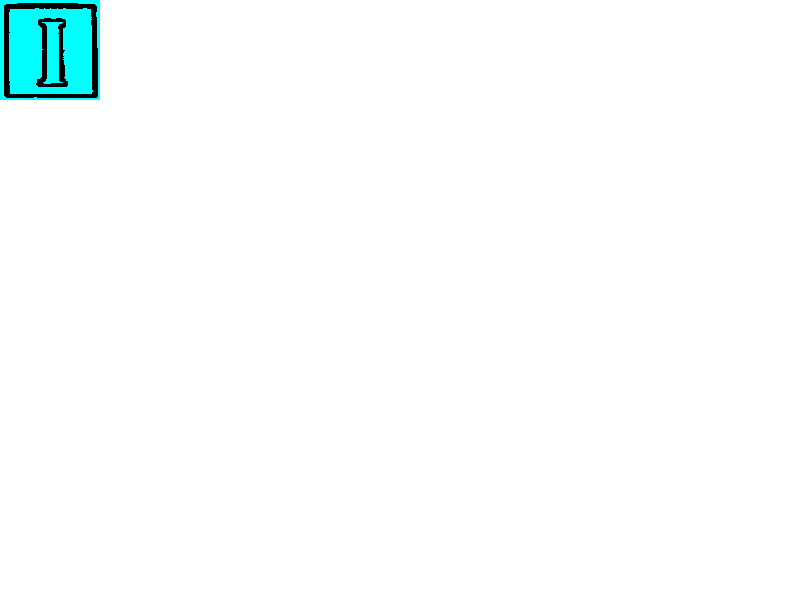 I I
|
F you wear your hat
on the side of your head,
You'll have a lazy wife, 'tis said.
|
If a slouchy coat or slipshod feet,
You'll have a wife who loves to eat.
帽子もはすに 花させば
もらう嫁さん疳のムシ
破れ上着に つっかけ靴じゃ
もらう嫁さんタバコ好き
「服装の乱れは心の乱れ」というのはいつの世にもある考え方で。旧時,男女の結婚は,親または縁者によって,当事者の意思・好みに関わらず「運命的」に決められていたから,配偶者がどんな相手かというのが「天罰」になりえたわけです。
「耍叉(shua
3cha
1)」というのは「騒動をおこす」とか「もめ事」,すなわち‘trouble maker’といった意味だが,元来は鉾をふるって戦うこと,また鉄の三叉鉾をぶんまわす大道芸のことだから,そういうムキムキの暴れん坊と言う意味にもとれる。ヘッドランドが
"…Boy and Girl" のなかで
‘ Boys are warned of the dire consequences …'(男の子ならこの恐ろしい結末に震え上がることだろう)と言っているほど,英訳はさほど恐ろし気でもないが,もしこういうことなら確かにコワい。
「趿拉鞋(ta
1la
1xie
2)」というのは靴のかかとを踏みつぶし,つっかけること。
またヘッドランドは「食いしん坊」と訳しているが,「吃茄」の「茄」はこの場合「雪茄烟(xue
3jia
1yan
1)」すなわち英語の‘cigar’(シガー)の音訳を略したものであろう。すなわちタバコ好き,それもおそらく「洋モク好き」。つまりモダン好みの蓮っ葉娘だ,と言っているのだと思う。
――――――――――――――――――――――――
cf./『大同民間歌謡集成』(1989 山西人民出版社)p.182に,これを貧乏人のつぶやきとした版がある:「歪戴帽,拖拉着鞋,想娶個媳婦没一個錢。」(はすの帽子に ひきずり靴よ 嫁さんもらうにゃゼニがない)
また同様の歌詞は,他の民謡中のフレーズとしても見られる。『偃師縣風土志略』(河南省 民国23年 第五編):「槐樹槐,槐樹涼下搭戲臺。去教三姐看戲來,不知三姐來不來。尋個女壻不成材。歪戴帽,踢拉鞋,又吃煙,又打牌,鬧的一家八家過不上來。」
イーチュワ チンル
一抓金兒
アルチュワ インル
二抓銀兒
サン プシィアオ シ ハオ レンル
三不笑是好人兒
〈GRAB THE KNEE〉
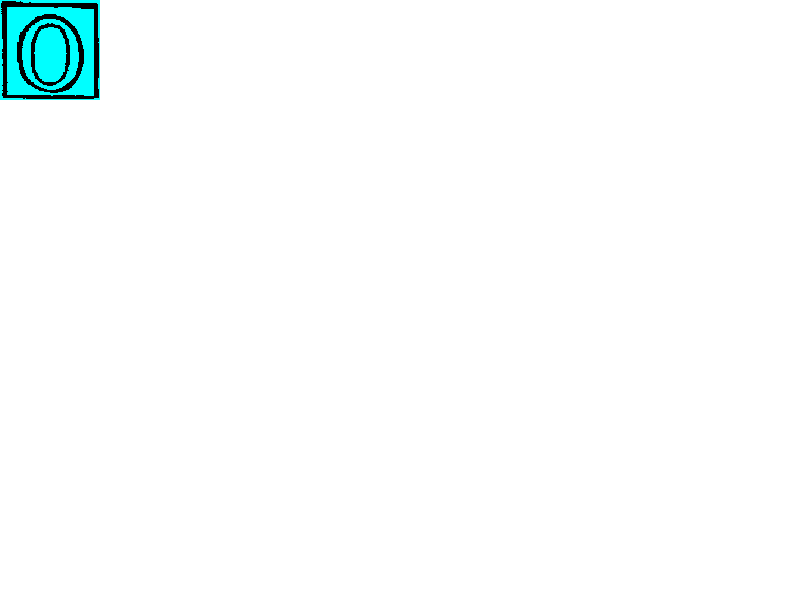 O O
|
NE grab silver,
Two grabs gold,
|
Three don't laugh,
And you'll grow old.
ひとこちょ こがね
ふたこちょ しろがね
さんこちょ 笑わにゃ りっぱだね
からだ遊びの唄。ヘッドランドは
"…Boy and Girl" p.28 でこの唄を英語の――
If you are a gentleman
As I suppose you be
You'll neither laugh nor smile
At the tickling of your knee.
|
さてもあなたは
紳士さまでしょ
くすりもあははもいけないよ
おひざをこちょこちょちょ
|
と対照させて,中国人の乳母やが,同じように子供のひざ小僧をくすぐるときの唄として歌った場面が描かれている。『歌謡週刊』2-1「兒的唱法」(徐芳)には,母親もしくは乳母やが,指で子供の掌のまんなかをくすぐるときの文句だともある。まあ,『北京民間兒童娯楽』(p.1-2)のいうように「子供をくすぐってはしゃがせる」ときに唱えられる唄の一つ,と言うのが妥当なところか。
正月元旦の朝,家の門前を掃き清めながら唱える呪詞に,これと似た「一掃金,二掃銀,三掃聚寶盆…」という唄がある。家の繁栄を願ったものだが,これも同様に子供の成長を願って唱えられる呪歌の意味合いもあるかもしれない。
――――――――――――――――――――――――
cf./ヴァリエーションとしては『北平歌謡続集』(続031-016)に「一抓金,二抓銀,三抓不楽,是好人。」,また『淮陽郷村風土記』(河南省 民23年)に「一抓筋,二抓銀,三抓不笑是個大好人。」(筋=金)などがある。この二例はヘッドランドの記述と同じく「膝をくすぐる」唄としているが,『各省童謡集』(浙江省杭縣 各092-048)「一掬金,二掬銀,三掬不笑是好人。」では「腕をまっすぐにのばさせて血管の上を指でくすぐる」と注されている。
また『兒歌三百首』(p.54) にも,「一抓金,二抓銀,三抓四抓茶葉,五抓六抓抓個人。」(湖南) と,これの類唄が見えるが,注によれば,当地ではこれが目隠し鬼の「鬼決め唄(counting-out rhymes)」として用いられているという。
FOR ENTRANCE
前の頁
次の頁