ある日,まだ一歳七ヶ月のわが娘と,食卓を囲んでいたときのこと。母親の膝の上にいた彼女のすぐそばで,拾ったゴム人形を,ちょっと乱暴にはたいていたら。娘ははじめ驚いたような顔をし,ついで顔をしかめたかと思うと,見る見る涙をあふれさせて母親に嘆願したものである。
「お願い!パパにお人形さんをいじめさせないで!」
「おもちゃ」というものが,子どもたちの人生にとって,どれほど重要な役割を果たしているのか――これを理解しているオトナは少ない。大部分のオトナにとって,それらは「子どもたちのために作られた遊戯道具」程度のものでしかない。しかし,それは「おもちゃ」の使われかたから言っても,また,おもちゃとコドモの関係から言っても,じつに狭量な見方である。
おもちゃ作りの根底には一種のテツガクがあり,その歴史はこの世界と同じくらい古く,人の人生と同じくらい深い。そして今なお,そのテツガクには,少なからぬ研究と研鑚が積み重ねられている。
玩具というものは人類にとって,食物や薬と同じくらい必要不可欠な構成要素であり,じっさい,それらと同じくらい人間の健康や民族の文化的発展に貢献している。調理や医療における学問と同様,おもちゃ作りという職業も,厳格なる先達たちによって支えられてきた。その目的とは当然,彼らによって生み出されたものに興味をしめしてくれた,小さな紳士淑女の「長所」に,ばん健やかなる自己啓発をうながすことである。
子どもにとって,おもちゃはまさしく商売道具。手職をみがく工具であり,生業を営むための道具であり,商売上売り買いされるモノであり,また自分の造り上げた「おもちゃの世界」に指令を下すための軍配。そしてまた,しもべとなる動物であり,楽しませてくれる仲間ともなり,かりそめの家庭に喜びをもたらし,慰めとなる子どもたち,ともなるのだ。
おもちゃこそは彼らを自然界へと導く最初の教師である。子どもは小さなシャベルや,鋤や草刈り鎌を手にして,農業の初歩を学び。トンカチやクギを持っては,種々の職業訓練への第一歩をしるす。子どもがオトナへと踏み出してゆく折々のきっかけは,こうしたおもちゃによってもたらされるのだ――かのリンネウス(注)の父親は,まだ幼い時分の彼を自分の花咲く庭へといざなった。そして,それこそが「疑いなく,この幼子をして,長じてのち,植物学,そして自然科学の祖たらしめんとした」のであり,けっして「血筋」がどうだとか言ったうわけではなかったのだ。
化学教室で行われるどんな実験も,少年時代に管と,石鹸水をいれた壷を手にやったシャボン玉遊びよりも,不思議だなあとか面白いとか思えはしないだろう。幼い少女たちのこしらえる,泥まんじゅうとか色んなお菓子のまがいモノは,お料理教室の第一講であり。ままごと遊びと人形のお家でのお茶会は,接客作法の第一歩。そして人形遊びによって,少女は家庭内の感情の機微や,家族への愛情のありかたを心にはぐくみそめるのである。
 世に「なんとか学」と名づくもののなかで,アジアに起源をもち,またそこで完成の域にまで達したような学問は一つもない。まあだからといって,ヨーロッパ人やアメリカ人が鼻をひくつかせながら,他人種を見下し,自慢してまわる理由にはならないが。なぜなら,われわれはそうした「なんとか学」と同じくらい重要なものを,このアジア圏から賜っているからだ――そう,アジアの外に発生した「宗教」で,なんにせよマトモなところまで成熟したものはないではないか。
世に「なんとか学」と名づくもののなかで,アジアに起源をもち,またそこで完成の域にまで達したような学問は一つもない。まあだからといって,ヨーロッパ人やアメリカ人が鼻をひくつかせながら,他人種を見下し,自慢してまわる理由にはならないが。なぜなら,われわれはそうした「なんとか学」と同じくらい重要なものを,このアジア圏から賜っているからだ――そう,アジアの外に発生した「宗教」で,なんにせよマトモなところまで成熟したものはないではないか。とはいえ,このことこそまさに,この中国というアジアのなかでもっともアジアらしい国において,おもちゃ作りを専門とする企業や,児童教育を対象とする高度な学問というものが,見あたらない理由のようなものだ。ヨーロッパにおいて,とうにれっきとしたビジネスや学問の対象となっている「子どもの遊び」や「おもちゃ作り」が,アジアにおいていまだしなるは,ちょうど天文学が,アジアにおいても古来よりずっと研究されてきたのに,それを「科学」にまで高めたのはギリシャ人であったというのと同様。西欧では幼稚園で教えるようなことを,ここ東洋ではいまだ街の辻々で学ばせているし,西洋では巨大な商用施設で大量生産されている子どものおもちゃも,ここ東洋では貧しい女性の手によって家内生産されているのみである…ほかも諸事,ご同様である。
とはいえ。中国のコケコッコ笛も,ゴムでできたわたしたちのそれとまったく同じように,ひとつでイヌの「わんわん」も出せれば,赤ん坊の「おぎゃー」も,ウマの「ひひーん」や羊の「めええ」,ウシの「もー」も出すことができる。同じようなひとつの事柄には,おなじような結果が出るもので。たとえば中国の少女の,2,3銭から高くても20銭で買えるお人形も,地球の反対側にいる彼女の姉妹たちの,2ドル,3ドル,あるいは20ドルもする人形も――彼女らの胸のうちに,ひとしく母性本能をはぐくみ,かつ一方でめっぽう手荒なあつかいを耐えつ忍んでいる。それでいて,彼らの迎えるは最期は一様に悲惨なものだ。この世からのお別れには,手をもがれ,足をもぎとられる。もちろん,そこには外科手術のような悠長なプロセスなどない,そんなものだ。

中国の玩具は概して,多様性がなく,複雑でなく,原形に忠実でなく,そして西洋のそれほど高価ではない。たぶん1~2世紀ほど前の,わたしたちの世界のおもちゃもこんなだったのだろう。そんなおもちゃでも,いったん男の子や女の子の手に渡れば,太鼓はちゃんとタントンと鳴るし,ラッパはぷーぷー,笛はぴーぴーと鳴り響く。ギンガムのワンコやキャラコのニャンコも,それぞれの土地で,より親しまれているそのほかの――土くれから造られた――動物たちも,おのおのその土地において,その動物の鳴き声をあらわすコトバによっていなないている。どの国でも同じ,おもちゃというものは総じて,その国の「ちっちゃなマフェット嬢ちゃん(little Miss Muffet)」や「ちっちゃな青ちゃん(little boy Blue)」たち(注)の好みにぴったりあうように造られるものである。
もうすこし大きくなると,子どもたちは,コマ(注)をまわしてうなりをあげさせるにせよ,ブーブー笛(注)を鳴らすにせよ,玉の鈴を揺らすにせよ,カタタン車(注)をひっぱるにせよ,より彼らの好みにあった音,先祖から受け継いだ嗜好により合うような音を出すモノを求めるようになる…それらはコドモたちの仕事(すなわち,遊び)や生活のなかにとりこまれ,やがてはホントに生きているかのように,自在に声をあげるようになるのである。そのためにもまた,彼らの人形たちは,そのふた親の産たる子孫,すなわち彼ら子どもたち自身そっくりに造られているのである。
中国の玩具には,むずかしい科学的な原理に従って作られているようなものはない。西洋のオルゴールも,ここ中国においては,高価な「輸入品」であるということ以上には知られていないし,中国人は,瞳を開いたり閉じたりする人形(このからくりは,ごくシンプルなものだが)についても,ちょっとミステリアスなバネ仕掛けが内に仕込まれていて,ひとりでに動くようになっているおもちゃについても何も知らない。そもそも,どうやってそのバネを造ればいいのかについてさえまだ知らないのだ。
とはいえ,そういう科学的な原理を応用したようなおもちゃもあるにはある。もっとも,こうしたことは,その原理を理解して作ったわけでなくとも,利用することはできるものであるが――たとえば,空気は熱せられると膨張し,循環をはじめる,といったようなことを。この原理は「回り灯籠(とうろう)」に活かされている。この灯籠の上のところには十字に台木が渡されていて,そこに紙でこさえた輪車がとりつけられており,その車に吊るされた紙の男や女が,さまざまな動物たちとともに,陽気なメリーゴーランドを演じるようになっているのだ。これはつまり,二十年ほど以前なら,アメリカの雑貨屋や田舎の郵便局の片隅のストーブの上にかならず,カラカラと回ってたあれ――木挽や穴掘り人夫,鍛冶屋や洗濯人夫たちの姿をかたどったモール飾り――と同じ仕掛けである。(注)
中国のおもちゃを研究するにあたって,わたしが一番はじめにしたことは,信頼がおけて,そうしたおもちゃをまっとうな価格で買うことができるような中国人の知り合いに声をかけ,北京市内で見つかる限り,さまざまな種類のおもちゃを買ってきてもらうことだった。
依頼した初日,彼は「ガラガラ(rattles)」のほか,何も買ってこなかった。これは彼が「ガラガラ」こそ,生まれた子どもがまずひきつけられる,「最初のおもちゃ」である,と考えたためである。
その日の夕刻,シン氏はけっこう大きなサイズのカゴに,いっぱいガラガラを入れて戻ってきた。
あるものはブリキ製で,シリンダーのような形で取っ手のところに小さな丸石が入っているものや,桶のようにストンとした形のもの,また鍋やフライパンみたいな形のものもあった。
またいくつかは木製で,極彩色で彩られており。中空の玉やザル,あるいは桶や瓶の形をしていて,それに長い取手か首,もしくは柄のようなものがつけられていた。この日のガラガラのなかでは,この種類がもっとも美しかったのだが,その表面の彩色はたまたまそのおもちゃで遊んだ最初の子にくっついて,ほどなくはがれて落ちてしまった。「その子」は,もちろんわが幼き娘であるが。
こうしたガラガラのなかで,もっとも庶民的なものは,身近な家禽類や,未知の動物の形をした土製のものである。この種類には,サンタ・クロースを思わせるころころと肥った僧侶や,それで遊ぶ子どもたち自身にそっくりな――ずんぐりむっくりな子どもの――形のをしたものもあった。(注)
子どもの成長にともなって,ガラガラは竹や木のわくに,皮(魚の皮であることも珍しくない)を両端に張って,長い柄を付けた太鼓型のものが好まれるようになる。その側面には,二本のみじかい紐の先端にビーズをつけたものが下がっていて,ガラガラを手のうちで回すと,これらが太鼓の面を打つようになっている。この真鍮やブリキ,また竹で作られた太鼓型のガラガラは,よく行商人が客寄せに持って歩いているもののイミテーションである。(注)
「外国人は "中国には人形というものがない" と言っているが,どうなんだい?」
そう,わたしが尋ねると,シン氏は「いや,たくさんあるよ。」と,例のステロタイプな言い回しで答えた。
「じゃあ,明日は見つかるかぎりの人形を全部買ってきてくれないか。」
「全部?」ちょっと驚いたような声で,彼は聞き返してきた。
「うん,全部。中国におよそどんな種類の人形があるのかを知りたいんだ。」
次の日の夕刻,シン氏はステキに大量の人形を抱えてやってきた。
彼の持ってきた布人形は,大きいのも,小さいのも,中くらいのも,糸でかがった鼻に,糊でくっつけた耳,ほかの部分は絵具で描き込んであるもので,じつに雑な造りだが。そのうち一つを,わが娘にあげてみたところからすると,子どもにとってはこういうものも,よりリアルで高価な人形と同じくらい魅力的なものらしい。じっさい中国在住の西洋人の子どもたちはよく,アメリカやヨーロッパからもたらされた同様の人形より,中国のこうした布人形のほうに愛着をもつようになるものらしい。
シン氏が持ってきた人形のなかにはまた,ねりものの頭と皮製の胴体に,粘土でつくった手足をもつ大小の人形があった。これらは胴体部分がふいごのようになっていて,リードがしこまれており,ごく幼い子どもでもワンワン笛やコケコッコ笛のような音が出せる仕掛けになっている。これらの人形の頭部には本物の髪の毛が,ちょうど彼ら中国の子どもたちがしているのと同じように[*唐子髷に]ちょん,ちょんと植えられており,さらにここの赤ん坊たちが夏にするのと同じような服装(すなわち腹掛けに,靴をかズボンを穿いただけ)をしている。(注)

シン氏はここで,小さな包みをとりだした。中には半ダースかそこらの,中国語でいうところの「小人兒(シャオレル)」(注)が詰まっていた。この「小人兒」は,頭から手や足までぜんぶ紙製,精緻な彩色が施されていて,極上の絹の着物を纏ってはいたが,その頭のてっぺんに,絹糸の輪っかが付けられており。わたしにはいわゆる「お人形さん」ではなく,壁に吊るす飾りのように思われた。
「シンさん,これはなんだい?」わたしはシン氏にたずねた 「こいつは‘お人形’じゃないだろう?」
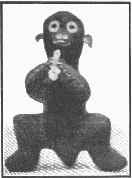 「いいや」と彼は答えて 「これはね,こっちにある布の動物たちで子どもたちが遊ぶときにつかう‘お人形’なんだよ。」
「いいや」と彼は答えて 「これはね,こっちにある布の動物たちで子どもたちが遊ぶときにつかう‘お人形’なんだよ。」われわれの指摘を見越してか,彼は布のラクダの一大コレクションを持ってきていた。全体ラクダ色の布でこさえられていて,頭や首,コブや脚の関節のところだけに,ちょこちょこと房毛が植えてあり。ちょうど木の芽どきの,毛がわりのころのラクダといったていである。(注)
ゾウもあった。灰色がかった生地でできていて,その背にはこうした動物を使役するときに用いられるようなハーネス(注)がちゃんと付けてある。 クマもあった。首と尻尾のところにわずかに毛が植えてあり,鼻面には引きひもが付けられている。(注) ウマは白と赤に塗り分けられていて,どうみても「サーカスの曲馬」といった感じ。 サルには黒いビーズ玉の眼に長いしっぽ。 ライオン,トラ,ヒョウには,大きくて,いまにも咬みついてきそうな,真っ黒なガラスの眼玉と,それぞれの特徴に合わせた,たてがみとかしっぽがついており,しっぽには先っぽまでハリガネが通っていて,いかにもらしく曲げてある。(注)
最後に彼がとりだしたのは,「お化けちゃん」であった。
それはライオンかトラみたいな頭が,胴体の両端についている,なんだか得体の知れない動物で。おもちゃとして使われるのではなく,本来マクラとして用られるものである。(注)
「おもちゃの動物はもうほかにないのかい?」
「いいや」彼は答えて言った。
「明日持ってくるよ。」
 つぎの夕刻,シン氏はまさしく枚挙の暇がないというほどたくさんの,粘土でつくったおもちゃを持ってあらわれた。これらのうち,ウマ,ウシ,ラクダ,ラバ,シカのほか大半は,人々の想像の産物でしかない動物たちであった。
つぎの夕刻,シン氏はまさしく枚挙の暇がないというほどたくさんの,粘土でつくったおもちゃを持ってあらわれた。これらのうち,ウマ,ウシ,ラクダ,ラバ,シカのほか大半は,人々の想像の産物でしかない動物たちであった。口を引かれたロバに女の人が乗っているもの。またウマにのった男が疾走するトラを弓で,もしくは投げ槍でやっつけようとしているもの。そして赤ん坊を腕に抱いた女性の横に,その子をあやそうとガラガラを振るおばあちゃんがいて,父親がアヘンパイプをふかしてながまっている,というものもあった。

つづいて,カゴの底の方から,彼はおびただしい数の小さな包みをとりだした。
「それは何だい?」
「土でできた虫だよ」
それらはまさしく,わたしがいままで中国で見た中では最高のねんど細工だった。フンコロガシにバッタ。カマキリが二種類。ヒキガエルにサソリ。そのほか中国では珍しいものから,中国ではぜんぜん見られないものまで。粘土の虫たちの足と触角は,細いハリガネで作られていた。
べつの包みの中には,1ダースばかりもの踊り子人形(dancing dolls)が入っていた。粘土製で1インチ半(約4センチ)くらいの大きさ。紙でできた服をまとっており,16分の1インチ(約1.5ミリ)ほどの細いハリガネが服のすそからつきだしている。彼はそれを全部を真鍮のトレイのうえに並べると,ちいさな棒でもってそのふちをたたいて振動させた。すると人形の踊り子たちはくるくると,いろんな方向へ回り出すのだった。
つぎの包みに入っていたのは,土でできた乞食の人形たちである。まず,二人でケンカしているもの――ひとりがもう一方のあたまに,土でできたツボを叩きつけようとしている。次はふざけてツボをあたまにかぶっているもの,三番目のはものを食べているところで,左右の二人は自分たちの分を手づから運んでいるところである。また一体は片足が爛れていて,よく見ると口を開いて顔全体で苦悶の表情をあらわしていた。

べつの包みからは,いくつものからくり人形(jumping jacks)が出てきた。見たところ,それらは日本のものを模倣してつくったもののようである。「サルの曲芸」は,ねんどでつくられたサルが,ハリガネと皮紐で細長い竹の板にくくりつけられている。(注)また棒にくくりつけられている人形の手に,シンバルが持たされていて,その辮髪をひっぱるとそれを鳴らすようになっているものもあった。(注)さいごの一個は大きな「龍」である。これは,そのために作られた専用の土人形を二~三体ごちそうしないと,その大いなる怒りを静めることができないという仕掛けになっていた。
 しかし,おそらく,この日彼が持ってきたおもちゃのなかでもっとも傑作だったのは,土笛の類である。焼きものか日干しの粘土でつくられたこれらのおもちゃは,中空で。さまざまな鳥や獣や虫の形をしており。息を吹き込むと,笛としてはかなり甲高い音が出るようである。またほかに,リードの付いた笛の類もあったが,こちらは先に述べた人形型の笛の同類で。多くは本体に空気を吹き入れるための,ふいごのようなものが付けてあって。それにより,ニワトリはコケコッコ,イヌはワンワン,赤ん坊はオギャー(まあ,どれも同じ声調ではあるが)と,泣くことができるようになっているものである。
しかし,おそらく,この日彼が持ってきたおもちゃのなかでもっとも傑作だったのは,土笛の類である。焼きものか日干しの粘土でつくられたこれらのおもちゃは,中空で。さまざまな鳥や獣や虫の形をしており。息を吹き込むと,笛としてはかなり甲高い音が出るようである。またほかに,リードの付いた笛の類もあったが,こちらは先に述べた人形型の笛の同類で。多くは本体に空気を吹き入れるための,ふいごのようなものが付けてあって。それにより,ニワトリはコケコッコ,イヌはワンワン,赤ん坊はオギャー(まあ,どれも同じ声調ではあるが)と,泣くことができるようになっているものである。「明日はなにをもってきてくれるの?」
「うーん…太鼓に,刀,それとコマってとこかな。」とシン氏。この日までに,彼はわたしがさいしょに渡した資金を使い果たしてしまっていたが,彼の購入計画にはまだまだ先があるようだった。
つぎの夕刻,彼はおもちゃの太鼓をたくさんもって現われた。そのうちのいくつかは,全体として胴の真ん中あたりがふくらんでいて,樽みたいなかたちをしていた。太鼓の皮の面には明るい色調で,甲冑や晴れ着を身にまとった男女が描かれていて,家内の騒音に悩まされるオトナたちにとって拷問具でしかないこれらの太鼓を,みごとな芸術作品にまで高めている。
おもちゃの刀は輝くばかりの光彩を放っていた。おそらくは簡単なメッキがほどこされているのだろう。それにたくさんの三叉鉾。これらには音で敵を威かすための,金属板,もしくはシンバルのようなものが,ゆるくとめられていた。
シン氏が集めてきたコマはどれも,すばらしく興味深いものだった。中国のコマは他に類を見ない代物である。それらはじつにシンプルな造りで,竹でできており,一本のヒモによって回される。そして,うまく操るとひゅるるんと甲高い音が発せられるようになっている。
打ち独楽(注)は軸が無く,ただの木のかたまりをコマの形に成形しただけのものである。ヒモをつかって回すところは同じだが,あとはそれを鞭打つようにして回し続けるのだ。
これらとは別に,外国人は総じて「コマ(tops)」と呼んでいるが,そのじつ西洋で見られるそのどれとも異なるおもちゃがある。中国人はそれを「クンチュン」(K'ung chung 空鐘)と呼び,わたしたちが言うところのコマのことは「トゥロゥ」(t'o lo 独楽)と呼んでいる。(注)クンチュンはおもとして竹を輪切りにした二つの部品によって構成されている。どちらも同じコマのような形になっていて,たがいはその両端の重さがちょうど釣り合うように,精妙に調整された一本の横軸によって接合されており,見た目には馬車の車輪というほかない様子をしている。これを二本の棒にとりつけられた一本のヒモを,軸に一巻きさせてから回すのであるが,上手な者は,これを足の上下をくぐらせたり,背後で回したり,くりかえし20~30フィートも高く宙に放り上げては,落ちてくるところを受け止める――といったふうにさまざまに回すことができる。これをそうやってうまく操るうえでの極意は,一方の棒をきゅっと引いた瞬間,もう一方のほうをすこしく緩めてやるところにあるようである。(注)

「――明日はね」コマ回しをやめて,シン氏は言った。
「おもちゃの馬車を持ってくるよ。」
中国の馬車は,サラトガ・トランク(注)に輪っかを二つくっつけたようなかたちをしている――と言われている。しかしながら,じっさいにそんなかたちをしているのは,乗り合い馬車だけで,ほかにも色んな種類があるのだが。それらもすべておもちゃになっていた。馬車のおもちゃにはみな,オルゴールのようなからくりが付けられており,車軸がまわるのにつれて,じっさいの馬車そっくりな音を出せるようになっている。
おもちゃの馬車は,ブリキと木とねんどによって作られている。紙で作った幌をのせただけの単純なものもあれば,街頭馬車の備品すべてがそろっているような手の込んだものもあった。馬車を引くラバをとりはずしてみたところ,これがなかなか良い出来であったので,そのまま置いておいたら,ほどなく彼がエサを貪り食うかわりに,自らが虫の餌食となってしまった。こうしたおもちゃはたいがい,永らえたとしても,次の季節までには,たてがみやしっぽ,それに身体の皮の大部分までなくなってしまっている。
馬車の荷台の真ん中には,くるくる回る木釘がつきでており,そのうえに小さな泥人形が一個据えられていて,それが棒の動きに合わせてくるくると回転するようになっている。またほかの泥人形はみな,荷台の左右に渡されたハリガネにとりつけられている,これらは御者と乗客をあらわしたものである。

シン氏はつづいてカゴの底から,品の良い作りのちいさなパグ犬(pug-dog)のおもちゃをいくつもとりだした。胴体に仕込まれたふいごを押すことによって鳴くようにできている――もっとも,その音は数日前のコケコッコ笛と同じではあるが。
さて,こうして色々と述べてきたが,これらはシン氏が持ってきてくれたもののほんの一部についてでしかないことを断っておこう。また,ここにも述べたようなさまざまな種類の安物の土人形を,街中を流しながら,一個あたい5分の,もしくは10分の1セントくらいで売っている男が一人いるのだが,彼といっしょによく一人の飴細工売り(注)を見かける。この飴細工売りは吹き管と溶かし飴(taffy-candy)の入った鉢を持って,人でもニワトリでも,馬車だろうが麦の穂だろうが,まるでガラス職人が瓶やランプのほやを吹くみたいにして,子どもの望む通りになんでもたちまち吹きこしらえてしまう達人である。子どもたちは彼の「作品」を飽きてしまうまでもてあそび,そして――食べてしまうのだ。
第5章 おわり