「まざあ・ぐうす」がひとつの国,ひとつの民族だけの存在だと思っているなら,それは大間違いというものだ。
彼女はどこにでも,かの老婦人は世界じゅうあまねく存在するのである。
ヨーロッパやアメリカとおんなじように,もちろんアジアにも。
いずくにありとも子を持つ母あれば,おばあちゃんあり,そして乳母やあり。ゆえに「まざあ・ぐうす」――いや,「まざあ・ぎいす」とでも呼ぶべきであろうか? もっとも,この老婦人のことを複数形でどう言えばいいのか見当もつかないけれど――ありきである。たとえばインドの「まざあ・ぐうす」は,わたしにこんな唄をうたってくれたし,
日本の「まざあ・ぐうす」は子どもの手を握って,ちょうどわたしたちが「これが教会,これが塔…」(注)をやるように――
と唱えていた。ここに言う「親」は親指,「子ども」は他の手の指のことである。
そして「中国のまざあ・ぐうす」。
わたしがこれまでに彼女の中華風コレクションのなかからひっぱり出した唄は,六百首あまりにもなるのだが。まずはわたしがどうやって,そんなに唄を集めたかについてお話しするとしよう。
それは夏休みの,とある暑い日。
北京から西へ15マイルほど。丘の中腹にあるとあるお宅で,ベランダに腰掛けていたときのことである。C.H.フェン夫人からふと尋ねられたのは――
「あんな唄のことをご存じかしら,ヘッドランドさん?」
「なんの唄のことです?」と,わたし。
 「ほら,ばあやのインさんが,いま息子のヘンリーにうたって聞かせている唄のことなんですけどね。」
「ほら,ばあやのインさんが,いま息子のヘンリーにうたって聞かせている唄のことなんですけどね。」「…いやあ,気がつきませんで。彼女にもう一度歌ってくれるように,たのんでもらえませんか。」
フェン夫人が言って,かのばあやが歌ったのが次の唄である。それはちょうど,「ちゃんと見てなきゃ,小鬼に捕まる…」(注) に良く似た調子の唄であった。
わたしはばあやにもう一度,こんどはもっとゆっくり歌ってくれるように頼んで,その歌詞を書き取り,訳してみた。
この中国の唄の内容の方が,わたしたちの「ジャックとジルの唄」のそれより,世間様に通りの良いものであろうことは,わたしも認めざるをえない。だいたいこの有名な二人,「二人で水を汲みにゆく」なんてまえに,そもそもジャック氏が一人で運んだとかいうのならば,「優しい!」とか評判になったろう,さもなくば「頭が割れちゃい」ながらもジル嬢が「すッ転ぶ」のを防いだとか…せめてそんなふうに,彼女を転落の危機から護ったとか,楽させてあげたとかいうのならば,この唄が人気のある理由も,いくらか合点がゆくのだが。
 このように,唄に人気がある理由というものは,それがシンプルかつリズミカルで,なにより子どもたちのお気に入りである,という事実をのぞいては説明することができないものだ。しかしながら,この中国の唄の原文は,その歌詞や調子のよさといった点は「ジャックとジル」の唄と同じようなものなのに,ストーリーの方はより好ましいものとなっている。なにせ悲劇的な結末なしで,もっと "科学的に転がって" いるうえに,「ジャック・スプラットの唄(注)」なみに,道徳的な内容をも含んでいるのだもの。
このように,唄に人気がある理由というものは,それがシンプルかつリズミカルで,なにより子どもたちのお気に入りである,という事実をのぞいては説明することができないものだ。しかしながら,この中国の唄の原文は,その歌詞や調子のよさといった点は「ジャックとジル」の唄と同じようなものなのに,ストーリーの方はより好ましいものとなっている。なにせ悲劇的な結末なしで,もっと "科学的に転がって" いるうえに,「ジャック・スプラットの唄(注)」なみに,道徳的な内容をも含んでいるのだもの。この唄はじっさい,中国北部では英国と米国の「ジャックとジル」に匹敵するくらい広く知られている。中国の子どもたちに「 "ちっちゃなネズミちゃんの唄" を知っているかい?」と尋ねてみるがいい。その子はちょうど英語圏の子どもたちが「ジャックとジルの唄」を歌うみたいに,立て板に水といったようすで歌ってみせてくれることだろう。
その唄は子どもたちのお気に入りかって?
それはもう。その唄は彼の人生の一部みたいなものなのである。たとえば,こんどは逆に,その唄をあなたが彼に歌って聞かせてみたらいい。一語でも違えようものなら,彼はプンプン怒ってしまうことだろう。
ちょうどあなたが,あなたの息子さんや娘さんを前にして,つい――
Jack and Jill
Went down the hill
Went down the hill
なぞとやってしまった時のようなものである。
こんなふうによく知られた童謡を,子どもたちの覚えているのとわざと違った風に歌ってみたら一体どんなことになるか。想像してみるといい。
さて,ネズミちゃんの唄も書き取り終わり。
わたしはインさんに,他にも唄を知っているかどうか尋ねてみた。すると,彼女は微笑んで「たくさん」知っています,と言う。そこでわたしは彼女と交渉して,唄が良くても悪くても平凡でも――というのもわたしは,どんな種類のものでもぜんぶ確保しておきたかったからだが――とにかく一首聞かせてくれたら500錢(3セントくらい)はずむ,という約束で聞かせてもらうことにした。
その結果。
それ以前にわたしが知っていた中国のわらべ唄というものは,親馬鹿とでもいう愛情発露の唄か,下品で粗野そのものというようなものでしかなかった(もちろんこの後者に属するものは,乳母たちが子どもに,ではなく。子どもたちが自分で歌っていたものだが)。 しかし,インさんから1ダースあまりもの唄を教えてもらい,まもなくそれらの唄を中国語で歌えるようになってからというもの。これらの唄のおかげで,男性,女性,子どもたち――わたしは逢う人逢う人の,中国人の心のより深いところにまで,入ってゆくことができるようになったのである。
またある日,わたしはちっちゃなロバの背にゆられ,コウリャン畑(注)を通ろうとしていた。
ロバの背が低いので,足を地面にひきずってしまいそうになりながら,わたしはかのわらべ唄のいくつかを口遊んだ。するとロバの口取りをしていた御者が,ふと話しかけてきたのである。
 「ほお,だんな,そんなわらべ唄までご存じなんで。」
「ほお,だんな,そんなわらべ唄までご存じなんで。」「ああ。おまえ,ほかになにか知らないかい?」
「ええ,たくさん知ってまさぁ。」
(この「たくさん」というのは,中国人の口癖だ。)
「じゃあなにか聞かせておくれよ。」
「ようがす…では,こんなのはご存じで?」
わたしはロバからとび降りるとその唄を書き取り,前とおなじように彼にも,知らない唄一首につき500銭,と話をもちかけた。
こうして,市街と行き来する道中,会話のあいま。ばあやや使用人たち,個人的な友人や教師たち,子を持つ親やその子どもたち,そして中国で生まれ育ち,乳母やからわらべ唄を教わっている外国人の子どもたちからも。わたしはその夏休みの間じゅう唄を集め続けた。
そして秋になんなんとするころ,わたしの手元には50首以上もの,もっとも親しみ深い,つまりは北京とその周辺でもっともよく知られたわらべ唄を得るにいたったのである。
数ヶ月後,街にもどったわたしは,ある巡回牧師からイタリア公使館の通訳官・ヴィターレ男爵によって出された,北京の民俗に関するある書物[* "CHINESE FOLKLORE--PEKINESE RHYMES"(1896)(注)]のことを教えてもらった。このような本こそ,まさしくわたしが求めていたものそのものであったが,250首あまりもの唄を集めてはいるものの,彼の訳は散文体(韻文体ではなく)だったし,おまけにかなり不穏当な表現まで,何ら削除することなく,そのまま本にして出版してしまっていた。
やがて,わたしがわらべ唄を集めていることを聞きつけて,帝国の各所から唄が送られてくるようになった。『中国人気質』("Chinese Characteristics")の著者として有名な,アーサー・H・スミス博士は,山東省の唄を300首以上も集めて送ってくれたのだが,この中には,わたしがすでに北京で見つけたある唄に,よく似ている唄が混じっていた。さらにその後,わが小さな友人・チャルファン嬢から,同じ唄の,同じ山東省内でもスミス博士とは異なる地方における,別のヴァージョンを受け取り,ここにおいて,わたしが知っている中国の「このブタさんは買いものに…」(This pig went to the market…)(注)に類する唄は,少なくとも5つにはなった。

|
こうしたわらべ唄は,中国では出版物として刊行されたことがない。とはいえ,われらがまざあ・ぐうすだって,1719年以前にはご同様だったのである(もっとも,例のボストンのお話し(注)を信用すればのはなしではあるが)。わらべ唄というものは本来,子どもたちの心と記憶によって受け継がれるものだったからだ。そしてまさにそこに,わたしが唄を集めるうえで経験した,最初の難関があった――つまりいかにして完全な唄を採録するかということである。たとえば,
「ジャックのお家」(House that Jack built)(注)
を,はなからおわりまで,ぜんぶ暗唱出来る人はそれほどいないだろう。活字にされたものがいくつもあり,誰しもが幼い頃ぜんぶ教わったはずなのに。
まして中国においては,その難は十倍である。なにしろ,この国ではわらべ唄がいままで活字になったことがないのだ。おまけにひとつのオリジナルからは様々なヴァージョンが派生している。これは疑いなく乳母やたちが,唄を部分的に忘れてしまっているのに,子どもたちを楽しませるために,つぎたしたりしながら歌い聞かせたためであろう。
つぎの難問は,どこからも文句がつかないようにするには,いったいどんな収集をつくればよいのか,ということであった。中国の古典は世界の古典文学中,もっとも純粋無垢なものであるが,せっかく伝えられたそんな精神文化の産物をさえ,まるで自分のモノのように,あえて汚すようなことをする人は結構多いものである。じつに多くの唄がそのような受難にさらされ,結果,ある唄にはこっそりと悪態の意がひそめられ,またある唄には,口にするのもはばかられるようなこととか,極端にわいせつなことが平然と歌いこまれてしまったりしているのである。
三番目の問題はいちばん最初と二番目のものよりずっと大きい。
それはこうした唄を「韻文で」訳すということの難しさである。
読者諸氏が,先年出版された拙著『中国のまざあぐうす』の中から,わたしの翻訳のしようもない個所を見つけることは,疑いなくたやすかろう。なにせわたし本人でも,「改善の余地のある」個所よりも「どうしようもない」ところを見つけるほうがずっと簡単なくらいなのだから。とはいえ,オリジナルの唄に出てくるじつに多くのコトバは,その文字や意味について記されたものがなく,ちゃんと字があるものでも,わたしたちのスラングのように,辞書に載っていないコトバもまた多いのだ。
さて,ここいらで話しをこうした「文字なき児童文学」のもっと楽しい面に向けてみることにしよう。言語というものにはすばらしい韻律がみちあふれている――なれば言葉の不都合のあるような部分も,韻律を損なわずに削ることができるはずである。何らかの不当な手が加えられたように,ではなく,まるでもとからなかったかのように。
どこの国でもわらべ唄には,虫や鳥,獣や人物,しぐさや商売や食べ物や子どもたちのことが描かれているものである。わたしが集めた中国のわらべ唄のなかにも,昆虫なら,コオロギやセミ,クモ,カタツムリ,ホタル,テントウムシ,それにチョウなどについて歌ったものがあり,羽根のあるやからならばコウモリ,カラス,カササギ,オンドリ,メンドリ,アヒルやガチョウについて歌ったもの,獣でいえば,イヌ,ウシ,ウマ,ラバ,ロバ,ラクダ,そしてネズミの唄など,すばらしいものがいくつもある。さらにはヘビとカエルのことを歌ったものあり,そのほかにも名所や事物,そして人物―男や女,それに子どもたち―について歌ったような唄も無数にある。
中国人は子どもを愛していないなどという感情を抱くものたちは,こうした彼らのわらべ唄に触れてみたことがないのだ。
この地球上のありとあらゆる言語のなかで,中国の子どもたちに歌われているわらべ唄ほど,痛烈かつ思いあふるるようなものは存在しない,わたしはそう信じている。
たとえばある親御さんが子どもにむかって――

とか――
なぞと歌い聞かせているところを見たならば,あるいは父親か母親,もしくは乳母やが――乳母はときとして彼女らの小さな預りものを両親とほとんど同然に可愛がるものであるし――子どもをその胸に抱きしめ,彼がどれほど愛らしく思われているのかを「この子可愛いや人殺しィ」(注)などとつぶやいているところを見たならば,即座にその真価を認めるざるをえなくなるだろう。
こうした子どもの唄のテーマのなかで,どこの国のものにも見られる大事な要素がほかにもある。
すなわち,「食べ物」である。
「ジャック・スプラット」(注)に「ちいさなジャック・ホナー」(注),「二十と四羽のクロウタドリ…」(注)に「アーサー王の御時世にゃ」(注)…わが言わんとするところを含む唄は,ほかにもまだいっぱいあるだろう。
小さな子どもというものは,すごい勢いで成長してゆく胃袋のようなものである。その食欲中枢に訴えることすべて,空きっ腹を満たすためのことならなんでも,文学に昇華させてしまうのだ。このゆえに人気のあるわらべ唄というものはすべからく,「なにか美味しいものを食べる」ということを,その最大のテーマとしているものである。とはいえ,こんな唄には要注意――
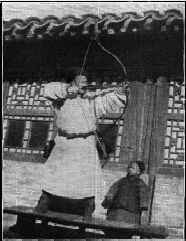
「中国人ってカラスを食べるの?」などと,読者諸氏が眉をひくひくさせながらつぶやいているさまが目に浮かぶが。思い出して欲しい。あなたがただって小さい頃から「王様」のために作られる「見事な料理」の材料が「二十四羽のクロウタドリ」であっても,そのクロウタドリが本当に美味しいのかどうかについては,何の疑問も湧かなかったはずである。
つぎに記すべき点は,すべてのわらべ唄はさまざまな人々の手を――実際には口を――経ることによって出来上がってきたのだ,ということ。
たとえばあるとき,アメリカ人かイギリス人の子どもが,ある情け深いご婦人が,おなかをすかせた飼犬にあげる骨を納戸に見つけられなかった,というお話しを聞いたとしよう。彼の気持ちは同情であふれかえり,やがて奮起して尋ねたことだろう。「そしてそれから?」「どうしてお肉じゃダメなの?」「ワンちゃんは本当に死んじゃったの?」そこで乳母やは,子どもの好奇心を満足させ,かつ,婦人と犬,両者のジレンマを解消させるような,さらなる唄句をこさえなければならなくなった。そして,それがのちへと伝えられ――唄の流れから「ハッバードおばさんの唄」のできたきっかけを読み取ると,およそこんな感じであったろうことは容易に想像がつく。「ハッバードおばさん」の唄のオリジナルは,おそらくその最初の,六行三韻で構成されている部分でしかなかろう。それだから他の句はすべて,四行一韻の形式のみでまとめられているのだ。(注)
同様のことは中国のまざあ・ぐうすの唄にも見られる。一つの例として,次の唄をあげよう――
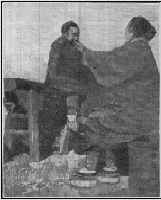
これがオリジナルの唄句であった。これにのち,2節の唄句が,韻律も筋も,調子や道理やせっかくの良い風味をも無視して加えられたのである。そう,このような――
…ぶたれて母さん窓まで跳んだ
窓には格子ありません
ぶたれて母さん鏡見た
鏡にゃ台がありません
ぶたれて母さん唄歌う
唄のしまいをしりません
ぶたれて母さん猿回し
くぐらすその輪がありません
ぶたれて母さん天国へ(注)
窓には格子ありません
ぶたれて母さん鏡見た
鏡にゃ台がありません
ぶたれて母さん唄歌う
唄のしまいをしりません
ぶたれて母さん猿回し
くぐらすその輪がありません
ぶたれて母さん天国へ(注)
わらべ唄に込められた道徳的な教えは,その唄を唱える人々自身のモラル,それ如何によってどうにでもうつろうものである。すでにあげた「ちっちゃなネズミ」の唄の内容には,悪いことに対する警告と,その罪の報いとがこめられている。燭台をよじのぼってロウソクをぬすんだネズミくん(注)は降りられなくなった。それは盗みに対する罰というものであるが,そこには同時に,子どもたちに対して,もしお母さんのいない間に納戸へいって,許しもなしに甘いお菓子をせしめたりしたら,このネズミくんと同じ目に会うよ,という教えが暗に示されているのである。「ネズミくん」はそこで再三,彼にとって後光さすほど慈悲深き存在である「おばあちゃん」を呼ぶ。しかし,彼女はこない。このことは子どもたちの心に深く共感を呼び覚ますことだろう。結果は見えている,そう,ネズミくんは自分から「宙返りをして」,「床に転げ落ち」なければならなくなるのである。
子どもたちに盗みを戒めようという唄はほかにもある。しかしその報いを説く脅し文句は,子どもたちを更正させようとする約束,というよりは,むしろ両親や乳母やのたんなる不信感のあらわれのようにも見える。
さて,男の子ならこの恐ろしい結末に震え上がることだろうが…もし帽子をはすにかぶったり,破れた上着の着た切りすずめや,靴のかかとを踏んだまま外に出たりしたらどうなるか?というと――
――と,まあこんなぐあいだ。
両親の,子どもへの愛情のあらわれであるわらべ唄は,子どもたちの心のなかに同様の情愛を培いもする。中国のまざあ・ぐうすのなかに「小さな白菜の歌」と題される,なんともせつない物語の唄がある。一人のぼうやが歌うには――
|
ちいさなコマツナ黄色くしぼむ
七歳八歳お母は死ぬる お父のいい子で過ごしてきたが 後妻とったらなんとしょう もらって三年したならば 生まれた兄弟にゃかなわない あっちにゃおかず,わたしにゃお汁 えんえんしくしくおッ母思う(CMG) |
 |
こんな唄を聞いて,子どもたちの心の中に哀愁や同情の念が育たないはずはない,だから自然,困っている人々に,より親切に,優しくできるようになるのである。
またある唄の少女は,想いに駆られてチョウチョを追いかけはするが,それを捕まえようとはしない。(CMG)思うにこれも,彼女が「虫の気持ち」にまで共感したためであろう。
 はなはだ残念ではあるが,もちろん中国のわらべ唄のすべてが,このように高いモラルをもっているというわけではない。たとえば彼らの唄の中では,仏教の僧侶にたいする尊敬の念はまったくといっていいほど欠落している。「尊敬の念」など,わらべ唄にもりこむ必要がないというまえに,それは僧侶にたいしては必要ない感情だとされているからだ。とはいえ,これは子どもたちの情緒形成上はじつに残念な傾向である。僧侶にたいする唄ではきまって,剃髪しているそのおつむに攻撃の手が向けられる。(CMG)また,ある唄では,彼らの頭を「ひょうたん」だと言い(CMG),ある唄では彼らを虎のような貪欲な猛獣と同列に扱ったりもしている。(CMG)
はなはだ残念ではあるが,もちろん中国のわらべ唄のすべてが,このように高いモラルをもっているというわけではない。たとえば彼らの唄の中では,仏教の僧侶にたいする尊敬の念はまったくといっていいほど欠落している。「尊敬の念」など,わらべ唄にもりこむ必要がないというまえに,それは僧侶にたいしては必要ない感情だとされているからだ。とはいえ,これは子どもたちの情緒形成上はじつに残念な傾向である。僧侶にたいする唄ではきまって,剃髪しているそのおつむに攻撃の手が向けられる。(CMG)また,ある唄では,彼らの頭を「ひょうたん」だと言い(CMG),ある唄では彼らを虎のような貪欲な猛獣と同列に扱ったりもしている。(CMG)ところで,中国人には何にでも(それこそもう,帝国の頂点に位する御方から,路傍の乞食にまで)アダ名をつけたがるクセがあることは,いくつかの唄から明らかである。たとえば,現王朝の長であり,宰相,皇帝の親友でもある大人物でさえ「せむしの劉」で通っているし,「あちゃ眼の王」,「足曲りの張」,「禿頭の李」などと呼ばれているものもいる。こうした身体的な欠陥や,精神的特徴などは,なんでもそのアダ名のネタとなりうるのである。もちろん,わたしたちのような外国人も,この国民的令名の悪癖からは逃れられない。
たとえば,顔にアバタ[*天然痘の痕]のある者は,次のような唄でもって子どもたちにからかわれる。ほかにもことごと,いろいろな例はあるが,ここではほんのさわりだけにしておこう――
中国人はわたしたちがふだんするのとは反対のことをしている,ということが中国人の特質としてよく語られる。わたしたちはよく,彼らのそうした「さかさま」のやりかたを批難するが,しかしそのような責めはわたしたちこそうけねばならないものなのかもしれない。なぜなら彼らにしてみれば,それこそ自分たちの「正しい」やりかただからである。たとえばわたしたちは親愛の情をあらわすため互いに手を握りあうが,彼らは自身の手を組んで握る。わたしたちは敬意を示す行為として帽子をとるが,彼らはかぶったままである。わたしたちは喪にさいしては黒い服を着るが,彼らは白い服を着る。わたしたちはベストを上着の内側に着るが,彼らは外に着る。こうしたことはほかにも数知れず,あるいはこれらほど日常的でないことのなかにも,同様のルール,わたしたちにとっては本末転倒なやりかたでおこなわれていることは多い。ときに,彼らのわらべ唄のなかにも,言うことなすことすべてが「馬の前に荷馬車」[*“Cart before the horse”本末転倒。]な調子になっているものがある。たとえばこんな唄――語り手は言う「外の騒ぎが聞こえたので,見てみるとイヌがヒトに噛まれていた」,もちろん彼はすぐ助けに入ろうと「扉をあげて,お手々をあけ」,「犬を拾って,レンガにぶつけ」たのだが,その「レンガが彼の手を噛ん」だので,彼は「ラッパを叩いて,太鼓を吹いて」いる光景をあとにした,などというものである。(CMG)
舌もじりの唄(注)は,英語のそれと同じように中国でも一般的なもので,同じくらい子どもたちの間で行われている。もっとも,こうした唄は概してその国の言語以外への翻訳は不可能なものだ。
また,あるわらべ唄では,菓子売りがステントール(注)ばりの大声を出して,公衆に呼びかけている。いわく,彼の商品は「めしいた者の眼をすら開く」そして――
――唄はさらに「禿頭に毛が生え」「気弱な亭主も強くなる」と続く。
ぎゃくにまた別の唄では,実の母親に鞭打たれ続けてきた一人の少女が,ひとり静かにつぶやく――結婚したなら,自分がどれほど夫を愛し,彼のため,彼だけのためにつくすか,たとえ,さげずむべき義理の母親を「お母さん」と呼ぶはめになろうとも……と。そのつぶやきを耳にした,彼女の怒れる両親が「何か言ったか!」とたずねると,彼女はこう,答えるのである――
これは親不孝な子の唄というよりは,女の子たちへの応援歌,ととったほうがいいだろう。というのも中国では,女の子をもつ親は,彼女が自分の母親にうんざりして「義理の母親」を望む(結婚したいとおもう)ようになるよう,厳しくしつけるものだからである。
ほか,ある常套句をかしらにすえた一群のナンセンス唄がある。それらはどれもこれもただ道理に欠けていて,わたしにはお世辞にも「よいナンセンス」な唄だとは思えない。まあ批評家がそういう唄についてどうのこうの言ったところで,じじつそれらは子どもたちの間ではポピュラーなのだし,わらべ唄に関する限り,その最高裁判所は子どもたち自身なのではあるが。たとえばこんな唄がそうである――

|
中国の乳母やたちは,からだのあちこちに関する唄をじつによく頭に容れている。たとえば手の五本の指で遊ぶときの唄,あるいは足の爪先をつまむときの,また膝小僧をつかんでくすぐりながら,子どもに笑うのを我慢させるときの唄,顔の各部とその感覚を対応させた唄,あるいはおでこをドアにみたてたり,さまざまな感覚を綴った唄――最後は,もちろん,おチビちゃんの首筋をくすぐって終わるのであるが。
これら中国の子どもたちのあいだにおこなわれている唄,そのどの唄をとっても「ちっちゃなぶーちゃん市場まで」(little pig went to market)とか「おでこにゃやっとこ,めんめはぱちぱちや」(forehead bender,eye winker)などといった,われわれの似たような唄が思い起こされる。たとえば両親か乳母やが,子どものつまさきをつまんで,わたしたちがわたしたちの子どもに「ちっちゃなぶーちゃん」をして喜ばせてあげるように,小さな東洋の子どもには次のような唄が唱えられるのである――

そこで,彼女はふざけてそのちっちゃな裸足の指をはじくのだ。これが手の指になると,指を一本一本手にとってゆきながら,両親もしくは乳母やはこんな唄を唱えるだろう――
 この種の唄には,土地により,さまざまな型のものがある。ちなみに上掲の例は山東省のものだが,北京では――
この種の唄には,土地により,さまざまな型のものがある。ちなみに上掲の例は山東省のものだが,北京では――――という唄が唱えられている。
次の唄は…まあ,見てのとおりのことではあるが。乳母やがおでこをとんとんと叩き,ついで,眼,鼻,口,そしてあご,と触れてゆく唄である。こう,唱えながら。
この終いの二行で子どものくびすじをくすぐるのである。
ちなみに,英語のわらべ唄にこんなものがあり――
If you be a gentleman, As I suppose you be, You'll neither laugh nor smile With a tickling of your knee. |
もぉしもオトナなら どぉぞおねがいよ にこりもくすりもなぁしよ おひざをこーちょこちょ |
何ヶ月ものあいだ,わたしはこうしたゲーム――指や,顔や,からだをつかったもの――がほかにもっとないかと求め続けたのだが,とうとうわが家の乳母どのにも,いままでお教えしたもののほかにはもうなにひとつ知りません。と,きっぱり言われてしまった。ところがある日,ふと気がつくと,その当の乳母やが,うちの娘の膝をにぎりながら,これにそっくりな,こんな唄を口遊んでいたのである。
中国という国おいては,文学作品にせよ,宗教上の聖典にせよ,わらべ唄とはりあえるほど,広く一般に知られているものはない。わらべ唄は,有識者にも無学な者にも,王様の子どもから乞食の子にまで,あまねく聞き知られ,唱えられているのだ,すべて民族の,心と精神の結晶として。そして,これら小さな国民たちは,牛を笑い飛ばし,小白菜(こまつな)に同情してむせび泣く,ちっちゃなネズミからモラルとは何かを学びとり,ちいさなカタツムリの唄(CMG)で眠りにつくのである。
彼らだってときには,ほかの国の子どもたちと同様,唄に歌われているようなことごとの信憑性に疑問をもったりもする。たとえば,こんなことがあった。あるとき,我家の年老いた乳母やが子ども部屋で子どもたちに,いくつもの物語を語り,数多くの唄を歌って聞かせていた。彼らははじめ,老女の口からすべりだす数々の神話に,何の疑問もはさまず,神妙に耳を傾けていたのだが,まもなく彼女のお話しが一つの風の唄におよぶや,たちまち彼らの不信感がかまくびをもたげ出したのである。こんなぐあいに――
風おばあちゃん風吹かせ
ロバにまたがり東のはて
雨ふりばばあ雨ふらせ
馬できました北のはて
雪のばあちゃん雪ふらせ
鶴でとんできた西のはて
カミナリおばちゃん稲妻おとせ
黄狗またがり南のはーて (注)
ロバにまたがり東のはて
雨ふりばばあ雨ふらせ
馬できました北のはて
雪のばあちゃん雪ふらせ
鶴でとんできた西のはて
カミナリおばちゃん稲妻おとせ
黄狗またがり南のはーて (注)
「…ねぇ,ばあや。“風おばあちゃん”なんて,ほんとはいないんでしょ?」
「ええ,もちろんですとも。でもね,みんな風のことを“風おばあちゃん”って呼ぶのよ。」
「じゃあ“雨ふりばばあ”なんていうのはなぜ?」
「たぶんね,雨が降りそうな天気だと,みんなよくいやな気持ちになるからじゃないかねぇ。」
「そしたらなんで雪は鶴に,カミナリは黄狗(ホァンコウ 注)に乗っているの?」
「たぶんねぇ,鶴は雪みたいな色しているからじゃないかしら。それにカミナリってイヌみたいにすばしっこいし,色もなんとなく似てるじゃないの。」
第1章 おわり